- ウスバカゲロウの幼虫って蟻地獄?
- ウスバカゲロウは幼虫期間も毒がある?
ウスバカゲロウの幼虫は蟻地獄なのでしょうか。蟻地獄は捕まえたり飼育したりできるのでしょうか。
そのためにはウスバカゲロウの大きさや毒も気になります。

そもそもウスバカゲロウそのものがよくわかりません。
わかりました。ではウスバカゲロウの生態や種類、寿命や卵などについてもご紹介しましょう。
ウスバカゲロウの幼虫は蟻地獄でOK?
この動画にあるように、ウスバカゲロウの幼虫は蟻地獄です。
成虫と幼虫では全く姿が違いますね。体の色は砂と同じ色なので、砂の上にいるとあまり見分けがつきません。
卵から孵化した蟻地獄は、家の軒下などの砂地にすり鉢状の巣を作り、そこで餌を捕食します。

どうやって巣を作るんですか?
地面の土を放り投げて作ります。
砂を投げると大きなものは遠くへ飛んでいきますが、小さな砂は近くに落ちます。
小さな砂で作られた蟻地獄の巣は急斜面となるので、罠にかかった虫は脱出しにくくなるんですね。
面白い動画があったので、ご紹介させていただきます。
虫が罠にはまったら、蟻地獄はその虫に砂を投げつけて、脱出の妨害をします。
が、結構な割合で虫は脱出するようです(笑)
蟻地獄といっても餌は蟻だけではなく、いろんな小さな虫も捕食します。
捕食する動画もありますが、苦手な方はご遠慮ください。
生体や大きさは?

蟻地獄の大きさはどのくらいですか?
だいたい体長1センチ前後くらいです。 結構小さいですね。
後ろ向きにしか歩けず、間違って蟻地獄の外に出ようものなら、蟻の集団に負けてしまうくらい弱いそうです(笑)
なのでずっと穴の中にいるのかもしれませんね。
幼虫の間はだいたい1~3年くらいで、餌を多く食べれば成虫になるのも早いです。
また、2~3か月くらい餌にありつけなくても小さく縮まって生存することができるそうです。
食事の仕方がちょっと変わってます。
とらえた餌に消化液を注入し、体の中の栄養分を溶かして吸い上げます。
そして吸い終わった餌は、巣の外に放り投げるそうで、何ともお行儀の悪い食べ方ですね(笑)
でも必要な栄養分のみ吸収するというのは、ある意味効率のいい食事の仕方ではあります。
糞をしないって本当?

蟻地獄は糞をしないって本当ですか?
そうなんです! びっくりしちゃいますね。
でも食事も栄養分のみを吸収するので、糞となるような余分なものがないとも言えます。
蟻地獄は罠をしかけて餌を捕獲するので、ただただ餌がやってくるのを待つしかありません。
いつ来るかわからない餌、下手をすると1か月も食事にありつけないこともあります。
そのため糞をせず、一度食べた栄養分を次の食事までもたせるという仕組みのようです。
しかも尿すらも出さない、とずっといわれていました。
ところが、なんと千葉県の小学4年生が新しい発見をしたんです!
それは蟻地獄のお尻から黄色い液体が出ていることでした。
黄色い液体・・・想像するに尿、要するにおしっこですね。
まだ正確なことは証明されていないようですが、よく発見しましたね。
このような発見をするには、蟻地獄を飼育しなければなりません。
さて、蟻地獄は飼育することができるのでしょうか?
蟻地獄の捕まえ方と飼育の仕方
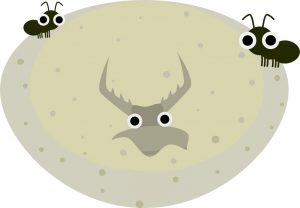
捕まえ方はとても簡単!
こちらの動画をご覧ください。
なんと掌で簡単に捕まえることができちゃうんですね!
素手であのグロテスクな蟻地獄を捕まえるなんて、わたしには絶対に無理ですが(笑)平気な方は平気なようですね。
飼いたいけど触るのはちょっと・・・な方はシャベルなどを使うか、厚手のゴム手袋などを使うと良いと思います。

巣はどうやって見つけるんですか?
雨が当たらないような家の軒下、木の根元などの乾いた砂地をよ~く見てください。
すり鉢状の穴があれば、だいたい蟻地獄だと思って良いと思います。
静かに近づいて、穴の2倍以上深いところから砂をすくいあげてみましょう。
慎重に砂を振るい落としていくと、きっと姿を現してくれると思います。
次に飼育の仕方です。
これも本当に簡単なんです。
- 容器
- 捕まえてきた場所の砂
誰でもすぐに飼うことができますね(笑)
容器は穴が作れるくらいの高さがあれば、逃げ出すことはありません。
また羽化するまでは蓋も必要ありません。
捕まえてきたところの表面の砂は乾いていますが、中の方は湿っています。
あまり乾燥させないように、水分には気を付けてあげてください。
容器を置く場所は、風通しが良く半日蔭の場所がおススメです。
蟻地獄の餌

蟻地獄は美食家でもなく、蟻しか食べないわけではありません。
餌は小さくて柔らかい虫なら何でも大丈夫です。
餌をたくさん与えると早く成長し、逆に少なく与えるとゆっくり成長します。
複数の蟻地獄を飼うなら、餌の量を変えることで、成長の違いを観察することができますね。
蟻地獄からウスバカゲロウへ
幼虫が蛹(さなぎ)になることを蛹化(ようか)といいますが、だいたい蟻地獄の蛹化時期は梅雨の前後です。
巣穴を掘らなくなったと思ったら、ちょっと容器を揺すってみてください。
球状になった繭がでてきたら、今その繭の中で蛹になっています。
そうなったら容器に蓋が必要です。
繭ができて一か月くらいすると、羽化した成虫、ウスバカゲロウの誕生です。
羽化が終わるとウスバカゲロウは必ずすることがあります。

なんですか!?
蟻地獄は成長過程において尿はしますが糞はしません。
そのたまりにたまった宿便を出すんです。
あまり想像したくありませんが、見た目は硬そうで糞っぽくないそうです。

羽化して最初の仕事が糞をするって、ちょっと面白いですね(笑)
自由に動けるようになったので、もう保存していた栄養は不要ということかもしれません。
自由といっても漂うくらいにしか飛べないウスバカゲロウですが、後ろ向きにしか進めなかった蟻地獄から比べると雲泥の差です。
そして成虫になって1か月くらいでその一生を終えます。
ウスバカゲロウ幼虫期間の毒


ウスバカゲロウの毒について教えてください。
成虫のウスバカゲロウには毒はありません。
ただし、幼虫のときの蟻地獄には猛毒があるんです。
その毒の強さはフグ毒(テトロドトキシン)の130倍ともいわれていて、蟻地獄は巣にかかった虫にその毒を注入して、身動きが取れなくなったところで栄養分を吸い上げます。
えっ? それじゃあ飼えないって?
昆虫などの節足動物に反応する毒で、蟻地獄の体内にあるバクテリアが作り出すそうです。
本当に生物の神秘ってすごいですね。
では次に蟻地獄からどうやってウスバカゲロウになっていくのかをご紹介しましょう。
ウスバカゲロウとは
ウスバカゲロウは日本全国に生息し、だいたい6~9月に多く見られます。
最近は秋でも暑い日があるので、10月でも見られるようになりました。
パッと見た目トンボのようですね。
大きさはだいたい4センチくらいで触角の先端が曲がっているのが特徴。
羽は4枚、柔らかく半透明でユラユラ飛びます。

トンボとの違いは何ですか?
- 止まった時に羽をたたむ
- 触角が曲がっている
- 体の色に派手な色がない
これがウスバカゲロウの特徴です。
一番わかりやすいのが止まった状態を見ることですね。
これまではウスバカゲロウは何も食べないのでは?と考えられていたそうですが、実は小さな昆虫などを食べていることがわかりました。
あまり上手に飛ぶことができないので、ほかの昆虫や鳥などに捕まりやすいそうです。

せっかく羽があるのに上手に飛べないなんてかわいそうですね。
またデリケートな虫なので、飼育も難しく捕まえてもすぐに死んでしまうようです。
幼虫の時の蟻地獄とは、なんだか随分違って弱々しそうです。
蟻地獄はしばらく食べなくても生きていくことができて、仕掛けを作って餌をとり、さらに猛毒を注入して栄養を吸い上げるという、悪魔のような(笑)虫です。
それに比べると、フワフワ飛びながらひっそりと生きているのがウスバカゲロウ。

同じ虫とは思えない変わりようですね。
寿命も全然違うんですよ。
寿命は蟻地獄の1~3年に対し、ウスバカゲロウは3週間から1か月くらいです。
成虫になってからは、本当に儚い運命だといえるでしょう。
生きている短い期間にウスバカゲロウは結婚相手を見つけ、交尾をして蟻地獄が巣を作りやすい砂場に卵を産むそうです。
こうみると、本当に不思議な一生を送るんですね、ウスバカゲロウって。
ま、ウスバカゲロウから見ると「人間って変な生き物だな」って思うんでしょうけど(笑)

ところで何年か前にウスバカゲロウが大量発生したことがありましたよね?
このことでしょうか?
これはカゲロウですが、ウスバカゲロウではないようです。
ウスバカゲロウが大量発生することは、あまり考えられません。
この動画は愛知県で起きた2016年9月のことです。
まるで猛吹雪のようですね(笑)
と笑ってる場合じゃありません。
原因はわかっていませんが、車がスリップするなど事故も起こりました。
一体なんだったんでしょうね?
蟻地獄の駆除
害虫を退治してくれたり、そこにいるだけで何の悪さもしない蟻地獄ですが、やっぱり見た目がどうしても・・・。
っていう方もいるようですね。庭が穴だらけでみっともない、っていうケースもあるようです。
巣に水をかけると崩れはしますが、またその辺りに作ります。
常に水をかけておくと巣を作ることはできませんが、毎日となると面倒です。
そんなときは、巣を掘り返して似たような環境の砂場に移動させてください。
自分じゃ無理! というなら誰かに頼んでみましょう。
ウスバカゲロウの名前の由来

ここでプチ情報をひとつ。
ウスバカゲロウの名前ですが、中国のある言い伝えがあります。
その昔下級兵が戦術としてすり鉢状の穴を掘ったらどうか、と提案したところ「薄馬鹿野郎」とののしられてしまいました。
そのことを悲観し、その下級兵は自ら命を絶ってしまいます。
その後その下級兵の仲間が偶然蟻地獄を発見し、「薄馬鹿野郎」の生まれ変わりだと憐れみました。
ということです。

ではウスバカゲロウは漢字ではどう書くんですか?
「薄翅蜉蝣」です。
薄い羽で陽炎のようにユラユラ飛ぶその姿から、この名がついたともいわれています。
日本では地域によって「神様とんぼ」や「極楽とんぼ」なんて言われているそうです。
緑のウスバカゲロウっている?

緑色のウスバカゲロウがいるって聞いたんですが?
日本に緑色のウスバカゲロウはいません。
恐らくクサカゲロウのことだと思います。良く似ているので間違えたのかもしれませんね。
まとめ
- 幼虫期間には毒があるでOK
- 成虫には毒はなし
- ウスバカゲロウの幼虫は蟻地獄でOK
ウスバカゲロウそのものも、見たとしても「あ、トンボだ」くらいにしか思わないかもしれません。
また幼虫の蟻地獄に至っては、巣は見たことがあるけど幼虫そのものはずっと土の中にいるので見かけることも少ないと思います。
あまり接触する機会のないウスバカゲロウですが、こんなに壮絶な一生を送っているとは知りませんでした。
こんなに一生懸命生きているのに「蟻地獄」という名前、もうちょっと何とかならなかったのかと思います(笑)
ウスバカゲロウとクサカゲロウ
トンボや幼虫について
- トンボ・幼虫の種類を画像で解説
- カミキリ虫はエサに何食べる?
- ウスバカゲロウの幼虫は蟻地獄なの?
- カナブンの餌でおすすめは?
- クスサンの幼虫には毒がある?
- オオミズアオは絶滅危惧種だった?
- オオムラサキの幼虫を飼育したい?
- オオゴマダラの幼虫には毒がある?















