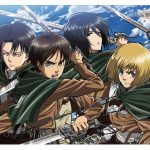- 花魁とは?花魁の小紫ってどんな人だったの?
- 有名な花魁5人と、その生涯とは?
「花魁」というと売れっ子遊女の華やかなイメージを持ちますよね?
けれどその実態は、華やかとはかけ離れた悲劇の象徴であることの方が多いのです。
かつて幕府公認遊郭の「吉原」にいた、絶世の美女・小紫。
小紫を初め、有名な花魁の名前と写真を以下に紹介していきます。
彼女たちの生い立ち・人生から、花魁が決して華やかなものではなく、貧困や男尊女卑社会の犠牲者であったことを感じ取っていただけたらと思います。
遊郭・花魁とは?
遊郭とは幕府公認の風俗営業地域。1617年、江戸幕府は風紀の乱れを正すために、遊女を江戸の一角に集め、幕府公認としての「江戸吉原遊郭」が誕生しました。
現代の日本橋人形町や、浅草田町などが、400年前には数千人の遊女が暮らす「吉原」だったのです。
1958年に「売春防止法」が実地され、日本全国の遊郭が廃止されるまで、吉原には多くの遊女がいました。

現代でも花魁の悲話をとりあげた小説や映画が人気で、その生活を垣間見ることができます。
遊郭がもっとも栄えたといわれる江戸時代。遊女の中には厳しい階級があり、上級の遊女たちは「花魁(おいらん)」と呼ばれていました。
花魁道中

花魁道中、という言葉も有名ですよね。
豪勢な着物で着飾った花魁が、高い下駄をはいてゆっくりと歩く姿を映画などで見たことのある方も多いでしょう。
あの花魁道中、実は普通に歩けば10分ほどの距離を、1時間ほどかけてゆっくりと歩いているんです。
客の待つ茶屋へと向かっているだけなのですが、そこに行くまでの道のりで、道行く人に自分の格と美しさを披露している、一種のパフォーマンスなのでした。
花魁道中があると通行人は立ち止まり、普段目にすることのできない高級遊女の姿を目に焼き付けるのです。
張り見世
花魁を扱った映画などでよく見かける張り見世。多くの遊女たちが格子の中で、通りをゆく客から見えるように座り、自分を広める場所です。

格上の花魁は張り見世にでることはほとんどなく、自分の部屋で待機して客が来るのを待っていました。
呼び出し

上述の通り、2階の自室で客が来るのをまつことのできるのは、売れっ子の証拠。
花魁たちは昼と夜、2回客引きをしていたのですが、昼の方が夜よりも安価でした。
安い昼ですら、三分(約6万円)の料金がかかる格上の花魁のことを「呼び出し昼三」(よびだしちゅうさん)と呼んでいたのです。
遊女の中でも最上級の地位で、数千人の中のほんの数人という割合だったようです。
有名な花魁
https://www.youtube.com/watch?v=ugY4HeI1OXs

そんな花魁の中で、現代にも名を残す有名な花魁を探してみました。
親に売られ戸籍もなく本名でも呼ばれない遊女は、歴史に名を残すことがほとんどありません。
そのような状況で、それでも語り継がれている有名な遊女たち。語りづがずに入られない、悲話が、そこにはありました。
小紫

美しすぎる花魁として有名な小紫。彼女の生涯もまた、悲劇と無縁ではいられませんでした。
江戸吉原の「稲本楼の小紫」は美しさはもちろん、和歌に長け聡明であることから、平安時代の和歌の名手であった「紫式部」の名をつけられました。
あるとき、小紫の花魁道中を見て、一目で恋に落ちた男性が現れます。平井権八という名の男性は、小紫の座敷に上がるために、辻斬りを繰り返してお金を稼ぎ始めるのです。
切った人の数、実に130人。想いが報われ、小紫の座敷に上がることができ、お互いに想い合うようになります。しかし辻斬りの罪から逃れることができず、平井権八は斬首刑に処せられてしまいました。
一方で身請けをし、無事に吉原を巣立つことができる身になった小紫。晴れて自由の身になったにもかかわらず、小紫は権八の墓の前で、自害してしまうのです。

来世での逢瀬を願って、愛人の墓の前で命を絶った小紫の名は、その美しさと悲劇のストーリーと共に語り継がれています。
八ツ橋

江戸時代の享保の時代にあった「吉原100人切り事件」に登場する美しい花魁、八ツ橋。
妖刀・ムラマサをもつ次郎左衛門が、吉原で花魁道中のときの八ツ橋を見かけ、恋に落ちるシーンは芝居などの見所シーン。
一目で男性のハートを射抜く花魁の美しさは、想像を絶するものだったのでしょう。
春駒


1927年に発刊された、「春駒日記」という、実在の花魁の手記を記録した書籍が残っています。
実在の遊女(花魁)が当時の廓での日々を書き綴った書として、花魁の暮らしぶりを知るためにとても参考になる書籍。
19歳のときに父親の残した借金のかたに、廓に売られた春駒。
著者である春駒は廓での「生き地獄のような」暮らしぶりを鮮明に文章に表現し、足抜け(自由廃業)した後に、「光明に芽ぐむ日」と「春駒日記」を出版。
手引きを助けてくれた西野哲太郎という男性と結婚したということです。
男性の性欲処理の道具のように使い捨てられてきた遊女もたくさんいたため、歴史に葬られることの多い吉原の実態。
ただの道具ではなく、意志や知性ある実在の女性が、不運によって身をおいていたのだと、等身大に感じることのできる春駒の本。
花魁の感情や境遇を世に知らせるという、大いなる貢献をしたと考えていいでしょう。
ちなみに春駒の本名は「森光子」ですが、女優の森光子さんではありませんのでお間違いのないよう。
揚巻


歌舞伎の「助六由縁江戸桜」で有名な揚巻という花魁がいました。
ここで紹介する花魁を初めとして、上級職であった花魁は名を引き継ぐことが多かったようです。
助六由縁江戸桜に登場する揚巻も、2代目・3代目が存在したようです。名を引き継ぐほどの花魁なので、いずれにせよ美女ぞろいであったことはうかがえますね。
高尾太夫


悲劇の遊女として名をはせた高尾太夫。
「太夫」とは、遊女の中でも最高級の位です。1659年の江戸吉原。
絶世の美女であった2代目高尾太夫(当時19歳)は和歌俳諧に長じ、書は抜群、諸芸に通じて全盛を誇ったといわれています。
そこへ、仙台の3代目伊達藩主・綱宗候が恋に落ちます。金銀財宝を積み上げて高尾太夫に思いを寄せる伊達綱宗候。

しかし高尾太夫には想う人が別にあり、ついにそのことを伊達綱宗候に伝え、「自分をあきらめてくれ」と懇願。
すると激怒した伊達綱宗候は、高尾太夫をはだかにして、船に逆さづりにし、切り捨てます。
高尾太夫のなきがらは岸に流れ着き、引き上げられた地に「神霊高尾大明神」として祀られたのが、高尾稲荷神社の起縁。
実物の頭蓋骨を祭神として安置してある、全国でも珍しい神社。高尾太夫の悲劇に同情する多くの人の参拝が途絶えない、有名な社です。
まとめ
歴史に名を残す有名な花魁を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。あまりの壮絶な彼女たちの人生は、「花魁」という華やかな言葉とはそぐいませんよね。
彼女たちのことを知れば知るほど、不自由で暴力的な世界の中、美しく咲くことだけを強要された悲劇が浮き彫りになります。
- 小紫
- 八ツ橋
- 春駒
- 揚巻
- 高尾太夫
上に紹介した5人の花魁以外にも、かつて悲劇の中に身を沈めた遊女の数は数千人~数万人。
自ら望んで遊女に身を落とした女性など、一人もいないことだけが確かなこと。
花魁のことを知るほど、なんて壮絶な人生なのだろうと涙する人も多いといいます。
だからこそ、本来ならば歴史の闇に葬られる花魁の人生が、芝居や劇などで繰り返し演じられ、語り継がれていくのでしょう。
忘れてはいけない歴史の闇は、国や時代を変えれば、現代にも繰り返しうる悲劇だということを、私たちに思い出させてくれます。