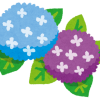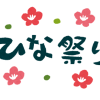- こどもの日って何をするの?
- こどもの日には何を作ればいい?
- 端午の節句とこどもの日は違うの?
5月5日は『こどもの日』ですよね。
この日は昔からの風習で、どんなことを行い、何を食べるか知っていますか?

こどもの日というと鯉のぼりを飾ったり、柏餅を食べたりしますよね。
今回は、こどもの日には、どのような意味があり、何を食べたりするのでしょうか。
『こどもの日』に何する?

こどもの日として知られていますが、端午の節句とはまた違うのでしょうか。
5月5日はこどもの日でもあり、端午の節句でもあるのですが、違いを説明できますか?
私はこの違いが何だろうと調べるまで、全く知りませんでした(笑)
【こどもの日のイメージ】
- 男の子のお祝いの日
- 兜や五月人形を飾る
- 鯉のぼりを飾る
- 柏餅を食べる
このようなイメージがあるのではないでしょうか。しかし、何故このようなことが行われるのか意味まで分かる方は少ないのではないでしょうか。
この2つの違いを調べてみると日本の伝統的なお祝い事にとても興味深く関心がもてました。
「端午の節句」の意味

端午の節句について説明します。
節句とは、季節の節目という意味があり、江戸幕府が祝日として定めたのが起源なんです。
節句は、端午の節句だけではなく、五節句として5つあります。
- 1月7日 尽日の節句(七草の節句)
- 3月3日 上巳の節句(桃の節句)
- 5月5日 端午の節句(菖蒲の節句)
- 7月7日 七夕の節句(七夕)
- 9月9日 重陽の節句(菊の節句)
※()内は和名
では「端午」の意味は何かというと、旧暦で”午”=5月
十二支は干支で年を表していることはご存知ですよね。それ以外にも月、日を表すのにも使われています。
- 子:11月
- 丑:12月
- 寅:1月
- 卯:2月
- 辰:3月
- 巳:4月
- 午:5月
- 未:6月
- 申:7月
- 酉:8月
- 戌:9月
- 亥:10月
5月は「午」。
最初(=端)の午の日を「端午」としていたのです。
本来は5月1日を端午とていしたのですが、後に「午」=「五」と考えられたり、他の節句に併せて5月5日を端午の節句にするようになったそうです。
「こどもの日」とは

では5月5日がこどもの日となったのは何故なのでしょうか。
- 端午を象徴する菖蒲が剣に似ている
- 菖蒲と尚武(武道を重んじる)が同じ読みであることから、端午の節句は男の子を祝う日
端午の節句は、このように昔は考えられていて男の子を祝う日とされていました。そこから「こどもの日」と言われるようになったのは、祝日ができたからなのです。
端午の節句=こどもの日と考える方も多いですが、もともとの5月5日の端午の節句があとから国民の祝日として「こどもの日」に制定されました。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに母に感謝する日」
1948年にこのような意味を持って定められたものなのです。母に感謝する日でもあったのですね!
現在はこどもの日として男の子に限らず、女の子も一緒になって祝ったりもしていますよね。
こどもの日に何をする?

こどもの日は各家庭、地域によってさまざまなことを行いますよね。
こどもの日に行われる風習について、どのような意味合いがあるのかご紹介していきます。
兜や鎧、五月人形を飾る

五月人形などなぜ飾るのでしょうか。
兜や鎧は身体を守るものです。人形を飾ることで「災いから身を守る」という意味合いがあります。
かつての武家社会では、神社に鎧や兜を奉納し安全を祈願していた。
これが風習の元です。
庶民が武家のマネをして、端午の節句に兜や鎧を飾るようになったことでこの風習が広がりました。
五月人形は、昔話の金太郎がモデルになっています。
金太郎のように健やかにこどもが育つようにという意味で、祈願して飾られるようになりました。
鯉のぼりを飾る理由

鯉のぼりは何故飾られるようになったのでしょうか。
鯉のぼりが飾られるようになった理由は、起源の中国にあります。
竜門という滝を多くの魚が登ろうとしたところ、鯉だけが上り切って竜になったそうです。
それから鯉の滝登りが「立身出世」の象徴に。
登竜門という言葉はここから来ているんだそうです!江戸時代にこいのぼりの風習が広まりました。
裕福なのに地位が低かった商人が、武士に対抗して中国の鯉の滝登りを取り入れて吹流しと一緒に鯉の絵を飾ったんだそうです。
江戸時代の商人が飾り始めたものだったのですね!
菖蒲湯につかる
武家社会では、「尚武(武装を重んじる)」と「菖蒲」をかけて端午の節句に菖蒲湯につかる風習が生まれました。
菖蒲は古代中国から薬草として使われていました。
季節の変わり目など体調を崩しやすい時期に菖蒲湯に入るという習慣もあったのです。
このような風習が、江戸時代に庶民の間でも広まったとされています。
柏餅・粽(ちまき)を食べる

端午の節句には何を食べたりしますか?
- 柏餅
- 粽(ちまき)
端午の節句にちまきを食べるという風習の起源は中国。ちまきには元々「供養」の意味があったのです。
5月5日は春秋戦国時代を代表する詩人・屈原の命日。政治争いに敗れて湖に身を投じたのです。
屈原を慕う人たちが、竹筒にもち米を入れて湖に投げ入れていました。ある供養の年に屈原が現れ、「湖に棲むという龍にちまきを横取りされないように、龍の嫌うチガヤ(芽)で包んで糸で結んで欲しい」と言い残したことを受けて、言われた通りに芽の葉にもち米を包んで5色の糸で縛って湖に投げました。
これがちまきの始まりなんですね。5色の糸は、鯉のぼりの吹流しと同じ色なんですよ!
ちまきともつながりがあったんですね。

柏餅を食べる風習は中国は関係していないようです。
これは日本独自の風習。
柏の葉に意味があって、新芽が出るまで落ちないことから”家系が途絶えない”、”子孫繁栄”という縁起物として扱われているんですね。
これも江戸時代から根付いた風習なんだそうです。
地域によって違うちまき

ちまきと言っても、地域によって違いがあるのはご存知ですか?
ちまきの形は「三角形」をイメージされる方が多いのでしょうか?
- 秋田、山形県などは縦長のちまき。
- 東北、日本海側は三角形のちまき。
新潟のちまきは、形だけが違うわけではありません。
「三角ちまき」というものは、もち米だけのちまきとも違ってきな粉をつけて食べるもの。
新潟名物にもなっているので、新潟へ旅行など足を運んだときには食べてみたいですよね。
中にあんこが入ったちまき、笹団子の形をしたちまきなどもあるので、色んな地域のちまきを探して食べてみるのも楽しいですね。
地域によって違うこどもの日の食べ物
https://www.youtube.com/watch?v=Jw7b_Y90l8c

柏餅、ちまきが代表的ですが、地域によっても風習が異なります。
- 北海道:べこ餅
- 山形:笹巻き
- 新潟:三角ちまき
- 関東:柏餅
- 関西:ちまき
- 徳島県:麦団子
- 宮崎県:鯨ようかん
- 鹿児島:あく巻き
- 沖縄:ちんぴん・ポーポー
それぞれ地域によっても食べるものは異なるようですね。
まとめ
5月5日のこどもの日、端午の節句は江戸時代から浸透したもの。
地域によって風習は少々異なることもありますが、鯉のぼり、兜、五月人形を飾ったり、柏餅、ちまきを食べることは今でも行われていますね。
こどもたちの無病息災、健やかに育つことを祈願していることは共通しています。
こういった昔からの風習。こどもたちに意味を聞かれたときにも答えられるようにしておきたいですよね!
今年のゴールデンウィーク中に旅行へ行かれたときには、その時のこどもの日の食べ物にも注目してみてはいかがでしょうか。
ひな祭りの関連記事
ハマグリをひな祭りに食べる由来|蛤のお吸い物を食べる理由はなぜ?
こどもの日・女の子へのおすすめプレゼントは?鯉のぼりでお祝いは?