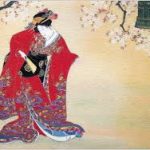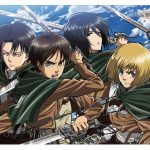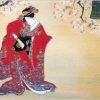- 伊達正宗ってどんな人物?伊達正宗の凄さとは?
- 伊達正宗の家紋は8つ?それぞれの由来とは?
- 家紋ってそもそも何?たくさん持つ意味はある?
1987年に放送されたNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』は、大河ドラマの中でもヒットしたとして知られてます。
この作品の主人公である伊達政宗ですが、家紋が8つあったと言われていますがその家紋とはどのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、伊達正宗の8つの家紋の由来や意味をそれぞれ徹底解説していきたいと思います。
伊達正宗ってどんな人物?伊達正宗の凄さとは?
https://youtu.be/7HrtccVUVPE
過去の偉人はたくさんいるものの、大河ドラマでも注目を集める伊達正宗はどんな人物だったのでしょうか。
永禄10年(1567年)8月3日、伊達正宗は出羽国米沢城で生まれました。
伊達家は、鎌倉時代から陸奥に勢力のある豪族だったと言われています。
幼少期は暗かった
しかし、伊達政宗は決して順風満帆な生い立ちではありませんでした。
4歳のときに感染症の一つである疱瘡で右目を失明したことから暗い少年時代を過ごしています。

だから黒い眼帯をしているのですね。
しかし、1584年に17代目当主に就任した途端、一気に活動的な青年に変貌したといわれています。
仙台城を築いた人
また、伊達政宗は1601年に仙台城を築城し、初代仙台藩主として君臨します。
藩主となった伊達政宗は、諸外国との交流や領地の開発・発展に力を入れました。
生まれた時代が不運
一方で、伊達政宗は天才的な頭脳とカリスマ性を持ち合わせていましたが、唯一残念だった点があります。

それは生まれた時代です。
なぜなら、伊達正宗が力を発揮し始めた時期には既に統一されつつある時代になっていたので、伊達政宗もその能力をすべて発揮する事は出来なかったと言われています。
もう少し生まれるのが遅かったら、もっと偉大な人物となっていたかもしれませんね。
伊達正宗の死因
そんな伊達政宗は、寛永13年(1636)5月24日に死亡しました。
腹膜炎、あるいは食道がんが原因だったといわれています。

つまり、死因は病死です。
戦で命を落としたわけではないのは、とても意外ではないでしょうか。
元々、春先から体調を崩していたのですがすでに、病を察して仙台から江戸に向かっています。
その際に日光に寄ったとされていますが、自分の命が永くはない事を察し、徳川家康へ挨拶に立ち寄ったのではないかとされています。
伊達正宗はオシャレだった
そんな伊達正宗ですが、オシャレのセンスにおいては群を抜いて目立っていたと言われていますよね。
オシャレな人を指す、”伊達者”という言葉も伊達正宗から生まれた言葉です。
白一色で登場
伊達政宗のオシャレというのは、どちらかと言えばインパクトの強い服装で人目を引いていたという記録が残っています。
特に、豊臣秀吉の小田原(北条)攻めに白装束で参陣し、豊臣秀吉だけでなく敵陣の注目も集め、伊達正宗の名は一気に有名になりました。
しかも、豊臣秀吉とこの時が初対面だったとされているからびっくりです。
この初対面の日に、伊達正宗は事もあろうか約束の時間に遅れてしまいます。
そこで、詫びの意味を込め命を捧げるつもりで、全身白装束に身を包んでくれるみ豊臣秀吉の前に現れたのです。
しかし、豊臣秀吉秀吉もパフォーマンスが大好きで有名な人物である事から、伊達政宗のこの行動が気に入られるきっかけとなったのです。
豪華で華麗な軍服
また、朝鮮出兵の出陣式においても伊達軍勢が着用していた戦装束は、かなり豪華できらびやかだったことも、伊達正宗がオシャレだと呼ばれるきっかけとなった出来事の一つです。
- 紫紺地に金の日の丸が描かれたのぼり
- 金のとんがり笠
- 朱鞘の太刀
- 銀箔の柄頭の脇差
このように、当時ではあり得ない派手さがインパクトとなり、伊達政宗のオシャレな一面に注目が集まるのです。
しかし、この装束における目的は人々を驚かせることではなく、派手好きの秀吉が気に入りそうな派手な戦装束を整えることで、秀吉から自身の軍勢を選んでもらおうと思いそうしたという説が濃厚です。

つまり、伊達政宗は賢かったのですね。
本当は派手好きでない?
実は、伊達政宗は天下統一を遂げた豊臣秀吉には家紋を譲り受ける事はあっても、最後まで抵抗していたといわれています。
伊達政宗が、豊臣秀吉に服従したのは1590年(天正18年)で、ギリギリまで反発していたのです。
つまり、他の大名に比べ危うい立場だったといわれています。
だからこそ、関白であった豊臣秀次が謀反の疑いから豊臣秀吉に切腹を迫られた際、豊臣秀次と親交のあったに伊達家にも疑いがかけられましたが、伊達正宗はこれを上手く切り抜けています。
それは当時、派手好きで知られていた豊臣秀吉に自らを合わせ、派手でオシャレなイメージを付け豊臣秀吉に気に入られる事が、ある意味生き残る戦略の一つだったのではないかという事なのです。
家紋もオシャレなものが多い
そんなオシャレな伊達正宗だからこそ、これから紹介する8つの家紋においても、どれもオシャレなものが多いです。
特に、伊達政宗の家紋は複雑なものから現代でもオシャレに見えるものなど、様々な家紋を譲り受けたり作ったりして、伊達家の存在を示したのです。
伊達正宗の家紋は8つ?それぞれの由来とは?
https://youtu.be/uIeGPeuQ_mk
そんな伊達正宗には、家紋が8つあったと言われています。
そこで、それぞれの意味や由来を紹介したいと思います。
伊達政宗の家紋1:竹と雀

伊達政宗の家紋と言えば、特に有名なのが真ん中に雀を描いた『竹と雀』の家紋ですよね。
この竹に雀の家紋は、別名”仙台笹”や”伊達笹”とも呼ばれています。
家紋の由来
この家紋の由来は、伊達政宗の大叔父である伊達実元(だてさねもと)が、越後の上杉定実(うえすぎさださね)の養子に入る際、婿に対する引き出物としてこの家紋を譲り受けたと言われています。
その後、養子に入る話はなくなりましたが家紋だけはそのまま使われているのです。
上杉家の家紋が元となる
また、この『竹に雀』ですがやはり上杉家の家紋を元に、オリジナルの「伊達笹」と呼ばれる家紋を作り上げました。
だからこそ、上杉家と伊達家の雀の家紋はとてもよく似ていますよね。
伊達家の家紋はたくさんありますが、特にこの家紋は特別であるのです。
伊達政宗の家紋2:三つ引き両紋
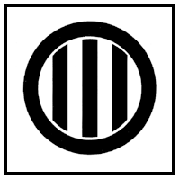
伊達政宗の家紋の中で、最も長く使用されているのがこの『三つ引き両紋』だと言われています。
三つ引き両紋は、波線のものや横引きなどいくつかのかたちがありますが、縦引きのものが伊達政宗の家紋です。
家紋の由来
三つ引き両紋の由来は、『寛政重修諸家譜』によると伊達家初代の伊達朝宗(だてともむね)が、文治5年(1189年)奥州平泉藤原氏征伐に参加した際、藤原討伐の功績により源頼朝から下賜されたと言われる家紋です。
しかし、その時は二引両だった幕紋を伊達家ではその後、竪三引両に改めさらに輪郭を入れたものを定紋にしたといわれているのです。
引両紋は強運の証
また、この引両紋は家紋の中でも高貴で強運の紋とされています。
特に、二本の場合は”二匹の竜が天に昇る”ことを意味しているとされ、縁起が良い強運の紋だったのです。
伊達正宗の家紋である、三つ引き両紋も同じような意味合いが込められたとされています。
仙台市のマークも家紋から?
また、伊達正宗と言えば仙台市が有名ですが、仙台市のマークも伊達正宗の三つ引き両紋にとても似ていると言われています。
一方、仙台市の『仙』の字からという説もあるのでどちらかは謎です。
伊達正宗の家紋3:九曜紋(くようもん)

大きな一つの丸を中心に、小さな丸が円を描くように8つ並んでいる家紋が九曜紋です。
また、この家紋は星をイメージしたものだと言われています。
今でこそ星は☆で表しますが、日本では星はすべて”〇”で表現していたとされています。
だからこそ、伊達政宗の羽織などにもこの〇がたくさん使われていますが、意味合いとしては西洋の星をイメージしているようです。
家紋の由来
伊達正宗は、オシャレな将軍としても知られていました。
だからこそ、家紋も8つもあるのでしょうね。
そんな、オシャレな伊達正宗は九曜紋を家紋とする細川忠興に、無理を言ってもらい受けたと言われているのです。
特に、羽織りにも星をいれるほどでしたので、紋であるこの九曜紋が欲しかったのかもしれませんね。
片倉小十郎に渡った九曜紋
一方、そこまでお願いして手に入れた九曜紋ですが、伊達正宗はなんとその家紋を、片倉小十郎に渡したという話も有名です。
家紋においては、譲ったり譲ってもらったりするのはよくある事なので不思議はないのですが、せっかく譲ってもらったのにという感じですよね。
伊達正宗の家紋4:雪薄紋(ゆきうすもん)

波打つような縁取りに草が生え、そこに雪が降っている様子可愛い家紋が『雪薄紋』です。
仙台と言えば、雪国ですので東北らしい家紋だと言えます。
家紋の由来
この雪薄紋は、伊達正宗の代で用いた家紋だと言われています。

いわゆるオリジナルです。
基本的には、伊達家の姫や姫に仕える位の高い女中の為の家紋として使用されていたとされています。
一方、伊達政宗の初陣では、この雪薄紋を付けた旗を使用したと言われています。
伊達正宗の家紋5:五七桐(ごしちのきり)

『五七桐』は、日本政府が使っていることでも有名ですよね。
だからこそ、政府の演台には必ず五七桐が飾られています。
政府、内閣総理大臣、内閣府紋章として豊臣秀吉と同じ五七桐を使っています。
家紋の由来
この五七桐は、元々は豊臣秀吉が家紋として使用したことで有名でした。
豊臣秀吉は、この五七桐を多くの家臣に下賜したといわれています。

その一人に当たるの伊達正宗なのです。
グレードの高い家紋
また、この五七桐は家紋としてのグレードは最高峰に近いものでもあります。

そもそも、桐紋は天皇家の紋章です。
皇室の紋章と言えば、今でも使用されている菊花紋が有名ですが、替え紋として桐紋を使用してきたと言われているほどです。
伊達正宗の時代も、やはり秀吉効果もあり高貴な家紋の一つだったことから、伊達正宗も欲しい家紋の一つだったのかもしれませんね。
伊達正宗の家紋6:十六葉菊(じゅうろくようぎく)
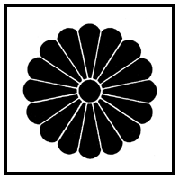
円の中に菊の花が咲いている、シンプルな家紋が『十六葉菊』です。
菊の花びらが10枚あるのなら”十菊”、12枚なら”十二菊”と呼びますが、伊達正宗の家紋は花びらが16枚なので”十六菊”です。
家紋の由来
この十六葉菊ですが五七桐と同様、もともと豊臣秀吉が天皇から下賜された紋で桐紋と一緒に下賜されたものの一つです。
その後、豊臣秀吉から伊達正宗が譲ってもらったかたちとなています。
仙台市青葉区霊屋下に、2代藩主伊達忠宗(だてただむね)によって建てられた伊達政宗公の霊屋である『瑞宝殿(すいほうでん)』にも、この十六葉菊の家紋が至る所に散りばめられています。
菊紋はステータスがあった
戦国時代は、戦果を挙げた武将への褒賞として菊紋が下賜されるということが行われていました。
当時、後醍醐天皇から菊紋を下賜さたのは豊臣秀吉以外にも、足利尊氏など今でもその名が知れている人物ばかりです。
この当時、天皇は神様と同等ともいえる存在でしたので、武将たちにとって菊紋を持っていることはある意味ステータスだと言えるのではないでしょうか。
伊達正宗の家紋7:牡丹紋(ぼたんもん)

中国では牡丹は、”百花の王”と言われており唐代の中央官僚達が、この牡丹の美しさを競ったといわれています。
もちろん、そんな富貴な花が日本に伝わり家紋のデザインとなりました。
家紋の由来
この『牡丹紋』は、もともとは近衛家が使用していた家紋ですが、20代の綱村(つなむら)公が近衛家からいただいた紋だと言われています。

それを伊達政宗が譲り受けたのです。
牡丹の花がとても美しく、伊達政宗の家紋の中でも凝ったデザインの紋です。
伊達正宗の家紋8:蟹牡丹
 牡丹の花でありながら、もこか蟹を思わせるデザインの家紋です。
牡丹の花でありながら、もこか蟹を思わせるデザインの家紋です。

とてもユニークな家紋です。
家紋の由来
この家紋は、伊達家の20代目藩主にあたる伊達綱村(だて つなむら)が、近衛家から下賜された牡丹紋を、その後21代目となった吉村公がこのような形にデザインをしたといわれています。
つまり、伊達家オリジナルの家紋とも言えるのです。
だからこそ、江戸時代にはこの家紋が表紋とされていたといわれています。
このように伊達政宗の家紋は8つあり、それぞれ伊達政宗の家紋となるまでには、様々な由来やストーリーがあるのです。
家紋ってそもそも何?たくさん持つ意味はある?
では、伊達正宗の家紋の意味が分かったところで、そもそも『家紋』がなぜあるのか、またなぜ一つではないのか気になるところです。
家紋とは
まず、基本的な『家紋』とはそもそも何かというと、格家の地位やその歴史を示すものでした。
要するに、祖先と家に伝わる紋章(ロゴマーク)が家紋となります。
先祖代々、今へと繋がる血の流れを簡単なマークに置き換えて表現したものといえます。
しかし、戦国時代においては家紋をみると人脈なども分かり自分をアピールするシンボルだったといわれています。
家紋の使い方
では、そんな家紋はどのように使われていたのでしょうか。
- 建築物
- 着衣
- 旗印
- 提灯
このように、様々な場面で家紋は重要な役割があったのです。
また、江戸時代以前の武家社会においては、大名や旗本の素性や系列を見分けるのに、家紋は一目瞭然で利用されていたと言われています。
つまり、武士にとって家紋入りの着物や提灯を下げて歩くことは、自らの威厳を誇示するためのものでした。
家紋を複数持つ意味
伊達正宗も8つの家紋をもっていましたが、家紋と言えば一家に一個あるようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
しかし、家紋というのは一個ではなく複数持っていても良いのです。
なぜなら、戦国時代において例えば豊臣家の家紋を譲り受ける事は、譲られる方は強く存在感のある家の家紋を欲しがります。
そうする事で、その家と関わりがある事を家紋で示す事ができそれが誇りになります。
一方、家紋を分ける側も自分の家の家紋を分ければ分け得る程、知名度が広がります。
だからこそ、親交の深い者に家紋を譲ったり譲ってもらう事で、伊達正宗のように8つの家紋を使いこなす武士は多かったと言われているのです。
このように、家紋は調べればとても面白い由来や歴史が隠れている事がとても良くわかりますね。
さいごに
いかがでしたか。今回は、伊達政宗の家紋8選の由来や意味をそれぞれご紹介してみました。
家紋は、今でもオシャレに見えるものから意味合いを込めたものまでさまざまあり、とても興味深いものですね。
また、家紋はいわばステータスにもなる時代だったことから、伊達政宗はたくさんの家紋を持っていたことがよく分かりました。

ぜひ、参考にしてみてください。
家紋や歴史についての記事