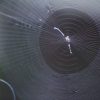- ハロウィンの意味や由来は?
- ハロウィンのについて子供に聞かれたら?
9月に入ると、街中がハロウィンムードとなり、所せましとハロウィン商品が陳列され始めます。
オレンジと黒が街中に溢れ、可愛いものもたくさんあるため、色んな商品に目移りしてしまいますよね。
そんな中、子供たちと共にお買い物に出掛けると、「どうしてハロウィンをするの?」なんて、聞かれて困ったことはありませんか?
実際、大人でもその理由を知らない。。。なんていう方も実は多いようで、素朴な子供の問いかけにちゃんと答えられなかったという方も多いようです。
そこで、子供からの質問に困らないためにも、ハロウィンの由来や子供にどのようにハロウィンを説明すれば良いか、その方法を簡単に解説したいと思います。
ハロウィンの意味や由来は?
では、まずは、ハロウィンの意味や由来について見ていくことにしましょう。
ハロウィンの意味

ハロウィンは、「諸聖人の祝日の前夜」という意味を持っています。
英語で「ALL Hallow’s Even」が略され、「Halloween」となったそうです。
諸聖人は、すべての聖人を崇敬する祝日となり、「万聖節」と言われていました。
ハロウィンの由来は?
ハロウィンは、そもそも古代ケルト人が「秋の収穫祭」というイベントで行っていました。
それは、古代ケルト人にとって1年の終わりが10月31日と定められており、日本で言う12月31日の大晦日と同じ位置付けとして、毎年一大イベントとして開催されていました。
ハロウィンで使う道具とその意味とは?
ハロウィンは毎年10月31日に開催されますが、その時、かぼちゃのランタンやお菓子をもらったり、また、その時に仮装をしたりと、とにかくハロウィンはとてもユニークです。
これらの道具を使用する意味とは一体何なのでしょうか?
かぼちゃ
ハロウィンというと、かぼちゃのランタンがすぐに思い浮かびますが、かぼちゃには、そもそも「お守り」という意味があります。

そして、ランタンは、「悪霊魔物から身を守る」という意味を持っていす。
ハロウィン当日は、かぼちゃの中身をくりぬいてランタンとし、中に灯をともし、悪いお化けを追い払う飾りの役目として使用します。
くりぬいたかぼちゃの中身はパンプキンスープやサラダにしてその日の料理に食べるんだそうです。
ジャックランタンの由来とは
ランタンというと、「ジャックランタン」という名前を聞いたことがあると思います。

このジャックランタンは、アイルランド人の「ジャック」という男性が由来となっているのです。
ジャックは生前悪いことばかりをしていたので、死んだ後は地獄へ連れて行かれることになりました。
しかし、子供の頃にハロウィンの日に駆け引きを行い、魂を取らない約束をしたために、ジャックは地獄へ招かれることもなく、天国へ行けることもないまま真っ暗な道をひたすら歩くのみです。
前が見えないジャックは、道に落ちていたかぼちゃの中にもらった灯をともし、かぼちゃの提灯を作って歩いたのだと言います。
このかぼちゃの提灯が「ジャックランタン」です。
今もジャックはこのかぼちゃのジャックランタンを持って、天国でもなく地獄でもない場所を彷徨っているのだそうですよ。
かぼちゃのランタン、最初はカブだった?
ハロウィンといえば、かぼちゃのランタンというほど定着していますが、このかぼちゃのランタンについても面白い話があるので、ご紹介しておきたいと思います。

実はこのかぼちゃのランタン、始まりはカブだったんです。
でも、アメリカはカブに馴染みがないために、最も加工しやすいかぼちゃを使用したことがきっかけでジャックランタンにかぼちゃが使用されるようになりました。
これをきっかけとし、アメリカ式のハロウィンが世界各国に広まり定着したため、ハロウィン=かぼちゃという考えになったそうです。
とはいえ、そもそもハロウィン発祥の地であるアイルランドでは、現在もランタンにはカブが使用されているそうです。
お菓子
ハロウィンの日には、子供たちはお化けや魔女に変身し、しっかりと仮装をしたら、その姿で近所の家を訪ねて回ります。

その時に「Trick or Treat?」(「お菓子をくれないとイタズラするぞ!」)という意味で言葉を発します。
そして、ハロウィンの日は子供たちはたくさんお菓子を手に入れることができるのです。
このお菓子については、本来、お菓子はお化けのご馳走です。
そのため、ハロウィンの日にやって来るお化けや魔女は、勝手に人の家に入り込み、みんが食べるはずのご飯を全部食べてしまうのです。
そうすると、あなたがお腹が空いてしまいます。
このようなことが起こらないよう、お化けが訪ねてきたら、お化け用のご馳走(お菓子)を渡して家の中には入り込まれず帰ってもらおうというものです。
そのためにお菓子を渡すようになったのだそうですよ。
ハロウィンで仮装した子供たちがお菓子をもらって歩くことには深い説が色々とあることが分かりますね。
仮装
ハロウィンだからと言って、なぜわざわざお化けや魔女に扮した姿に仮装を行わなければならないのでしょうか?
これは、子供たちは自分も同じお化けに化けることで、仲間だと思いこませ、魂を取られることを防ぎ、自身の身を守るためにこのような仮装を行っているのです。
最近では日本でも、ハロウィンこそリアルな仮装を楽しむ時代となり、ハロウィン当日は街中がコスプレイヤーで溢れ返っているほどです。
ですが、ハロウィンの仮装の本来の意味は、お化けに魂を取られてお化けの世界に連れて行かれないように同じ仲間と思わせるため。
ハロウィンの日は、この世とあの世が一緒になり、死んだ人が返ってくる日です。

その時にお化けも一緒に帰ってきてしまい、その後連れて行かれてしまうと言い伝えられています。
何も悪いこともしていないのに、死んでしまうのは嫌だと誰もが思いますよね。
だからこそ、お化けや魔女に顔すして、仲間のふりをすることであの世に連れて行かれることを防ぐことができるのです。
このようなことから、ハロウィンの日には仮装は必須だと言えますね。
ハロウィンについて子供に聞かれたら?
子供に「ハロウィンって何??」と聞かれた場合、大人用語を並べたとしても子供は一体何を言っているのか全く理解してくれません。
例えば、教科書通りによくある「古代ケルト人が秋の収穫祭を願って開催していたんだよ」、なんてそんな説明をしたところで、分かるはずありませんよね。
当然、子供たちからすると「ケルト人?何?それ?」という返事が返ってくるだけで、一体何のことなのか余計に混乱を招くだけだと思います。

では、子供に分かりやすく「ハロウィン」を伝えるにはどうすれば良いでしょうか?
ハロウィンとはどんなものなのか?
分かりやすい説明のしかた
このハロウィンは日本の話ではないということ、遠い外国のお話だということから上手に伝えましょう。
そして、ハロウィンを行う日が10月31日であり、その日に死んだ人がこの世界に戻ってくる日だということ。

つまり、「ハロウィンの日だけ、死んだ人が1年に1回だけ家に帰って来られる日なんだよ。」と伝えてみてください。
でも、死んだ人がすべて良い人ばかりではなく、中には悪い人もいて、そういう人は「お化け」となって一緒に帰ってきてしまうのよ。
そのお化けは生きている私たちをあの世へ連れて行こうとするそうで、特に子供が大好きなお化けは、あなたたちを狙って来るんだよ。
もしあの世へ行ってしまったらどうなるのかな?
もちろん、死んでしまうのよ。
でも、死んだら何もできなくなるからみんな死にたくないよね。
そこで、生きている私たちは、ハロウィンの日にあの世へ連れて行かれないようにお化けと同じ姿になれば、私たちを仲間だと思って連れて行かれない!そう思いついたのよ。
そこからみんなハロウィンの日には魔女やお化け、悪魔の仮装をするようになったの。
ハロウィンの日にお化けの仮装をしている人は、みんなお化けが怖いから、自分もその真似をしていれば怖くない、本物のお化けだって逃げてしまうと、だからお化けのふりをしているんだよ。
このように柔らかく噛み砕いてお話をすると、小さな子供さんでも理解できるのではないでしょうか。

また、言葉だけで伝わらない場合は、絵を書いたり絵本を読みながら伝えるのも良いかもしれませんね。
小さなお子さんには絵本がおすすめ
特に、まだ3歳くらいの小さなお子様であれば、絵本が最も効果的だと思います。
ハロウィンの絵本はたくさんありますが、小学校低学年に向けた絵本は残念ながらそれほど多くはありません。

そんな少ない絵本の中でも、低学年に向けた「ハロウィーンってなぁに? (主婦の友はじめてブック) [ クリステル・デムワノー ]」はおすすめです。
主人公の魔法使いの女の子が、おばあちゃんからハロウィンについて教えてもらうお話です。
この絵本は漢字も使用されているので、読み聞かせにも効果的です。
ぜひ一度、子供向けに読んであげて欲しい絵本のひとつです。
「トリックオアトリート」と言われた場合の返事は?
ハロウィン当日は、お化けや魔女に仮装した子供たちが近所の家を回る際、必ず「トリックオアトリート!」と言います。
このトリックオアトリートは、英語表記すると「Trick or treat」となります。
- Trick:いたずら、悪だくみ
- Treat:ごちそう、とてもいいもの
と、このような意味があります。
そして、この2つをつなげて日本語訳すると、『お菓子をくれなきゃいたずらするぞ!』という意味になります。

では、この『トリックオアトリート!』と言われた場合、私たちは一体何と返せば良いのでしょうか?
- 「Happy Halloween! (ハッピーハロウィン)」(良いハロウィンを!)
お菓子をあげるから、良いハロウィンを過ごしてね。という意味合いがある - 「Treat! (トリート)!』
お菓子をあげるよ!という意味がある
このような返事をしてあげましょう。
日本でハロウィンを行うので、なかなか英語に馴染みのない日本人が英語で言葉を返すのは何だかちょっと恥ずかしい。。。と思う方もいると思います。

そんな時は、日本語で『お菓子あげるからいたずらしないでね』と言えれば良いですよ。
実際、このハロウィンの風習は1911年頃から続けられているそうです。
ハロウィンで『トリックオアトリート!』が定着したきっかけとなったものがディズニー映画なんだそう。
1952年のディズニーの短編映画『ドナルドの魔法使い』に実にこのセリフが出ているのです。
このディズニー映画がきっかけとなり、『トリックオアトリート!』が世界中に広まったと言われています。
さすがアメリカですね。
まさか!?「トリックオアトリート!」を断ると?
子供が楽しみにお菓子をもらって回る中で、『トリックオアトリート!』と言われてお菓子をあげずに断る大人はいないでしょう。
しかし、大人も、「もしも子供にお菓子をあげなかった場合、一体どんなことが起こるの?」など、遊び心で断ってしまった場合、どんなことが起こるかと言うと、結構いたずら度合いがハードなのだそうですよ。
- 玄関や車に生卵を投げつけられる
- スプレーを家の壁にかけられることも?
- トイレットペーパーで玄関先の木をぐるぐる巻きにする
まさかこんなことが?と思うかもしれませんが、実際に起こったことがあるそうですよ。
このようなことから、子供の『トリックオアトリート!』を断ると、後にとても面倒なことになる予感がします。
とは言え、さすが本場アメリカ的な考えですが、実際日本でこのような事例はあまり聞くことはありません。
しかし、実際にあった場合は子供のいたずらだから。。。などでは済まされない気もしますね。
まとめ
ハロウィンの歴史を子供向けに分かりやすく簡単に解説する方法についてご紹介しましたがいかがでしたか?
ハロウィンは日本ではまだ歴史も浅く、仮装する楽しみで開催されているというイメージが強いと言えます。
しかし、本来の目的は、日本のお盆などと同じ内容で故人の霊をお迎えするという主旨で行うのが本来の意味となります。
それにしても、あの世に連れて行かれないためにも、自分の身を守る意味でお化けや魔女に化けるという発想はとても楽しいものですね。
ハロウィンの意味を改めて知ったという方も多いのではないでしょうか?
小さなお子様をお持ちの方は、これからハロウィンのことをたくさん質問されるでしょう。
その時には、この記事のマメ知識をしっかりと覚えておき、子供に説明してあげられるようにしておいてくださいね。
ハロウィンについての記事はコチラ