- 俳句で使われる「ホトトギス」にはどんな意味がある?
- 俳句で時鳥を使うコツはある?
俳句を作る際、それぞれの季節に合った季語を使用して作ることになります。
季語を含めることで、それぞれの季節感や風情が感じられ、より詠む側の心もこもる俳句が出来上がります。
俳句で使われる季語の「ホトトギス」にはどんな意味があるかご存知ですか?
ここでは、ホトトギスの季語の意味や時期、また、時鳥を俳句で使用するコツや実例をご紹介します。
俳句はどのようにして作るの?季語の意味は?
俳句は定型詩があり「五・七・五」のリズムでもって詠まれます。
ひらがなで書いて十七文字として仕上げます。
この俳句については、江戸時代から始まり、江戸時代では詠む人を俳諧師と言い、明治時代以降に作られた俳句は詠む人を俳人と言うようになりました。
俳句は十七韻で詠むことから、その中にできるだけ伝えたい情報、情景を詠み込む必要があります。

だからこそ、季語を使用します。
古来、日本の伝統からくる表現方法だとされています。
ホトトギスの季語の意味や時期は?
ホトトギスを季語として使用する季節は5月頃です。
ホトトギスはもともと渡鳥であり、この季節がやってくると日本に向かって飛んできては、ウグイスの巣に卵を産み、新たな命の誕生を待ちます。
夏の訪れを知らせる鳥として、俳句の中で用いられます。
■ホトトギスとは
ホトトギスとは、カッコウ目カッコウ科の鳥です。
体長約30cmで日本においては夏の鳥として渡来してきます。
九州よりも北、北海道では南部で繁殖し生息しています。
ホトトギスと名前がついたのは、「ホトホト」という鳴き声に聞こえること、そして「ス」はカラスの「ス」を、またウグイスの「ス」をもって付けられたと言われています。
漢字では「時鳥」と表記されます。
ホトトギスの見た目は、他の鳥であるカッコウにも良く似ています。
ホトトギスはウグイスの巣に卵を産み、孵化したヒナを育ててもらうといった習性を持ちます。
その為、ホトトギスはウグイスが生息している場所に飛んでくるのです。
林や藪、草原などでその姿を確認することができます。
ホトトギスは昼夜に関係なく鳴く鳥として知られています。
ホトトギスは、日本の夏の到来を告げる最も代表的な渡り鳥として知られており、春のウグイスと並び、季節の鳥として周知されています。
また、このホトトギスについては、万葉集にも記されている鳥です。
多くは5月頃に渡来し、ウグイスの巣に卵を産み、秋になると南へと去っていく渡り鳥として知られています。
■ホトトギスの特徴
ホトトギスはカッコウ目カッコウ科に分類される鳥類である為、カッコウの仲間だということが分かります。
その為、見た目もホトトギスとカッコウはよく似ています。
とてもよく似ている為、それぞれの特徴を知らなければ見分けがつかないということもあります。
ホトトギスとカッコウの見分け方
胸に横線が入っているのがカッコウで、それよりも横線が少ないのがホトトギスです。
また、尻尾に斑点があるのはカッコウ、ほとんど見られないのがホトトギスです。
身体の大きさはカッコウよりもホトトギスの方が少し小さめです。
ホトトギスは冬はアフリカやインド、中国南部で暮らしていますが、5月頃になると日本や朝鮮半島に向けて渡来してくる渡鳥です。
■ホトトギスは俳句の季語になる
ホトトギスが主人公となって作られる俳句はとてもたくさんあります。
数にして、万葉集には153例、古今和歌集には42例、そして新古今和歌集で46例です。
実に、「枕草子」でも、ホトトギスの声を聴きたくて、徹夜して待つ人が詠われており、他にも、仙谷さん大武将の織田信長や豊臣秀吉、徳川家康とそれぞれがホトトギスを俳句に読み、詠っています。
また、ホトトギスは漢字で「時鳥」と表記されることがほとんどですが、他にも、「杜宇」「蜀魂」「不如帰」などの異名を持っています。

これは中国から伝来したものだと言われています。
また、実は、ホトトギスは何も渡鳥としての存在だけではありません。
実際にはホトトギスと呼ばれる花が存在します。
その花にホトトギスという名前が付いたのは、ホトトギスのお腹の模様が花の模様であることが由来となっているそうです。
時鳥を俳句で使うコツ&実例まとめ
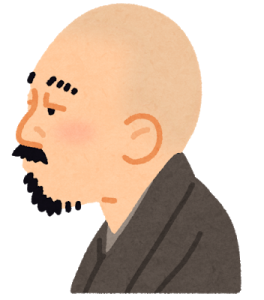
では、ホトトギスを俳句で使うコツや実例を紹介していきましょう。
■三大武将が詠った「ホトトギス」
日本の三大武将である織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった武士がそれぞれに、
- 織田信長・・・「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」
- 豊臣秀吉・・・「鳴かぬなら鳴かせて見せようホトトギス」
- 徳川家康・・・「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」
と詠った俳句は何とも有名で歴史上において誰もが耳にしたことがあると思います。

さらに、もう一人、歴史上の人物が存在します。
「鳴かぬなら逃がしてしまえホトトギス」
これは、織田信長の家臣である天下五剣の松浦静山が詠った俳句です。
ちなみに、「鳴け聞こう わが領分のホトトギス」というのもあり、歴史上の人物がホトトギスを詠んだ俳句は結構面白くもあり、歴史を感じますね。
こうして見ると、歴史上の人物が「ホトトギス」を主人公とした俳句を詠んだことが、今の時代になっても、私たちが学校で習う日本史で、歴史上のこを知ることができるのもとても楽しいですね。
■時鳥を俳句で使う実例
実際にホトトギスを俳句で使用した実例をご紹介します。
- 京にても 京なつかしや ほととぎす
- ほととぎす 声横たふや 水の上
- 木がくれで 茶摘ときけや ほとゝぎす
- ・うす墨を 流した空や 時鳥
- 五月雨の 雲やちぎれて ほとゝきす
- お茶壷の 上を鳴き行く 時鳥
- 時鳥 なくや夜明の 善光寺
- 郭公 何の夢見る 陰陽師
- 郭公 はてなき海へ 鳴て行く
このように、同じ「ホトトギス」でも、漢字表記をした「時鳥」以外にも、「不如帰」「子規」「郭公」と表現することもあり、これらをすべて「ホトトギス」と詠みます。

郭公は、実は、カッコウのことです。
実物を比較しても、カッコウとホトトギスはとてもよく似ていますが、全く別の鳥です。
しかし、日本古来より、和歌や俳句を詠む際は、カッコウのこともすべて「郭公=ホトトギス」として詠まれていたそうです。
そして、ホトトギスと聞けば、正岡子規です。
正岡子規は、「ホトトギス派文学」の創始者であり、まさにホトトギスを意味する「子規」を名乗る俳人として知られています。
また、ホトトギスは、激しく鳴き続ける鳥であるという伝説があり、それを自身が罹患した結核になぞらえて詠まれた俳句であると言われています。
日本に残る俳句でも、やはり「ホトトギス」を詠んだ俳句は非常に多いです。
また、鳥と言う鳥が季語に出て来るものすべてホトトギスの句になってしまうこともあります。
■俳句で「時鳥」はどのように使うの?
- あともなき三千坊や時鳥
- いつも初音ましてはつ音の時鳥
- うす墨を流した空や時鳥
- うづき来てねぶとに鳴けや時鳥
- おもひもの人にくれし夜時鳥
- くらがりに活けしあやめや時鳥
- 時鳥くらがり坂を君帰る
- 時鳥日は照り風も吹きながら
このように「時鳥」を用いて俳句を作ってみましょう。
まとめ
いかがでしたか?
ホトトギスの季語の意味やその時期、また、時鳥を俳句で使うコツや実例をご紹介しました。
ホトトギスは日本の歴史において、古く昔から俳句の中に詠まれていた季語だったんですね。
それも、織田信長や徳川家康、豊臣秀吉といった大物歴史上の人物が「時鳥」を使用していたのですから、改めて日本の戦国武将は凄い方であったことが分かりますね。
ホトトギスの季語の意味や時期が分かったところで、ぜひ、「ホトトギス」を用いて俳句を作ってみてくださいね。










