- 細菌・ウイルスはなにがちがうの?
- 真菌・原虫の違いも知りたい!
- もし感染したら?治療薬や抗生物質の仕組とは?
感染症を引き起こすとされる、細菌やウイルスはブロックしなくてはいけないという事はわかっていても、具体的な違いなどを細かく知っている人は少ないのではないでしょうか。
しかしこれらの物質は、私たちの生活と隣り合わせに存在しいているものばかりです。
だからこそ、きちんとその違いを把握し正しい対処法を行いたいものです。
そこで今回は、細菌・ウイルスなどの具体的な違いや治療薬の仕組みについてお教えしたいと思います。
細菌・ウイルスはなにがちがうの?
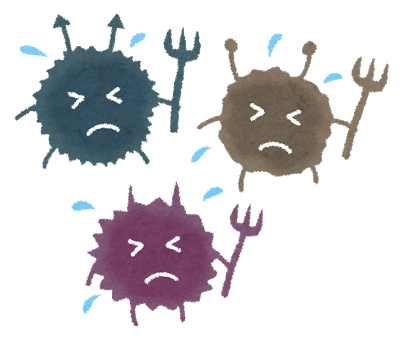
細菌もウイルスも、私たちは普段からよく口にしている言葉ですが、なんとなく同じ種類で”体に悪影響なもの”くらいの認識しかない人も多いですよね。

しかし、実はこの二つは全く違うものなのです。
では、何が大きく違うかというと以下の3つが違いの特徴と言えるでしょう。
- 大きさ
- 構造の特徴
- 増殖方法
大きさ
まずは、細菌もウイルスも目に見えるものではないので、その大きさと言われてもピンとこない人がほとんどです。
しかし、どちらが多い以下と言えば圧倒的に細菌の方が大きいといわれています。
- 細菌:0.5-5μm(マイクロメートル)
- ウイルス20~300nm(ナノメートル)
1mmの1000分の1の大きさがμm(マイクロメートル)で、100万分の1の大きさがnm(ナノメートル)となるので、その大きさの違いは歴然ですね。
もっとわかりやすく言えば、細菌は顕微鏡で見れますがウイルスは電子顕微鏡などでしか見る事ができない大きさです。

ウイルスが、どれだけ小さいかよくわかりますね。
また、このサイズですが小さければ小さい程、身体の中に取り込まれやすいといえます。
もちろん、どちらも注意したいものではありますがウイルスの方が厄介なものであると言えるのです。
構造の特徴
また、この二つは構造にも違いがあります。
- 細胞:生物
- ウイルス:非生物
つまり、細菌は細胞を持っていて、単体でも条件が揃えば生きていく事ができるのです。
その条件とは、菌の種類によっても異なりますが基本は以下の通りです。。
- 36度前後の環境
- 水分含量50%以上
- 人にとっての栄養分が豊富
このようなものが細菌が生きていける条件ですので、最近は”生物”ということになるのです。
一方、ウイルスは単体ではエネルギーを作る事ができない上に、短時間で活動ができなくなり消滅します。
ウイルスが存在する為には、意味物の細胞に感染しそこからエネルギーを得る必要がありますが、それも長期の生存はできません。

風邪などのウイルスにも、潜伏期間がありますよね。
つまり、単体ではエネルギーも作れず一定の期間を超えると生きていけないのがウイルスなので非生物となるのです。
増殖方法
では、どのように増殖していくか見ていきましょう。
- 人の身体に入り細胞に付着
- 細胞から栄養素を吸収
- 細胞を消滅させる
- 分裂を繰り返し増殖
このように、環境さえ整っていれば永遠に増殖する事ができるのが細菌です。

では、ウイルスはどうでしょうか。
- 細胞に寄生しウイルスは増加する
- 細胞が限界を超え壊れてウイルスが拡散
- 他の細胞にウイルスが飛び火
単体で増殖できない分、このようにして増殖を繰り返すのがウイルスです。
真菌・原虫の違いはなに?
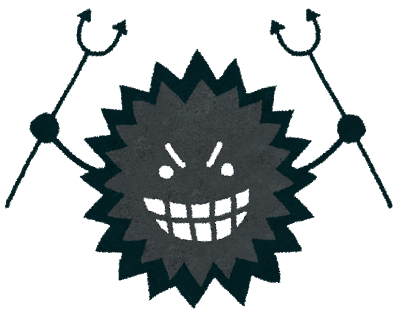

続いて、真菌と原虫の違いも合わせてみていきましょう。
真菌とは
真菌とは、いわゆるカビの仲間の総称です。
この真菌は原虫よりは小さく、細菌やウイルスよりは大きい5~10μm(マイクロメートル)と言われています。
- カンジダ
- アスペルギルス
- クリプトコッカス
- ムコール
この真菌は、湿度の高い浴室や台所、押入れといった湿気の多いところに見られます。
繁殖方法
真菌は、人の細胞に定着し菌糸が成長すると枝分かれし、どんどん発育していく仕組みとなっています。
また、酵母細胞では出芽や分裂によって増殖するといわれています。
原虫とは
原虫とは、理科の時間に顕微鏡でみたゾウリムシやアメーバなどの微生物の事を指します。
いわゆる”寄生虫”ともいえるのですが、厳密に言えば寄生虫は原虫と蠕虫(ぜんちゅう)の2種類に分けられており、原虫は1つの細胞からできているため非常に小さく、顕微鏡でないと見ることができない微生物です。
サイズは、1-20μm(マイクロメートル)と言われています。

さらに、原虫は4つの種類があります。
- 根足虫類
- 鞭毛虫類
- 胞子虫類
- 有毛虫類
繁殖方法
原虫は、直接人間に寄生するものもあれば、豚や鳥などの動物に寄生しその動物を通して人間にも寄生し、場合によっては人間を死に至らしめることもあるのです。
例えば、マラリア原虫は蚊によって媒介され、世界では年間3-5億人が感染し、年間200万人もの命を奪っているのが現状です。
感染したら?治療薬や抗生物質の仕組とは?


これらに感染した場合、どのような治療薬が効果的なのでしょうか。
感染するとどうなる?
まずは、感染するとそれぞれどうなるのでしょうか。
- 細菌: 大腸菌(O157)感染性胃腸炎
- ウイルス: インフルエンザ 麻疹
- 真菌: 水虫 カンジダ
- 原虫: マラリア 膣トリコモナス
上記はあくまで一例なので、他にも様々な病気に感染する事があります。
治療薬は?

では、それぞれの治療薬や方法を見ていきましょう。
細菌
細菌は、細胞あるいは増殖を抑制する抗菌薬が有効な治療薬といわれています。
また、細菌の特性は様々なのでそれに応じた抗生物質と合成抗菌薬があり解決できます。
さらに、抗菌薬を内服する量や期間も、感染症の場所と原因菌の組み合わせで変わってくるので注意が必要です。
ウイルス
ウイルスの治療薬は、現在も開発段階で種類が少ないと言われています。
その中で、抗ウイルス薬としてはウイルス自体の増殖機能を抑制し、ウイルスに直接作用するものがあります。
また、感染者の免疫機構を利用して抗ウイルスの免疫機能を調節するものがあります。
一方、ワクチンの予防接種で防げるものもありますが、防げないウイルスも多数あるのが現状です。
真菌
真菌のB場合は、細胞膜を破壊したり細胞膜の合成を阻害する抗真菌薬があります。
その、抗真菌薬は外用剤と内服薬・注射薬の3方法が存在し、多くの外用抗真菌剤はカビの細胞膜の合成を阻害する効果があります。
原虫
原虫にはワクチンを使用しますが、そのほとんどが研究段階のものであると言われています。
また、耐性原虫というワクチンに耐久性がある原虫も出現しています。
正しい処方が大事

このように、それぞれの症状によって治療法や薬はちがいます。
例えば“抗菌薬”とは、細菌を壊したり増えるのを抑えたりする薬のことを指し、その中でも微生物が作った化学物質を抗生物質、抗生剤と言います。
だからこそ、細菌以外の病原体であるウイルスや真菌が原因となる感染症には効果を期待できないと言えるのです。
また、”風邪を引いた”という例で考えてみても、私たちは単純に”風邪”という認識でしかありませんが、同じ風邪でもウイルス性のものもあれば、細菌が原因のものもあります。
これらは、医療機関を通してわかる事ですが、早めに正しい対応を選択する事が大切なのです。
つまり、それぞれの違いをきちんと知り正しい処方を早めに行う事が、様々なトラブルを防いだり治す一番の方法をいえるのです、
さいごに
いかがでしたか。今回は4つの菌や微生物の違いや、治療薬をご紹介しました。
すべて、普段私たちの身近にあるものばかりですが、実はその違いを正しく説明する事は意外と難しいですよね。
しかし、その違いや特徴を正しくし知り適切な対応ができる事が、症状を大きくしない方法でもあるのです。
ぜひ、参考にしてみてください。
虫・虫刺されについて















