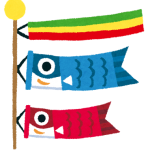- 鯉のぼりの数え方は1匹2匹じゃないの?
- 鯉のぼりの数え方は意味があるの?
みなさんは、鯉のぼりを数えるとしたらどのように数えますか?
鯉のぼりの正しい数え方と意味を知っている方は少ないかもしれません。

鯉のぼりは1匹、2匹と数えるものではないようですね。
鯉のぼりを飾ってお子様の成長を祝うのなら、正しい知識を持って風習を子どもに見せてあげませんか?
今回は、鯉のぼりの正しい数え方と意味を説明していきます。
菖蒲(しょうぶ)づくしだった端午の節句

昔は端午の節句の時期に盛りを迎える”菖蒲”が色んな形で用いられていました。
端午の節句は、菖蒲の節句とも呼ばれています。菖蒲は古来から健康を保ち、邪気を祓う力があると信じられていたのです。
菖蒲湯に入ったり、菖蒲酒を飲んだり、菖蒲枕で眠るなどハーブのように活用されていました。
強い香りで薬効を得るだけでなく、家の軒に飾って邪気を祓うという風習もあったのです。

まさに菖蒲づくしの1日!
そんな端午の節句は、時を経ても形を変えて今も尚、端午の節句の風習は受け継がれています。
5月5日の端午の節句は、男の子の健やかな成長を祝う日。
- 柏餅、ちまきを食べる
- 菖蒲湯に入る
- 鯉のぼりを立てる
- 鎧兜、五月人形を飾る
このようにして男の子を祝う日です。
鯉のぼりも現在の形になるまでに色んなプロセスがありました。
端午の節句の「鯉のぼり」

端午の節句に鯉のぼりがさまざまな場所で飾られています。
ゴールデンウィーク中の5月5日端午の節句には、たくさんの鯉のぼりが飾られているところへ足を運ぶのも良い思い出になりそうですよね。。
そもそも、端午の節句がどのようなもので、なぜ鯉のぼりを飾るのか、ご存知ですか?ここからは鯉のぼりに注目してお話していきます。
「鯉のぼり」は中国の故事の中に激しい流れの滝(竜門の滝)を登りきった鯉が竜となって、天に登ったという伝説、「登竜門」の話が起源となっています。
また清流だけでなく、池でも沼でも生きることができる強い生命力を持った魚でもあることも関係しているかもしれません。
鯉のぼりが広まった江戸時代
江戸時代、武家では男子が生まれると、家の家紋が入ったのぼりなどを立てていました。
江戸時代中期頃になると庶民にも広まり、「登竜門」の伝説にちなんで、鯉のぼりが飾られるようになったと言われています。
この頃は和紙に鯉を描いて飾られていました。そしてその鯉のぼりには、立派に成長するように立身出世を願う意味が込められたのです。
最初は黒の真鯉だけだった!

鯉のぼりというと黒、赤、青などの鯉が定番ですよね。
江戸時代では染料が限られていたので、黒の「真鯉」だけでした。
それから染料の技術も上がって、和紙から布製に変わり、さまざまな色の鯉のぼりが作られるようになったのです。
1番大きい真鯉はお父さん。小さく青い鯉は子ども。鯉のぼりの歌でも分かるように、それぞれ表していることが違います。
- 黒 → 大黒柱のお父さん
- 赤 → 生命を担って家庭を守るお母さん
- 青 → すくすくと成長していく子ども
家族が増えるに従って、紫や緑、ピンクなどの鯉を増やしていく家庭もあります。
数が増えることもある鯉のぼりですが、正しい数え方は1匹、2匹ではありません。
鯉のぼりの正しい数え方

鯉は魚だし、「匹」ではないなら・・・?
「匹」じゃないなら『尾』なのかな?と思った方もいるのではないでしょうか?私も鯉のぼりの由来や意味を知るまではそうでした(笑)
しかし「尾」も不正解です。
旒 (読み方:リュウ)
“リュウ”という数え方をします。
鯉のぼりが1つなら「一旒」、2つなら「二旒」ですね。
「旒」なんていう数え方、今まで聞いたことありましたか?
辞書で調べると「旒」の意味は、
- 旗につける
- 吹流し
- 旒:助数詞
という意味がありました。
旗やのぼりなどを数える時に用いる助数詞なんだそうです。

お店などのセールの”のぼり”も一旒と数えるということですね。
また、この鯉のぼりの数え方には諸説があり、「流」という文字を単位に「リュウ・ナガレ」という数え方をする場合もあるのです。
正しい数え方であって、1匹、2匹と数えても伝わらないことはありません。
テレビでは「●匹」という数え方も使われていたり、通販などを見ると5本セットや5尾セットなどの表現もされています。
保存してある状態では、「枚・マイ」で数えるようですよ。
鯉のぼりを買うときにも伝わりますから、それほど数え方は気にされていないのでしょう。
ちなみに生きている鯉はどう数える?

生きている本物の鯉はどう数えるのでしょうか。
池や沼など水面に向かって口をパクパクさせて泳いでいる鯉は、そんな数え方をしていますか?
こちらも1匹、2匹、『1尾』と数える方が多そうですよね。普通の魚は「尾」で数えますからね。
本物の鯉の数え方
- 折(オリ)
「オリ」と数えるんですね。
これもなかなか知っている人は少ないかもしれません!
数え方って意外とたくさんあって面白いですよね。
正しい数え方【番外編】

お子様と一緒にものの数え方を本で学ぶのも楽しそうですね!
日本にはものによってさまざまな数の数え方がありますが、数え方のことを助数詞と呼びます。
日本ではその助数詞の数、なんと約500種類も存在するんだそうです。
鯉のぼりや生きている鯉の数え方も500種類のうちの1つですから、知らない人も多いのは仕方ないかも・・・。
魚類だって色んな数え方があって、意外とまぎらわしいですからね。

数を数えるときにはいろんな数え方がありますが、これは知っていますか?
神様の数え方もあるのです。神様の正しい数え方。
それは、「柱・はしら」と数えるんだそうです。一柱、二柱・・・というように数えます。
ここでは柱という読み方になったことは割愛しますが、知るとなるほど~と納得しますよ♪
どんな鯉のぼりがお好みですか?
一般的な鯉のぼり

鯉のぼりを飾るといっても、家の環境によってはサイズを選びますよね。
歌のように屋根より高い大きな鯉のぼりをお庭に立てるご家庭もあることでしょう。
空を泳ぐような鯉のぼりを立てるお父さんやおじいちゃんは大変かもしれませんね・・・。
「小さめ鯉のぼり」
大きいものだけではなく、玄関先に飾れるサイズやベランダに飾れるタイプ。
「置物こいのぼり」
また、外に飾るのは向いていないお宅には、置物タイプの鯉のぼりもあるのでおすすめです。置物の見た目も可愛いからいいですね。
お好みの鯉のぼりを飾って、ぜひお子様と一緒に鯉のぼりや端午の節句についての話題の時間を設けてみてはいかがでしょうか。
まとめ
端午の節句に飾る「鯉のぼり」には男の子の健やかな成長を祝い、立身出世の願いが込められています。
鯉のぼりの正しい数え方は、吹流しの意味もある「旒・流」が正しい数え方になります。
しかし、1匹、1尾などの数え方でも十分に伝わり、間違いでもないようです。

鯉のぼりの数え方、あまり聞きなれない数え方でしたよね。
子どもに聞かれたときにも正しく教えてあげることができますし、大人同士でも豆知識として披露できそうですね。
鯉のぼりの由来や意味も興味深いですが、ものの正しい数え方も色々と知りたくなるのではないでしょうか。
鯉のぼりに関する記事