- クラスだよりの書き出しはどうすれば良い?ポイントはどこ?
- 文章を書くコツは?クラスだよりに含めると良い内容
- 【6月】保育園や幼稚園でのクラスだよりの書き出し文例について
保育園や幼稚園で各クラスだよりについては、毎月、どのようなことを書くべきか、先生方も頭を悩ませているのではないでしょうか?
ここでは、保育園や幼稚園で書く6月のクラスだよりの書き出しの文例や書き方のコツについてご紹介したいと思います。
クラスだよりの書き出しのポイントは?
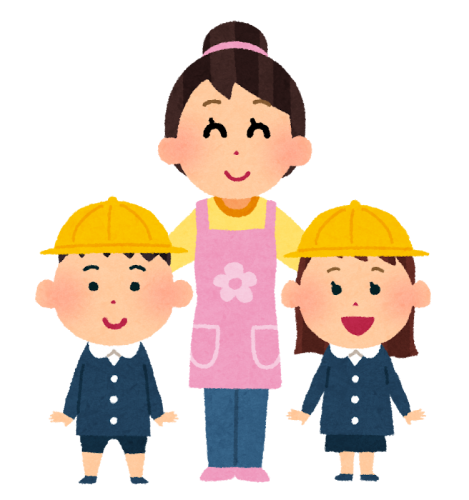
クラスだよりは、毎年その月々の内容を考えるのは先生にとってとても大変なお仕事です。
なぜなら、毎年決まったことを書いていれば良いという訳ではなく、子供たちの様子や保育園、幼稚園で行う行事、新しく企画したカリキュラムなど、様々なことが毎年流動的に変わることもありますよね。
その度に書き出しに悩んでしまうという先生に対し、クラスだよりを書くコツについていくつかご紹介していきます。
では、クラスだよりはどのようなポイントで作るべきでしょうか。
誰が読んでも楽しいクラスだよりにする
クラスだよりは保護者にとっては子供の日々の様子や保育園、幼稚園でどのように過ごしているかが1枚の紙に凝縮されていることを期待しています。
その為、担任の先生がどのようなことを書いてくれるのかを心待ちにしています。
特に新入園児ともなれば、6月とは言え、まだ入園して間もない為、保育園や幼稚園での過ごし方については、どの保護者の方もとても気になると思います。
先生が書いてくれるクラスだよりは、このようなことからとても重要なお手紙となっているのです。
クラスだよりに子供たちのことを心を込めて書く
クラスだよりは、子供の日々の活動やクラスでの活動、また、担任である自分自身のことを保護者に伝えるためのものです。
その為、伝えたい相手がいる為、その方に対し、どのような内容をどんなふうに伝えるかがとても重要なポイントとなります。

特に重要なことは、相手に伝えるために書くことです。
実際にはここが基本となっているのですが、案外このことに気付いていない先生も多いようです。
単に日記のように書いて、こんなことを行った、こんな様子だったなどというように、そのような書き方が間違っているとは言えませんが、それは単に先生の自己満足にすぎず、読み手に伝える内容になっていないことが多いです。

その点に注意しましょう。
あくまで読み手が存在しているため、どんな情報を盛り込むべきかを考えましょう。
クラスだよりの例文
例えば、ある日の午前中に、みんなでお砂遊びをしたというシチュエーションに対し、先生が2つの文章を書きました。
〇月〇日は、みんなで砂場で山を作ってトンネル作りをしました。
子供たちはおおはしゃぎで楽しんでいました。

これでは、何となく伝わりませんね。
〇月〇日、暖かい日差しが差し込む中、園庭の砂場では、みんながお砂場セットを持って順番にお山を作りました。
そこに上手にトンネルを作り、〇〇君がおもちゃの電車をくぐらせていました。
すると、みんながそれを見て、「すごい!トンネルできたーっ!」ととても大喜びでした。
次回はみんなで泥だんご作りです。
どんなお団子ができるか楽しみです!
このように、その日のその行動や言動がわかるような雰囲気のある文章に仕上げることで、保護者は子供たちがこんなに楽しいことをして遊んでいるのだということが、文章を通じてダイレクトに伝わってくるのです。
子供の雰囲気を伝えようとする気持ちが大切
確かに、文章ですべてのことを伝えるのは非常に難しいことであると言えます。
しかし、その文章を読み進める中で、その時の様子や雰囲気が少しでも想像できる内容であれば、クラスだよりとして成功!という訳です。
とは言え、クラスだよりを成功させるためには、先生が日々の子供たちの動きや様子をしっかりと観察し、一人ひとりのことをしっかりと把握しておくことが大切です。
素敵なクラスだよりを作る=担任の先生が、いかに日々の保育をしっかりと行っているかがわかるのです。
表面的なことではなく、具体的なひとつのエピソードを盛り込むだけで、全体のクラスだよりの雰囲気が一気に明るくなります!
ぜひ、相手に伝えるためのクラスだよりを作成しましょう。
クラスだよりの全体像を捉えて書く
クラスだよりを楽しいものに仕上げる為には、全体像を捉えて書くことも大切です。
例えば、内容やお知らせをどの位置に配置するのが良いかなど細かな構成を考えましょう。
- クラスだよりにサブ的な愛称をつける
- クラスだよりは大きくでもB4サイズ
毎回、そのクラスだよりを読み手の人にとって読みやすい場所に配置させることが大切です。
また、クラスだよりのタイトルは1年を通してそのクラスのイメージに合ったものを考えましょう。

覚えてもらいやすいものが良いですね。
もしも保育園や幼稚園によって、また、学年によって様々な愛称があるのであれば、サブ的な名称を考えてみると良いですよ。
毎回決まったコーナーを作っておく
毎回、同じ場所に同じことが書いてあるコーナーを作りましょう。
そのコーナーは毎月同じであることが読み手にとってとても読みやすく、意外にも楽しみにしている方もいるのです。
クラスだよりの冒頭に担任のあいさつを含める
クラスだよりの書き出しには、どの先生も頭を悩ませていると思います。
そんな時こそ、毎回のクラスだよりの書き出しは、まずは自分のあいさつや最近感じた保育園や幼稚園での出来事などについて短く紹介してみましょう。
ここでくどくど長い話を書き続けてしまうと、全部読んでもらえないといったことになりかねません。

その為、短く、さりげなく書くようにしましょう。
前回から引き続きのコーナーを作っておく
毎回終わりがなく、「次回へ続く」とするようなコーナーを作っておくだけで、先月の続きを見たくなるものなので、クラスだよりを隅々まで見るようになります。
保護者も案外このようなコーナーを好む方が多いと思いますよ。
伝えたい内容を一番に伝えよう
保育園や幼稚園での出来事などに対し、大切な事柄や必ず保護者の方へ伝えておきたい内容などがあれば、まずはそれについて一番に伝えることが大切です。
たくさんのポイントがあるように感じると思いますが、実際にはこのような点に注意し、コツをつかむことで、とても楽しいクラスだよりが出来上がります。
実際、読みにくいクラスだよりだと、きっと最後まで読んでもらえないと思います。
そうならないように、先生も一工夫必要になるという訳です。
6月のクラスだよりの書き出しアイデアは?
では、6月の梅雨時期ともなった際にクラスだよりの書き出しの言葉として良いアイデアをご紹介します。
書き出し分について
- あじさいがとても綺麗に色づき始めました。
- 園庭のあじさいが色とりどりとても可愛い花をつけています。
- あじさいが綺麗に咲き始め、梅雨の訪れを感じます。
- 梅雨入りとなりましたが、思いの他晴天が続いていますね。
- 雨が続き、なかなかお散歩に出られず、力があり余っているという子供の姿が目立ちます。
このような書き出しでスタートすると、文がきれいにまとまります。
文章を書くコツは?クラスだよりに含めると良い内容

クラスだよりに含めるべき内容については、これまでご紹介してきました。
次は、実際に文章を書く時のコツをお伝えします。
文章を正しく書くためには、読み手に対して楽しみがあり、とても分かりやすく、読んでいてその場の雰囲気を感じることができるような文章に仕上げることが大切です。
子供の日々の成長や保育園や幼稚園生活の楽しさを盛り込む
子供が毎日保育園や幼稚園での生活をどのように過ごしているのか、楽しそうな様子がうかがえるような書き方をすることで、読み手もとても微笑ましくもなり、楽しく読み進めることができます。
また、次はどんなことがあったのだろう?などといったように、文字を読むだけでわくわく感が止まらないという状態になるような書き方をしなければいけません。
子供の日々の変化や心の変化について感じたことを書く
子供の日々の様子を文章で伝えるには限界もあります。
しかし、子供の「心の変化」については、先生自身が感じること、その子供の年齢相応に感じることを交えながら文章を書く為、とても書きやすく、感想も文章に表現しやすいと言えます。

最も書き進めやすい文章だと思います。
子供の日々の姿を見て感じたことを素直に書く
子供は毎日成長しています。
その為、子供の意外性を感じることがあれば、それをノートに書き留めておき、クラスだより作成時に使用してみましょう。
例えば、”親でさえも気づかないようなことに先生が気付いた!”というような内容を盛り込むと、保護者は食い入るようにクラスだよりを読むと思います。
親の前で見せない、あどけない姿なども書きつづってみると良いでしょう。
保育者としての意見や見解について書く
保護者の立場ではなく、あくまで保育者としての意見として、時には少し保護者に対してカツを入れるような内容があっても良いでしょう。

気が引き締まる思いも時には必要です。
その際、「家庭での取り組みのお願い」などと題名を入れ、それについての内容を記載するようにしましょう。
クラスの中でも良い出来事に対してはその子供の名前を挙げてみる
これについては、例えば30人クラスだったとしましょう。
一人1回は、必ずクラスだよりの中に名前が登場するように記載しなければなりません。
1年は12ヵ月しかありませんので、計算すると毎月2〜3人は必ず名前が掲載されなければなりません。
どの子供が登場したかについては、担任の先生がしっかりと把握できるようチェック表などを作成しておくと良いでしょう。
これは、”わが子が全く登場しなかった”などといったトラブルに発展することもある為、徹底して管理を行うようにしなければなりません。
また、保育園や幼稚園によっては、名前を掲載することすらNGであることもあります。
その場合は、イニシャル等で対応するようにしましょう。
名前掲載が可能な保育園や幼稚園では、下のお名前を記載し、『〇〇くん、〇〇ちゃん』という表記で記載するようにしましょう。
先生自らの手で書くイラストを描くこと
クラスだよりはある意味、担任の先生のカラーも必要です。
“字は綺麗に書けるけど、イラストは下手だ”などといった先生であっても、毎月のクラスだよりに空白欄が出ないよう、そのような位置には手描きのイラストなどを描くようにしましょう。
手描きにする味や、先生の雰囲気が伝わるような下手ウマな絵が逆にウケがいいのです!
その方が実は「このクラスだよりを読みたい!」と思ってもらいやすいのです。

不思議な感覚ですよね〜♪
適度に改行を入れながら書くこと
また、文章だらけになってしまうと返って読みにくくなってしまいます。
少しでも読みやすいように工夫する意味でも、改行をところどころ含め、文章と文章の間は隙間を作る方がより読みやすくなります。
文字は、ぎゅうぎゅうになってしまわないように上手に配置して書くことがコツです。
【6月】保育園や幼稚園でのクラスだよりの書き出し文例について
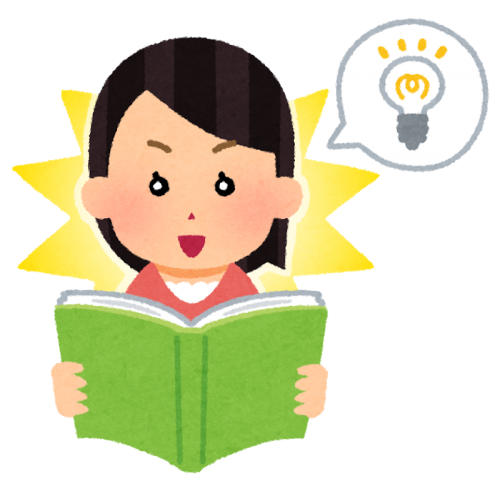

では、早速例文を見ていきましょう。
じめじめした季節がスタートしました。
園庭のアジサイがとても美しく咲き始めています。
先日、〇〇組は、雨の合間を見て、みんなで園庭へ行き、美しく咲くあじさいを観察しました。
そして、クレヨンを使用し、画用紙にアジサイの絵を描きました。
みんなであじさいの花びらの色をクレヨンで上手に色塗りしたり、折り紙をちぎってちぎり絵として貼り付けたりと自由な発想で楽しみました。
梅雨の合間のお天気の日には、みんなで園庭の草むらでダンゴムシを探して遊んだり、砂場でお山作りをして楽しみ、雨など吹き飛ばすほど元気いっぱいに過ごしています。
あじさいの花がとても美しく咲く季節となりました。
子供たちは園庭に咲くあじさいの様子が気になるのか、「今日はお外遊びできるかな」などと空を見ながら言う姿を見かけます。
雨の日はお外で思いっきり遊べない分、6月の梅雨時期に登場するカタツムリの時計を製作してみたり、てるてる坊主の製作を行うなど、様々な取り組みを行っています。
運よく雨降りではない日は、ここぞとばかりに園庭ではしゃぎ回る子供たちの姿がとても元気いっぱいで印象的です。
面白い形をした葉っぱを集めてみたり、木の実を持ち帰ったりすることがあるかもしれませんので、お洗濯の際は制服のポケットのご確認をよろしくお願いいたします。
梅雨となり、毎日蒸し暑い日が続きます。
晴れ間がのぞく日も少なく、室内遊びがメインとなる時期ですが、束の間の晴れを狙っては、外遊びに飛び出し、元気いっぱいに園庭を走りまわる子供たちも多く、幼稚園は毎日賑わいを見せています。
暑さが増すにつれ、草むらには虫たちの姿も見受けられ、最初は怖がっていたお友達も、いつの間にか自分で見つけたダンゴムシを触れるまでに成長しています。
6月下旬にはプール開きも行います。
それまで体調管理に気を付け、早寝早起きを心掛けるとともに、しっかりとバランスの良い食事を摂取するなど、ご家庭でも配慮をよろしくお願い致します。
その他の行事等に関するクラスだよりの書き出しについて
クラスだよりを作成する際はクラスの中のことはもちろん、その月に行われる行事などについてのお知らせを掲載することになります。
ほんの一部ですが、そのような行事等に関するクラスだよりの書き出しについてご紹介したいと思います。
6月〇日に交通安全指導教室を行います。
正しい信号の見方や、標識の確認、安全に配慮した指導をしっかりと受けます。
全園児対象に行う為、当日はできるだけ欠席等のないよう、今から体調管理を行っておいてください。
きちんとした学びが日々の生活の中にある事が伝わり、とても安心しますね。
〇月〇日より、お弁当が始まります。
食事の前の手洗いや消毒など、細かな点においてきちんと行うことができるよう、日々練習を重ねています。
みんなが交代してお当番を行うことで、みんなの前に立って話す経験を積み、養うことができます。
恥ずかしがり屋さんも、この時ばかりは胸を張って一生懸命頑張っています。
梅雨時期のお弁当は特に、腐らないものをご準備いただくこと、また、保冷剤などを上手に活用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
改めて、お母さんの意識を促すことでお子さんの安全を守る意識が伝わります。
給食でよく食べる枝豆の皮の剥き方についてみんなで色んな方法を挑戦しました。 皮剥きができないと最初は戸惑う子も多く、それでも一生懸命手先を使いながら剥いて食べることができました。 食育では、しっかりと噛んで味わって食べることの大切さを伝えています。 ご家庭でも、しっかりとよく噛んで食べることができるよう、声掛けをよろしくお願い致します。 できなかったことができるようになった様子が、子供の成長を感じさせてくれます。 6月4日は虫歯予防の日です。 幼稚園でも、〇〇歯科医院の〇〇先生による歯磨き指導を行います。 正しい歯磨きの方法を知ることで、虫歯予防につながります。 普段なかなか歯磨きをいやがる子供に対しては、無理な歯磨きの方法は避け、ガーゼなどを使用して汚れを吹きとるなどで対応しましょう。 ちょっとしたアイデアを盛り込むのも良いですね。 このように、保護者の方々が知りたい事を小まめに盛り込み、楽しいクラスだよりにする事が大切です。 いかがでしたか。 6月のクラスだよりの書き出しやその文例集などについてご紹介しました。 毎月作成するクラスだよりの書き出しに迷う先生は、ぜひ、このサイトを参考に、楽しいクラスだよりを作成してくださいね! 6月についての記事まとめ















