- イルカを漢字で現すと「豚」がつくのはなぜ?
- いるかの漢字表記には由来や意味がある?
海の中を自由自在に泳ぐイルカはまさに私達人間から見てもとても美しく愛らしい姿ですよね。
そんなイルカはカタカナ表記に思われがちですが、実は漢字で「海豚」と表現できるのです。
でも、イルカに漢字表記がある必要ってあるのだろうか・・・?など、疑問に思ったことはありませんか?
ここでは、イルカの漢字表記の由来や意味についてご紹介したいと思います。
イルカは漢字で書くと「海豚」?
漢字表記に由来や意味がある?
https://www.youtube.com/watch?v=cv0tlGBplRM
イルカを漢字で表記すると「海豚」になるのですが、漢字の由来について説明する前に、イルカについておさらいしておきましょう。
イルカとはどんな生物?

イルカなのに、クジラ目ってどういうことなのでしょうか。
イルカとクジラについては、生物分類上において、その身体の作りについてはそこまで大きな差がないと言われているのです。
とは言え、そもそも、日本においてカタカナ表記される「イルカ」や「クジラ」は、そもそも名前が異なる為、同じ科に属することはなく、別々の生き物として多くの方が認識していると思われます。
イルカとクジラのそもそもの身体の作りに大差がないと言うのであれば、一体どこでその個体を識別すれば良いかと言うと、それはやはり身体の大きさです。
- 体長4m未満がイルカ、それ以上のものをクジラとして捉えられる。
しかし、同じイルカや同じクジラにも、種類が様々である為、体長だけで識別するのは実際には難しいことです。
クジラの中で身体が小さいものとして知られている「マッコウクジラ」「ゴンドウクジラ」については、体長が4m未満である個体も確認されています。
そうであるにも関わらず、それはイルカではなくクジラとなる訳ですから、その識別はさらに難しいものになりますね。
それを言ってしまうと、イルカの中にも「シロイルカ」の体長は5m以上にもなります。
また、イルカの仲間とされている「シャチ」も、実はイルカの仲間なのです。
イルカの特徴
- 海に生息する生物
- 一般的な体長が1.3~10m。
- 重量は30~300kg
体長や重量は個体や種類によってばらつきが見られます。
イルカは海に生息する生き物ですが、「カワイルカ」と呼ばれるイルカは淡水の川に生息しているものもいます。
イルカの種類によっては、汽水域で生活するイルカも存在しているのです。
イルカの大半は身体の色がブラックに近い色をしていたり、濃いグレーをしていますが、イルカにも様々な種類が存在し、全身がホワイトや薄いピンクといった色を持つイルカも存在します。
イルカに先祖がいるってホント?

イルカの先祖はどんな姿をした生物だったのでしょうか。
このメソニクス目は、実は4足歩行している生物だとされています。
その為、カバや牛などが進化を遂げたことにより、イルカが誕生したのではないかという説も残っています。
しかし、仮にメソニクス目がイルカの先祖であったとしても、どのように陸上生物が水中生活に適応できるように進化したのかについては、全く明確な文献も残っていません。
つまり、イルカやクジラの起源は、哺乳類の進化において最大の謎のまま現在に至っているのです。

イルカの身体の形は、紡錘形です。
身体の中央部分が太く、頭や尾びれは細身な身体の形をしています。
背中に三角形の背びれを持ち、種類によっては背びれのないイルカも存在します。尾びれを上下にしっかりと動かし、躍動することで水中を自由自在に泳ぐことができます。
かつて4足歩行していたとされる先祖がいることから、前足となる部分には胸びれを持ちます。
そして、後ろ足となる部分には、ひれなどがなく退化し、体内に骨がわずかに残っていると言われています。
イルカの漢字表記の由来と意味
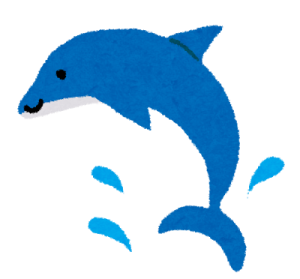
では、イルカの漢字表記の由来や意味について迫ってみましょう。
イルカの語源は?

イルカは、その語源にいくつかの諸説が存在しています。
どれをとってもイルカらしい雰囲気を感じます。
「行く」と同じ意味を持つ「ユルキ」がイルカに転じたと言われる説
- イルカがスイスイと優雅に泳ぐ姿を表しています。
イルカ漁の際、大量の血が当たり一面に広がることから「チノカ(血臭)」が転じたと言われる説
- イルカの追い込み漁が行われていた際、イルカが突かれ、大量の血が流れたことにより、辺り一面が血の臭いがしていたことから「チノカ」と呼ばれ、それが転じたと言われています。
「イルカ」の「イル」を魚とし、「カ」は食用という語を用いたという説
- 人間がイルカを食べていたという時代があったことを象徴している言葉だと言われています。
イルカは入江に入ってくる為、「イルエ」が転じたと言われる説
- イルカが入江内に入ってくることに由来しています。
イルカが飛んだり跳ねたり水面に姿を現わしたり水中に潜ったりする「イリウク(入り浮く)」が転じたと言われる説
- イルカが海面に顔を出したり水中に潜ったりと、浮き沈みする魚であることを指しています。
このような語源を持つと言われているのです。
イルカの漢字の由来は?

イルカは英語で「Dolphin」と表記されます。
そして、イルカが英語表記だけではなく漢字表記がなされる生物としても知られています。
それも実に5つもあると言われているのです。
- 海豚
- 鯆
- 魚+普
- 魚+専
- 逐
と書くそうです。
また、それぞれによって由来があるのです。
一般的にはイルカは漢字表記される際、「海豚」と書き、これを「イルカ」と読んでいます。
中国においては、イルカを「海豚(カイトン)」としており、実際に日本に伝わったのは中国からだと言われているのです。
中国語では、「紅豚」とも書かれ、これは日本でも明治維新前までこの漢字が定着していました。

他にも「鯆」と書いて、「イルカ」と読みます。
イルカは海の中で生活している哺乳類であることから、魚編は魚+哺乳類の甫が組み合わさって「鯆」となったという説もあるそうです。
イルカは新陳代謝の能力が高い
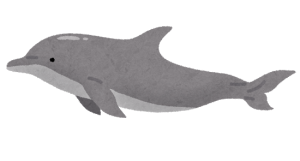

イルカは何とも驚異的なスピードで代謝を行っているのです。
イルカの皮膚はツルっとしていて、全く抵抗なく泳ぐことができると言われています。
そして、そのイルカの皮膚の新陳代謝は、たった2時間もあれば新しい皮膚が生まれると言われています。
海の中でたくましく生きるためには、外敵から自分の身を守る必要があります。
その為、どれだけ速いスピードで泳ぎ、危険回避しなければならないか、また生きていく上で自分の力で食料を確保しなければなりません。
このようなことから、イルカは海の中で生きる生物として、驚異的な進化を遂げていることが分かります。
まとめ
イルカの漢字表記には、海豚、鯆、魚+普、魚+専、逐といったように、5つもの漢字が存在するとは知りませんでした。
一般的に知られているのは「海豚」であり、海で泳ぐ姿が豚のように見えることからその漢字になったと言われています。
イルカは身体能力も高く、また新陳代謝が高く、知能も優れている為、海の中で生きる生物の中では、一番の進化を遂げた生物であると言われているのです。
私達が休日に行く水族館で元気いっぱいに泳ぐイルカにも、漢字表記されるようないわば名前があり、それには奥深い由来、そして意味があるんですね。
実際にイルカウォッチングやイルカショーなどを観賞する機会があれば、イルカの漢字表記の由来を思い出してみるのも楽しいと思いますよ♪
動物の漢字の意味・由来について
イルカに関する記事

















