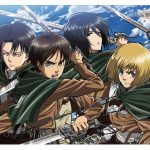- すいかはどうして「西瓜」ってかくの?
- 漢字の由来は?
夏にスイカを食べながら、ふと「なんでスイカって西の瓜って書くんだろう」と思ったことのある方。
西瓜の漢字の由来と、西瓜の歴史を調べてみました。以下を参考に、西瓜について学びましょう。
「西瓜」という漢字の由来
もともと、西瓜という漢字は中国の言葉です。
10世紀ごろに中国の西に位置する「ウイグル」という国からもたらされたため、「西瓜」と名づけられたそうです。
ちなみにウイグルとは、現在の中華人民共和国の中の「ウイグル自治区」やカザフスタン・キルギス・ウズベキスタンの辺りにかつて存在した国です。
14世紀に、今度は中国から日本へともたらされたときに、「西瓜」という名前もそのまま伝わったのですね。
日本における西瓜の歴史
室町時代の初期、南北朝時代の書物『空華集』に、西瓜についての記述があることから、日本に西瓜がもたらされたのはこの時期であると考えられています。
南北朝時代は年号にすると1,336~1,392年。この時代かその前に、明や元(中国)との貿易によって輸入されたのでしょう。
唐の発音で「西」は「すい」といいます。それゆえ、日本でも「西」を「すい」と発音。
14世紀ごろに、名前や発音と共に中国から伝わったのが、日本における西瓜の最初の歴史だと考えていいでしょう。
西瓜の基本情報
- 科目
:ウリ目ウリ科 - 原産地
:熱帯アフリカ - 英名
:Watermelon - 日本の主な生産地
:熊本県・千葉県・山形県 - 主な栄養素
:ビタミンA、、B6、C、βカロチン
夏の風物詩として、日本の食卓でも欠かせない西瓜。
栽培気温の幅が大きい
日本の主な生産地は、上にも書いたとおり熊本や千葉、山形県です。これらの地域が日本における西瓜生産量の1~3位を占めています。
熊本は九州。千葉は関東。山形は東北です。この後に新潟、鳥取、長野と続き、生産量第8位はなんと北海道。
このことからも、西瓜は日本の北から南までの、大きな温度差に耐えうる食物だと分かりますよね。
西瓜は九州でも北海道でも栽培が可能な、気候に左右されずに育てられる、とても強い食物です。
西瓜の品種
西瓜は品種改良が進み、多くの品種が存在する植物です。
でんすけ西瓜
:北海道当麻町で栽培。真っ黒な外観と真っ赤な果肉。初瓜では35万円の値がつく食べ応えがある人気の西瓜です。
尾花沢すいか
:古くから西瓜の栽培が盛んな地域、山形県尾花沢市の名物。日中と夜間の寒暖差の大きい地域ゆえに、陶土の高いおいしい西瓜が育ちます。
伊佐沢すいか
:日本国内で西瓜の生産が3位の山形県。西瓜のブランドもたくさんあります。
極実すいか
:倉吉市で一般的に生産されるのは「祭ばやし」という品種です。これに対し、西瓜に西瓜を接ぎ木する特殊農法の「極実すいか」も少量生産され、その溶けていくような不思議な触感が売り。
すいかの別の呼び名「水瓜」の由来
上に紹介した、南北朝時代の書物『空華集』の中で西瓜に関する記述があることが知られるまでは、西瓜は16~17世紀の江戸時代にもたらされたものと考えられてきました。
実際に西瓜が庶民の間で普及したのが、江戸時代だったのかもしれませんね。西瓜はご存知のとおり、とっても水っぽい果物です。

ほとんど水?といってもいいくらいですよね。
また、唐語の「西(すい)」の読みが、日本語の「水」の音読みと同じだったため、「水瓜」と表記されることもあります。
すいかという果物をよく知るわれわれからすると、「西瓜」よりも「水瓜」のほうがはるかにしっくりきますよね。
そういえば、英語でも西瓜は「watermelon」といいます。
西瓜に似たような漢字の野菜

「西瓜を漢字で書いて!」って言われたとき、「南瓜」って書いてしまう人、多いですよね。
西瓜も南瓜も当て字なので、覚えられずについつい間違えてしまう人も多いと思います。
他にも冬瓜や胡瓜、糸瓜など、漢字で「瓜」とつく植物はとても多いです。主に食用として栽培されていて、古くから人間の暮らしを支え続けてきました。
以下に、有名どころのウリ科の食材を挙げてみますね。
- 西瓜(すいか)
- 冬瓜(とうがん)
- 糸瓜(へちま)
- 胡瓜(きゅうり)
- 木瓜(ぼけ)
- 烏瓜(からすうり)
- 隼人瓜(はやとうり)
ひらがなは知っていても、漢字で書けるかどうかは、不安になりませんか?この機にぜひ、覚えてみてください。
西瓜はなぜ切って売られているの?
鮮度が命の果物。切り分けたとたんに、切った箇所から酸化が進み、腐敗してしまいます。にもかかわらず、スーパーなどで売られている多くの西瓜は、切られていますよね。
新鮮なままいただきたい方にとって、切り分けた西瓜はいまいち。と思われるかもしれません。西瓜を切り分けるのには、実はいくつかの理由があるのです。
西瓜から学ぶ日本の核家族化問題

西瓜は見てのとおり、とても大ぶりな果物です。
昔の農村地帯では、何十人もの大家族がいくつもありました。西瓜を切っても十分消費できる頭数があったのです。ところが今はどうでしょう。
まるごと一個の西瓜を切ったところで、家族の人数はせいぜい4~5人。とても食べ切れませんよね。結局は家で、食べ残った西瓜を保存することになります。
日本では、核家族化によって、1つの過程における西瓜の消費人数が減ってしまったということ。
だから、核家族に合わせたサイズに切り分けて販売する方法が、定着したのですよね。
冷蔵庫のスペース問題
1つの家族人数の減少によって、西瓜の切り分け販売が一般化したとお伝えしましたが、別の視点からのもう一つ理由があります。

今度は西瓜の収納場所問題です。
4~5人用の大きな家庭用冷蔵庫であっても、西瓜半分を収容するのは至難の業。他のものをよけたとしても、スペースは限られています。
大きな西瓜を丸ごと一個買っても、収納場所がないのです。
かつての日本では、川で冷やした西瓜を切り分けて、数十人もの家族で分けて消化していました。
昔を思うと、現代の核家族化や、西瓜を川で冷やせない環境が、物悲しくなりますよね。
まとめ
食欲が落ち発汗量の増える夏の季節に、人々の水分補給源として親しまれてきた西瓜。
西瓜という漢字の由来と、歴史背景。また食用植物としての詳細情報、西瓜に関する疑問点などを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
- 10世紀に中国の西の国(ウイグル)から伝わったため、中国で「西瓜」と名づけられた。
- 14世紀の南北朝時代の書物『空華集』により、西瓜はこの時期に日本に伝わったと考えられる。
- 「西瓜」という漢字は、中国語(唐語)をそのまま受け継いだ。
- 唐語では、西を「すい」と発音する。
- 西瓜は水っぽい食べ物なので、「水瓜」とも呼ばれる。
- 西瓜の英名は「watermelon」てある。
- 西瓜と似たような漢字のウリ科の植物もたくさんある。
- 西瓜は核家族化で消費量が減ったために、切り分け販売が一般的となった。
- 冷蔵庫に西瓜を丸ごと収納するのが難しいため、消費者にも切り分け販売が好まれる。
10世紀にウイグルから中国へ。14世紀に中国から日本へ。16~17世紀江戸時代に、日本の庶民の間で普及を始めた西瓜。
漢字の由来を知ることで、広大な中国の更に向こうの国、ウイグルからもたらされた、西瓜という植物の大いなる旅を知ることができます。
これさえ知れば、二度と「南瓜」や他の植物と書き間違えることはなさそうですね。
果物・野菜の漢字表記について