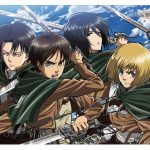- 武士道とはどんな精神?
- 武士道は儒教、仏教、神道のハイブリッド
- 日本の武士道に世界が感動した
- 「義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義」は日本に伝わる7つの徳目
武士道という言葉自体は、新渡戸稲造の著書「武士道」によって広まり、1900以前にはこのような言葉がいかなる文献にも載っておらず、江戸時代には一般的な言葉ではなかったとの指摘があります。
武士道は江戸時代に支配階級である武士に文武両道の鍛錬を徹底させたことから始まります。今回は武士道精神の意味と海外での反応、現代の日本に伝わる7つの徳目を考えてみましょう。

武士道とはどのような精神?
武士道とは?
「武士道とは何?」と聞かれた時、貴方はどのように答えますか。また正確に答えられますか。
武士道とは武士の行動原理でもあり、武士のあり方を追及するための思想と考えますが、それだけだは具体的ではなく明確でもありません。
武士道は一言で語れるものではなく、武士が規範とする行動や発言が時代によって違いがあるので説明するには非常に難しいのではないでしょうか。

旧5千円札で有名な新渡戸稲造が書いた「武士道」
「武士道」の著者・新渡戸稲造
旧5千円札で有名な新渡戸稲造は武士道を一言で言うと「武士の掟」すなわち「高き身分の者に伴う義務」と述べておられます。
武士は戦い事を主に専門としますが、武士が世の中や社会の中心となって好きなようにされては世の中が成り立ちません。長年にわたる日本の歴史の中で武士の間でもフェアプレイの精神が求められるようになりました。
このようにして武士の生活の中に武士道という崇高な精神が生まれました。武士道は仏教、神道、儒教の影響を受けそれらをうまく取り入れた精神です。

BUSHIDO ; The Soul of Japan 英文で書かれた「武士道」は世界に広まる
英語で書かれた「武士道」 世界で大反響
新渡戸稲造は明治・対象時代の教育家でありのちに国連事務局次長として活躍した人物です。
1891年に新渡戸稲造は「武士道(BUSHIDO;The Soul of Japan)」を体調を崩しながらも英文で書き上げます。
新渡戸稲造と聞くと「5000円札の人」と連想する人が多いと思いますが、「武士道」を英語で紹介したご本人です。では新渡戸稲造とはどんな人だったのでしょう?1962年、岩手県盛岡市に生まれ、農学を学ぶために札幌農学校(現・北海道大学)に入学します。
札幌農学校とは「少年よ、大志を抱け」で有名なあのクラーク博士が初代教頭を務めたエリート校です。新渡戸さんはここの影響で西洋のことについて多く学びクリスチャンになりました。同校卒業後、新渡戸さんは帝国大学(現・東京大学)の入試を受けた際に
「われ、太平洋の架け橋にならん」という有名な言葉を残し、のちにアメリカ、ドイツへと留学のために向かうことになります。
「武士道」はなぜ書かれたかというと、新渡戸さんが留学先でベルギーの法学者に「日本の学校では宗教教育がないのですか?」と聞かれ、
即座に「はい、ありません。」と答えます。そうするとベルギーの法学者は「宗教教育がない?日本はどうやって道徳教育をするのですか?」と返します。
この質問に新渡戸さんは考えた末、日本人の心の中にある善悪の観念、正義を形成しているベースが「武士道」であることに気が付きます。
また、妻のメアリーさんからもたびたび日本にこのような思想や道徳教育がいきわたっているのかを聞かれ「武士道」を書く決意をしたとのことです。
英文の「武士道」は1900年にアメリカで出版されるや否やたちまち話題と反響を呼び、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポーランド語、ハンガリー語、ノルウェー語、ロシア語、中国語をに訳され世界に広く伝わることになりました。

アメリカのルーズベルト大統領も感銘をうけた「武士道」
「武士道」は海外にも影響をもたらした
「武士道」は日本人が英語で書き大反響を得た著書で、海外における日本のイメージを定着させた功績をもたらしました。
アメリカ合衆国26代大統領のセオドア・ルーズベルトも「武士道」を徹夜で読み上げ感銘を受け、何冊もまとめて買い自分の子供や知人友人に勧めたそうです。
また、米海軍兵学校や米陸軍士官学校の生徒たちにも「武士道」を読むように熱心に伝えたといわれております。
かの有名な発明王エジソンも「武士道」を愛読し一度も訪れることがなかった日本の文化や風習に対して深く理解したといわれており、岡部芳郎という優秀な日本人助手を雇い全幅の信頼を寄せたとのことです。
ロバート・ベーテン・パウエルも武士道から大きな影響を受け、のちにボーイスカウトを創立したとのことです。
「武士道」の影響とその功績により新渡戸稲造は1901年に台湾総監府での勤務ののち1920年には国際連盟設立の際の事務次長にも選ばれました。
1933年に日本は国際連盟を脱退しますが、その半年後に新渡戸稲造は平和の希望をもってカナダの国際会議に参加し日本を代表してスピーチを成功させますが、志半ばで帰らぬ人となります。

武士道の基本理念は7つの徳
「武士道」7つの徳目
武士道で求められるのが 義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義 です。この7つの徳が武士道の基本理念とされています。
これら7つの徳はそれぞれ深い意味があるので説明が長くなりますが簡単に表すと下記のようになるのではないでしょうか。
- 義―人間としての正しい道、正義をさします。
- 勇―自分が正しいと思った道を進むために必要な勇気をさします。
- 仁―弱者や敗者に対する情けと慈しみをさします。
- 礼―人に対する優しさ、敬う気持ちをさします。
- 誠―嘘やごまかしはしない、約束事は必ず守ることをさします。
- 名誉―自分に恥じない高潔な生き方を守ることをさします。
- 忠義―主君に対し絶対に従う心をさします。

近代日本にどのような影響?
武士道が現代の日本に与える影響
武士道の精神は現代の日本においても存在しており、多少形が変化したものの影響力をおよぼしています。
例えば公共のマナーやルールを守ろうとする心、守らない人に対して注意をする勇気、部下または年下に対して接する上司の気持ち。
一緒になって仕事に取り組む姿勢、また恥ずべき行為はしたくないという自身の名誉に対する心や救ってくれた人に対する感謝の気持ち。
などなど武士道の精神は私たちの日常に見ることができます。海外の旅行者が日本に訪問し、まず最初に感じるのは街並みが綺麗で社会の秩序が保たれていることに感心します。
阪神淡路大震災や東日本大震災の時には暴動や略奪などが起きることなく、また悲惨な目に合ったとしてもじっと耐え行儀よく並ぶ被災者の姿、地域のボランティアによる炊き出しや助け合いの姿は海外の人々には信じがたい出来事として世界に発信されました。
これらはやはり日本人の心の根底に武士道の精神が無意識に宿っているからといえるでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。今回は「武士道精神の意味とは?海外の反応と現代の日本に伝わる7つの徳目」について考えてみました。
武士道は江戸時代に支配階級である武士に文武両道の鍛錬を徹底させたことから始まりますが、新渡戸稲造が海外向けに日本特有の道徳観や行動規律を紹介した著書「武士道」が海外で大反響となり日本へ逆輸入され普及したことがわかりました。
しかし、皮肉なことに「武士道」の精神はかつて日本が国際舞台にデビューを果たし、軍国主義に傾倒した時代には国への忠誠を至上とする「教典」として利用されたりもしました。
日本人の心・アイデンティティーをいわば明示した「武士道」は欧米のように宗教が倫理や道徳のベースになっていない日本人の行動規範を武士たちの生きざまを例え創り上げたものだといえるでしょう。
武士・侍・サムライに関する記事
- 流浪の武士となる経緯や浪人との違いとは?
- 武士は食わねど高楊枝の意味・使い方
- 武士道精神の意味とは?
- 武士の食事を完全再現!平安時代と戦国時代
- 武士語に変換・翻訳が面白い!
- 武士の情け・意味と使い方を例文で
- 侍の名前でかっこいいランキング7選