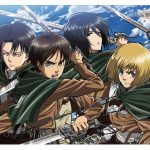- 花魁と太夫、夜鷹の違いとは?
- 名前と位について分かりやすく解説
日本古来の豪華で派手な着物にかんざしを付け、「花魁」と呼ばれるその姿は、現在の日本の時代劇でもよく見かけます。
しかし「花魁」と聞いただけでは、「昔の遊女であり高い位にいた女性」というイメージでしょう。
もしかすると「花魁」が一体何なのか分からない。。。違いが良く理解できない。。。などと言う方も少なくありません。
実際には、「花魁」と言う言葉は、18世紀の半ば以降から使用され、それまでは「太夫」や「傾城」などと呼ばれていたのです。
また、江戸時代の遊女全てが花魁のように華やかであったという訳ではありません。
ここでは、花魁と太夫、夜鷹の違いと、その名前と位について解説していきたいと思います。
「花魁」と「太夫」の違いは?

「花魁は江戸」「太夫は京都」です。
そして、江戸の吉原が遊郭で京都の島原は花街として知られています。しかし、花街は修練の場であり、江戸の吉原にはなく、違うものとされていました。
「太夫」の語源は、女歌舞伎で芸達者の役者を「太夫」と呼び、花魁は「おいらの姉さん」から取った呼び名であり、いずれも上流階級の遊女を指す呼び名であったようです。
「花魁」とは?

花魁は、江戸時代において遊女である位の高い人物と言うイメージです。
花魁は実際には昔で言うと位の高い遊女です。それでも、「花魁」と呼ばれ始めたのは18世紀の半ば以降であると言われています。もとは、江戸時代の遊女屋で働く女性は、「太夫」と呼ばれていました。
そして、見習いでついていた少女が「おいらんちの姉さん」と呼び始めたことがきっかけで「花魁」という言葉が生まれたと言われています。
そして、京都や大阪においても、最高位に位置する遊女を「太夫」と呼んでいたものが、吉原の高級遊女を「花魁」と呼ぶようになり、「太夫」=「花魁」というように変化しました。
「花魁」の元は「太夫」であり、その前は「傾城」という名がついていました。これは、「城が傾くほどのお金のかかる高級遊女」といった意味合いを持っていたのだとか。
「花魁」と呼ばれる身の女性は一流の高級遊女扱いであることから、15歳までに舞踊や和歌、お茶やお花、さらにはお琴や三味線といった実技を難なくこなさなければなりませんでした。
このような教養と美しい美貌を持ち併せた遊女しか「花魁」になりあがれなかったのです。
明治時代の花魁は?
明治時代の「花魁」や「太夫」は、一晩相手をしてもらうだけでも数十万円という金額を支払わなければならないほど最高の地位にいる遊女でした。
しかも、最低3回、花魁のもとに通う必要があるのです。また、お目当ての花魁がいるお店で派手に遊び、お金を落とす存在でなければ認められなかったのです。

その為、花魁のもとへ行くために、400万円以上必要であったと言われているのです。
一般庶民には到底無理であり、高嶺の花で合ったに違いありません。ただし、どんなにお金持ちの人でも、花魁が気にいらなければ簡単にフラれてしまうのです。
「夜鷹」とは?
江戸時代、路上で商売を行う遊女は、「夜鷹」と呼ばれ、京都では「辻君」、そして大阪では「惣嫁」と呼ばれていました。
夜鷹は、江戸の本所、鮫ヶ橋や浅草堂前の土手や材木置き場に客を呼び込み商売を行った女性を指します。
しかも、河原や林の中といった杜撰な場所でござを敷き、相手の男性と関係を持つ・・・という状況であった為、かなり大変な職業だったようです。
夜鷹の料金は他の遊女よりも破格の値段であったことから、多くの男性が買ったと言われています。安い夜鷹であれば、1回の値段が蕎麦一杯分程度であったのだとか。
しかし、夜鷹はそれだけの価格であることから、多くの男性と関係を持っていることから、性病を持った者も多く、病気をうつされる可能性は高かったのだとか。
夜鷹には10~50代、中には60代という女性もいたそうです。「花魁」=「太夫」に比べると遥かに位が下の者であることが分かります。
花魁の階級とは?

花魁の階級には、「太夫」と「端女郎」の2つの階級に分かれています。
その後、稼ぎや花魁の美貌、そして持つ教養により、「太夫」「端女郎」「切見世女郎」などといった階級があります。この中の「太夫」だけが「花魁」と呼ばれるようになりました。
一番下の身分である、「切見世女郎」は安くて多くの客と関係を持ち、そのせいで梅毒にかかっていました。
そのため、「切見世女郎」にあたることで病気をうつされ、死ぬかもしれないということから「鉄砲女郎」とも呼ばれていました。
そして、一部の富豪の遊び場としてあった遊郭は、「散茶女郎」が現れ、庶民化したと言われています。
「散茶女郎」は、「格子」の下で「端女郎」の上の階級であることから、高額な「太夫」や「格子」は少しずつ消失し、この「散茶女郎」が格上げされ、最高位となりました。

これが後に「花魁」と呼ばれるようになったのです。
「端女郎」の上が「太夫」
それが、「切見世女郎」の上に「端女郎」、その上に「局」「格子」「太夫」が続き、最終的には上位の「太夫」と「格子」「散茶女郎」の位にいた者が「花魁」と呼ばれるようになりました。
更には、「散茶女郎」が「花魁」となってもその後にも階級が定められました。

階級は3つに分けられています。
「呼出し」「昼三」「付廻し」という遊女です。さらにこの下には、「座敷待ち」「部屋待ち」「局」がおり、花魁は「付廻し」までの遊女を言います。
呼び出された花魁は、少女を従え、花魁道中を行います。これらの呼び名は時代によって、また、京都や大阪、長崎といった地域によっても階級の分け方や呼び名も異なっていたのです。
遊女の最高位は「太夫」

「太夫」は、美貌はもちろん、教養を身に付けており、位が高い存在でした。
現代で言う、女優やタレント、モデルといった者を組み合わせた存在が「太夫」であったと言えます。
また、「太夫」は江戸時代にはそう呼ばれなくなり、いつしか「花魁」という呼び名に変わりました。
「花魁」の名前と位のご紹介
- 昼三(ちゅうさん)
- 座敷侍(ざしきもち)
- 部屋待(へやもち)
昼三は、一晩最低13万円~という高額ぶり。座敷侍は、一晩5万円前後、部屋侍は一晩2万5千円~といった説があります。
新造(しんぞう)は下級遊女で、雑用を引きうける立場でした。この時点ではまだ客は取れない状況だったようです。
かむろは、10歳前後の女の子が花魁の雑用をしながら遊女としてのしつけを学び、後、15歳になれば新造としてつき、いずれは客を取るような立場となっていきます。
50年振りに誕生した現代の太夫

京都の島原の太夫として50年振りに太夫が誕生しました。
2014年京都の島原で芸子として最高位となる太夫がデビューし、京都市左京区下鴨神社で奉納道中が行われました。2歳8ヵ月で太夫の世話役である「かむろ」となり、12歳で見習い「振袖太夫」となりました。
その後、島原の文化、そしてしきたりを踏襲し、幼少期は着物などを習い、5歳からは日本舞踊を習い始めたそうです。彼女は「葵太夫」と命名された27歳の女性です。
まとめ
いかがでしたか?花魁と太夫、夜鷹の違い、また、花魁の名前と位について解説しました。
ここで言う花魁と太夫は同等の扱い、同等の位であり、いずれ太夫という呼び名がなくなり、花魁に統一されたことが分かりますね。
その為、一晩のお相手も、花魁、太夫ともに高額であることに変わりなく、花魁じたいにも階級の設定があることが分かりました。
一方で夜鷹は花魁や太夫とは正反対の階級であり、身売りも安く、梅毒になることも多々あったようです。江戸時代という日本の昔には、遊女にもこのような位の幅があったのですね。
幼少の頃から教養を受けた者だけが花魁となれる・・・生まれ育った環境と言えるものですね。
花魁の服装に関する記事