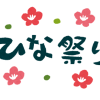- 折り紙の日はいつ?折り紙は脳にも効果的?
- 雨の6月は折り紙を楽しもう!季節のカエルを作る方法!
- ずっと残る!折り紙で綺麗なあじさいを作る方法!
- あじさいにはカタツムリ!簡単な折り方!
- 折り紙を子供と上手に楽しむコツと作った折り紙の活用法!
6月、雨の季節が近づくとお部屋で遊ぶ日も増えますよね。
そんな時、折り紙で6月ならではの季節を感じさせる折り紙遊びも楽しいものです。
そこで今回は、6月ならではのカエルやあじさいなどを折り紙で作る方法をご紹介します。
折り紙の日はいつ?折り紙は脳にも効果的?
6月と言えば、思いつくのはジメジメした雨ですが、6月はその雨のおかげで様々な生命が活発に動きます。
- カエル
- カタツムリ
- あじさい
- スイレン
このように、雨と共に思い浮かぶ植物や生物を見ると、”梅雨だなぁ”と感じますよね。
6月4日は虫の日
また、6月4日は「虫の日」である事をご存知でしょうか。
これは、故・手塚治虫さん達によって設立された「日本昆虫クラブ」が虫の住める街づくりを目指して提唱し、制定された記念日です。

様々な”○○の日”がありますね。
もちろん、語呂合わせによって決められた虫の日ですが、6月の梅雨は私達にとっては少し憂鬱ですがカエルやカタツムリ、そして植物にとっては恵の雨なんですね。
折り紙の日はいつ?
ちなみに、折り紙の日は11月11日です。
これは、日本折紙協会が「世界平和記念日」であることと、”1″という数字を4つ組み合わせると折紙の形である正方形になることから、この日を折り紙の日に制定したと言われています。
また、おりがみの楽しさや教育的な効果などを、より多くの人に知ってもらうことを目的とし制定されたとも言われています。
折り紙は脳トレーニングにも効果的
さらに、折り紙は簡単なものも多いですが上級者向けとしては、花、飛行機、動物など昔からある折り紙だけでなく、もっと本格的なアート作品にすることができるのも折り紙の魅力です。
そうして、手先を使い細かな作業を繰り返し、出来上がった形を想像していく事で脳をしっかりと動かす事ができるので、折り紙は小さい子供だけでなく老人ホームなどのプログラムでも取り入れられているのです。
空間認識能力もアップ
さらに、何気なく紙を折るだけの作業と思いきや、脳の中では”今折っているこの部分がはどの部分になるのかな”と無意識に考えてることで、”どこがどうなる”といったまだ出来上がっていない空間像を自然と思いうかべますよね。
そうすることで、空間認識能力が成長するといわれています。
特に、成長段階の子どもに折り紙をさせると、遊び感覚で脳の成長を促すことができるます。
もちろん、子供だけでなく認知症防止などにも繋がるため、折り紙は良い効果を様々な人にもたらしてくれると言えるのです。
雨の6月は折り紙を楽しもう!季節のカエルを作る方法!
6月になると、草むらから聞こえてくるのはカエルの”ゲロゲロ”という鳴き声ですよね。
この声が聞こえてくると、梅雨を感じると共に雨の日の合唱のようで楽しい気持ちになりますね。
では、さっそくカエルの折り方をご紹介していきましょう。
ぴょんぴょん跳ねるカエル
カエルの頭を作る
折り紙を裏面(白)にして、縦横にそれぞれ折り横に折った紙を戻したらさらに、真ん中の線まで折り戻します。
次に、左右からそれぞれ三角に折り目をつけてまた戻しましょう。
そうすると、先ほど折った横線に沿って指を入れていくと三角形ができますね。
カエルの足部分を作る
次にもう半分の紙も半分まで折り、今度は紙を戻さず左右を真ん中まで下りましょう。

三角屋根の家のような形になりますね。
そしたら下の長方形を半分に折り、折った紙を内側に折ると小さい三角形が出来上がります。
その小さな三角形を横に開いていくと台形を反転させたような形になりますが、さらに左右の角を下に向けて折りましょう。
ジャンプする部分を作る
次に、上の三角形の端を外側に向けて上に折り、先ほど下に向けて折った部分も外側に向けて下に折りましょう。
そしたら、それを真ん中で半分に折りたたみ、たたんだ方をさらに半分折り返してひっくり返すとぴょんぴょん飛ぶカエルの出来上がりです。
ぴょんぴょん跳ねるカエル②
胴体を作る
紙を裏面(白)にし、縦横に一度ずつ折り開いたら、真ん中の中心に向けてそれぞれの四つ角を内側に折り、小さな正方形が出来たらそれを三角形に折りたたみます。
三角形に折ったら、長い方の1辺が下にくるように置きその両角を内側に折り元に戻します。
次に、開いた両角をそれぞれ逆の線まで深く折り込みクセ付けます。
例えば、右の角は先ほど折った左の線まで折り、左の角は右の線まで折るとイメージですね。

そうすると計5本の線が出来ます。
ジャンプ足を作る
次に、左右をそれぞれ外側から二番目の線までまた折り、出た先を縦の線に合わせて折り返します。
そしたら、上の角だけが残った状態となり、長方形になっている部分を内側に半分に折おり、折った紙を更に外側に向けて半分に折り返しましょう。
顔を作る
裏面にすると、カエルの形が出来上がってきますが、最後に尖った部分に指を入れて少し口のように整えましょう。
そして、マーカーで顔を書いたらカエルの出来上がりです。
ぱくぱくカエル
顔のベースを作る
折り紙を表面(色)にして、縦横にそれぞれ一度ずつ折り開き真ん中の線まで折って観音開きの長方形をつくります。
開いている方を下に向け裏返し、さらに縦向きにして上下を真ん中の線まで折ります。

正方形ができましたね。
口と仕上げを作る
次に、また裏返して四つ角をそれぞれ真ん中まで内側に折り、より小さな正方形を作ったら一度開いて半分に折ります。
次に、ひらひらとしている部分をそれぞれ外側に開くと表面(色)が出てきますね。
最後に、目・鼻・足を好きなようにマーカーで書いていくと、口がぱくぱく開いたカエルの出来上がりです。
ずっと残る!折り紙で綺麗なあじさいを作る方法!
6月を代表する花と言えば、あじさいですよね。
雨の中、凛と咲く姿はとても美しいものです。
では、そんなあじさいを折り紙で折る方法をご紹介しましょう。
子供でも簡単あじさい
用意する折り紙は、以下の2種類だけです。
- グリーンの折り紙(大)
- 好きな色の折り紙(小)
花びらを作る
まずは、折り紙を表面(色)にして三角形を2回折り×の折れ線を作ったら、そのまま更にもう一度三角形を折ります。
次に、三角形の口を開いてたたみ正方形になるようにします。
続いて、完全に閉じている角を下に向けてその部分を少し折り、軸を作っていきます。
その軸を持ちながら開いている方を外側に平べったく開いて、花の形を作っていきます。

花が多いと華やかになりますね。
葉を作り花を貼る
次に、大きな折り紙を裏面(白)にして対角線上の角をそれぞれ内側に少し折り、表面(色)にすると葉っぱの様な形が出来上がります。
先程、作った花の裏面(白)に軽くのり付けし、葉っぱの好きな部分に貼り付けましょう。
立体的な花びらが簡単なあじさい②
https://youtu.be/_gBOKCvVAtc
花びらを作る
こちらでは、折り紙を表面(色)にして縦横斜めに一回ずつ折り、斜めに折ったまま両サイドを入れ込む様にすると、最初にご紹介した正方形の形になります。
また、閉じている角を少しだけ折り三角形を作るところまでは同じですが、そこから一度折り紙を開きさっき折った部分を内側に折り混んでたたみます。
たたんだら、2枚の折り紙のうち上の左端を軽く折り、右側を左に倒して同じように折ります。

下の折り紙も同じ流れで折りましょう。
さらに、折り紙の口を開いていくと四角の花が出来上がりますが、裏に返すと先程折った部分が四ヶ所あるので、それぞれを左に倒すように折ると花びらの丸みが出来上がりますね。
最後に、それぞれの花びらの先端を指で滑らせて丸めカールさせたら、あじさいの花の出来上がりです。
あじさいの葉の作り方
https://youtu.be/Lmh08cFitjU
あじさいに欠かせない葉っぱてすが、実はとても簡単にできてしまいます。
まず、折り紙を表面(色にして)三角形に折ったら、先端をそれぞれ外側に少し折りましょう。

逆三角形ができますね。
次に、右端から裏・表・裏と左端に向け交互に折ったら、紙を三角形の状態に戻し下を少し斜め上に向けて折ります。
さらに、三角形の上の部分を逆三角形に折っていた両サイドをそれぞれ八の字に折り、紙を開くと綺麗な葉脈のついた葉っぱが出来上がります。
簡単あじさい
花を作る
折り紙を表面(色)にし、折り紙縦横に一度ずつ折り、更にそれを半分に折って戻しその半分までまた折ります。
その状態で、折り紙を一度開いたら今度は縦向きにして折り紙を半分に折り、更にそれを半分に折って戻しその半分までまた折ります。
それを開くと、花びらのベースが出来上がりますが、より花びららしくする為に裏返し重なった部分を立てて開きつぶしていくと、丸みのある花が出来上がります。
葉っぱに関しては、先ほどの葉っぱの作り方とほとんど変わりませんので、そちらを参考にしてみてください。
あじさいにはカタツムリ!簡単な折り方!
最後に、あじさいと一緒に思い浮かぶ6月のイメージと言えばカタツムリですよね。
あじさいを作った横に、カタツムリも置くとより季節の雰囲気が出ます。
【初級編】カタツムリ
折り紙を裏面(白)にして、三角形に折り、右角と真ん中の角を合わせるように折ります。
更に、右のラインに沿って折り先端が少し紙から出た状態にします。
今度は、裏返して右側を上向きに折り真ん中の先端と下をそれぞれ内側に折りましょう。
最後に、ハサミで右先をカットし目を作りマーカーで渦巻を書いたら出来上がりです。
【中級編】カタツムリ
カタツムリの渦巻をつくる
折り紙を裏面(白)にして、半分に折り逆方向からも半分に折ったら、今度は折り紙を表面(色)にして三角形にを上下左右に一度ずつ折ります。
次に、折り紙を裏面(白)にして対角線状の角を真ん中まで互いに折ります。
そして、両サイドを折り込むように内側にたたむと、色のついた面とついていない面が上上下に分かれた状態となるので、折り紙を左にめくり全て表面(色)が見えるようにしましょう。
頭と足を作る
次に、真ん中の折れ線まで左右を内側に折って裏面も折り、また左側にそれぞれめくります。

下に裏面(白)が伸びている状態です。
まずは、左に伸びている裏面(白)を横向きに折り、先端を軽く曲げましょう。
次に、右側をまた左に向けてめくり伸びている裏面(白)を上に向けて半分に折ります。
そして折った部分を半分にたたみながら右に伸ばし、めくった部分を右に戻して行きます。
最後にマーカーで渦巻を書いたらカタツムリの出来上がりです。
折り紙を子供と上手に楽しむコツと作った折り紙の活用法!
それでは、今回ご紹介したような折り紙を小さな子供と一緒に楽しむためにちょっとしたコツもご紹介しましょう。
- 完成図を見せて意欲を掻き立てよう
- まずは簡単な折り方から始めよう
- 綺麗に折るかより楽しさを大事にしよう
完成図を見せて意欲を掻き立てよう
子供と一緒に折り紙をする際は、まずはじめに完成した形を見せてあげる事をおすすめします。
なぜなら、子供はすぐに飽きてしまうからです。
だからこそ、はじめに折り紙でどんな素敵なものができるかを見せて惹きつけておくとスムーズです。
子供は目で見て触って興味を持つ
もちろん、子供が考えていく想像力も大切ですがまずは一枚の折り紙がこんなにも素敵な花や可愛い生き物に変化する完成形を見せる事で、子供は興味を持ち飽きずに最後までやり遂げる事ができるようになります。
また、完成したものを触ってもらい”こんなにすごいものが折り紙でできるんだ”と、手にすることでより興味持つ事ができます。
まずは簡単な折り方から始めよう
折り紙の折り方は、人によっても違ったりさらに自分でアレンジできたりと楽しみ方は様々です。
しかし、初めから難しい折り方にチャレンジし失敗してしまうと”面白い”という感覚が無くなってしまいます。
だからこそ、最初は簡単な折り方を教えて徐々にレベルアップさせていきましょう。
まずは二つ折りから
だからこそ、まずは二つ折りで三角形や長方形を作ったりして、基本の折り方を覚えてもらうようにしましょう。
折り紙は、基本的な折り方を繰り返す事で一つの形を作り上げる事ができるものです。
だからこそ、基本の折り方を覚える事は大事な事なのでゆっくり進めていきましょう。
綺麗に折るかより楽しさを大事にしよう
折り紙は、丁寧に正確に折る事で完成度も高くなるので、つい教えるにも熱が入り過ぎてしまいます。
しかし、大事な事は綺麗に作る事よりも楽しんでできるかどうかです。
だからこそ、極端に言えば少しくらい失敗しても自分が作ったことを楽しく感じることができれば良いのです。
折り紙の色や折りたいものを子供に選ばせよう
では、子供はどのような事が楽しく感じるかと言えば、折り紙の色を選べたりすることも楽しさの一つです。
例えば、カエルだからといって緑色でなくてもよく、赤いカエルやオレンジのカエルでも良いですよね。
そういった選択肢をたくさん子供に与えてあげることで、子供は自分で選んだものや自分で作ったものに愛着が湧き”楽しい”と思うのです。
だからこそ、綺麗にできるかよりも子供が楽しんでいるか、どうすれば楽しくなるかに注目して折り紙を折ると良いでしょう。
作った折り紙はどうする?
では、最後にせっかく作った折り紙をどうすれば良いか迷ってしまう事がありますよね。
一生懸命作った折り紙を、ただそのまま置いておくのはもったいないので、ここでは折り紙の上手な保存方法をご紹介します。
糸でつないでモビールにする
折り紙で作成したものは、テーブルなど触れやすいところに置いておくとすぐにへ垂れてしまいます。
だからこそ、千羽鶴を繋ぐように折り紙を糸でつないで、何本かつくりそれをフックなどで壁に掛けると、オシャレなインテリアになりますね。
ゆらゆらと揺れるので、楽しいインテリアになります。
ポストカードにする
開くタイプのポストカードを用意しましょう。
そこの片面に、作った紫陽花やカエルの折り紙をノリで貼り付け、反対側にメッセージを書いて大切な人に贈りましょう。
手作り感たっぷりのポストカードをもらった人は、一生大事にしたくなるのではないでしょうか。
ファイルにしてコンパクトにする
写真などを張り付けたりできる、スクラッチブックやポケットになっているアルバム入れなどに、作った折り紙を保存してみましょう。
そうすれば、折り紙を綺麗なままさらにコンパクトに保存することができます。
このように、せっかく作った折紙を活用し、より楽しめるように工夫しましょう。
さいごに
いかがでしたか。今回は、折り紙で6月らしい季節の植物や生物を作る方法をご紹介せました。
このように、折り方次第では雰囲気が変わり違って見えたり、より凝ったものが出来上がったりと折り紙の世界は奥が深く楽しいですね。
だからこそ、子供や作る人のレベルに合わせて折り紙を楽しんで折り季節を感じてみるのも良いですよね。
また、子供達に最後まで飽きずに楽しめる工夫もプラスしてみると良いと思います。

ぜひ、参考にしてみて下さい。
折り紙・折り方についての記事
- 6月の折り紙アイデア!
- 七夕の折り紙・飾りの折り方!
- 七夕飾りの作り方!天の川・くす玉
- 父の日には折り紙をプレゼント!
- 七夕飾りの折り紙での作り方10選!
- 紫陽花の折り紙!簡単な折り方
- 鯉のぼりのかわいい折り紙!
- ひな祭り・折り紙の折り方!