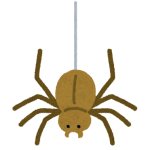- ほうれん草をあげるときは注意点をしっかり守ろう
- ほうれん草の消化にかかる時間は?
- どんなほうれん草を選んだらいいの?
- ほうれん草アレルギーってある?
赤ちゃんは、生後5〜6ヵ月頃になると、ママからの母乳だけではなく、食べ物からも栄養を摂取する時期を迎えます。
離乳食初期は、まだ赤ちゃんにとってはママの母乳やミルクの味しか知らない為、離乳食がうまく進まないという赤ちゃんもたくさんいます。
そんな中でも、離乳食として赤ちゃんに与える野菜の中にほうれん草があります。
ほうれん草は赤ちゃんの離乳食にも適していると言われていますが、実際には赤ちゃんにはいつ頃から与えても良いのでしょうか?
ここでは、赤ちゃんにほうれん草を与えても良い時期や、ほうれん草を消化する時間はどれくらい必要なのかについて解説していきたいと思います。
ほうれん草をあげるときは
注意点をしっかり守ろう
赤ちゃんは、生後5〜6ヵ月頃になると、ママの母乳やミルク以外に、食べ物から栄養を摂取していくようになります。

それが離乳食の始まりです。
ほうれん草はあげるときに注意すること
ほうれん草は、一般的に生後5〜6ヵ月となる赤ちゃんの離乳食初期頃から食べても良い野菜として知られています。

ですが、赤ちゃんにほうれん草を与える際は、調理方法に少し注意する必要があります。
- ほうれん草の茎はあげない
- 茹でた後はしばらく水にさらすこと
- くたくたに茹でてすりつぶしてあげる
このようなことに注意することが大切です。
まず、ほうれん草の葉の部分は茹でるとすぐに柔らかくなりますが、茎が混入しないように茹でましょう。
ほうれん草の茎部分は、繊維がしっかりとしていて茹でてもまだ歯が生えていない赤ちゃんにとって食べることが難しい為です。

また、ほうれん草からは少しアクが出る為、茹でている時にアクを取り、茹で上がったあとはしばらく水にさらしておくようにしてください。
もしも赤ちゃんに与える場合は、くたくたに茹で、その後すり鉢で完全にすり潰せば離乳食として使用することができます。
裏ごしすればおかゆにも混ぜてあげることだってできますよ。
もう少し月齢が進んだ離乳食中期頃であれば、おひたしにしたり、和え物などで与えることができます。
ほうれん草の栄養素
ほうれん草にはどんな栄養素があるのか見ていきましょう。
- 葉酸
- カリウム
- カルシウム
- ビタミンA・B1・B2・B6・C・E・K)
- マグネシウム
- 鉄分
- モリブデン
ほうれん草には、これらのような栄養素が含まれています。
鉄分や葉酸が含まれていることはよく知られていますが、それ以外でも野菜の中でもとても多くの栄養素を含んでいることが分かります。
また、便秘解消効果として食物繊維も豊富に含まれている為、便秘がちな赤ちゃんには、上手にほうれん草を離乳食に混ぜて与えると良いでしょう。
ほうれん草の消化にかかる時間は?

赤ちゃんの離乳食の際、ほうれん草を与えることは何ら問題ないことがわかりました。
しかし、そのほうれん草が消化に悪いという考えがあるようですが、実際のところどうなのでしょうか?
時間をかけてじっくり茹でて!
適量をあげることも大切
ほうれん草などの野菜類は、一度食べてから消化されるまでに約1〜2時間かかると言われています。

特に赤ちゃんは、胃腸器官の発達が未熟である為、それよりもまだ少し時間がかかると思ってください。
それでも、茹で時間をしっかりととり、クタクタになるまで茹でた後におかゆなどに混ぜて与える為、しっかりと時間をかければきちんと消化され、排泄物の中に排泄されます。
その為、離乳食に与えるには特に問題のない野菜であると言えます。
とは言え、どんな食べ物にも言えることですが、食べすぎ、食べさせ過ぎは消化不良を起こしてしまいます。
ほうれん草をあげるときは、適度な量を赤ちゃんに与えるようにしましょう。
どんなほうれん草を選んだらいいの?
赤ちゃんの離乳食にほうれん草を与える場合は、そのものをしっかりと吟味する必要があります。
最近では、離乳食として使用することができるよう、とても便利にほうれん草をペースト状にしているものが販売されている為、イメージとしてはとても安全性が高いと思いますよね。
ほうれん草選びのポイント

日本で販売されているほうれん草についてはほぼ国内産となります。
国産というと安全性も高く安心もできるので、赤ちゃんの離乳食を作る際に、ほうれん草を使用するママも多いと思います。
ですが、厚生労働省が「クロチアニジン」と呼ばれる農薬の残留基準を緩和させたため、それらの農薬を散布したほうれん草がスーパーで販売されている可能性は十分考えられます。
となると、やはり赤ちゃんに離乳食として与えることに抵抗を感じる方も少なくありません。
その為、赤ちゃんには安全性の高いほうれん草を与えるべきであることから、以下の点に注意してほうれん草を選ぶようにしてください。
どんなに良いほうれん草を選んだとしても、ほうれん草を離乳食に使用する際は、茹で時間をしっかりと取って、えぐみを取り除く必要があることは忘れずに調理してくださいね。
冷凍ほうれん草は購入しない
最近では、手軽に利用できたり、天候によって野菜の価格高騰が続いたときに購入しやすいなどという理由から、冷凍ほうれん草が活躍した時がありました。

確かに、冷凍のままで調理することができる為、手軽であることは確かです。
しかし、これらのほうれん草は、残留農薬が残っているタイプとなる為、赤ちゃんにはおすすめできません。
できれば避けていただくとともに、他の方法でほうれん草を購入するようにしてください。
生産者が分かる野菜を購入する
スーパーで販売されている野菜コーナーに、生産性が高く、より安全性を重視した野菜を販売するという意味で、農家直接のコーナーなどを設けて野菜を販売するスーパーが増えています。
また、道の駅などでも多くの野菜が販売されています。
このような場所で販売されている野菜は、生産者の名前が記載されている為、どのような方法で栽培されているかを細かく記載してくれている場合もあります。
その為、購入する私たちにとってはとてもありがたく、生産者が分かるという点ではとても安心して食べることができるという訳です。
無農薬や低農薬野菜を購入する
赤ちゃんが食べる野菜には特に気を遣う必要があります。
そして、いちばん気になるのは農薬を使っているか、いないかという点だと思います。
可能な限り「無農薬」や「低農薬」と表記された野菜を購入したいですね。
ほうれん草アレルギーってある?
離乳食をあげるときに、素材選びも重要ですが、アレルギーについてもとても気になるところだと思います。
初めての食べ物をあげるとき、アレルギーはないか体調は悪くならないか、ちょっとヒヤヒヤしながらあげたことがあるママさんもいることでしょう。
では、ほうれん草でアレルギー症状が出ることはあるのでしょうか?
ほうれん草のアレルギーは比較的少ない?
ほうれん草については、「アレルギーになりやすい食品」には該当していないため、食物アレルギーは少ない食材であると言えます。

しかし、少ないというだけで、全く問題のない野菜であると言い切ることはできません。
実際のところ、少ないながらも、ほうれん草アレルギーである方は存在するようです。
ほうれん草アレルギーはどんな症状が出る?
ほうれん草は、比較的アレルギーの少ない食材と言われてはいますが、まれにほうれん草でアレルギーを起こす場合もあります。
これは口腔アレルギー症候群と言われる病状であり、食べたことで口の中や口の周りが赤く腫れてしまうことを指します。
- 口の中や口の周りが赤く腫れてしまう
- 手足や体に蕁麻疹などの発疹が現れる
- 目のかゆみ
- 鼻水
- 喉のかゆみや痛み、腫れ
- 喘息
- ひどい場合は下痢や嘔吐
症状の出かたには個人差はあるものの、これらの症状が現れることがあります。
おかしいと思ったらすぐに病院へ行くこと
先ほどお話した症状からすると、「花粉症」や「食中毒」のような症状にも思えてしまいます。
その為、食事を摂取してから数時間、数日経過しているような場合は、アレルギー症状であることが判断しにくい場合があります。
もしも、赤ちゃんにほうれん草を与えて、アレルギーのような症状が出たり、体調に変化があった場合は、すぐに小児科又はアレルギー科を受診するようにしましょう。
ほうれん草はしっかり加熱調理をすること
ほうれん草はヒユ科ほうれん草属の野菜に属しています。
ほうれん草アレルギーはそこまで知られていないアレルギーではありますが、まったくアレルギーが起こらないというわけではありません。

また、ほうれん草は加熱調理済みのものよりも、生の方がアレルギー反応が起こりいやすいそうです。
赤ちゃんにほうれん草を与えるという場合は、必ず加熱調理を行うことが大切です。
まとめ
いかがでしたか?
ほうれん草が消化される時間や赤ちゃんの離乳食に最適であるかについて解説しました。

ほうれん草は、とても栄養価の高い野菜であることから、赤ちゃんの離乳食にはとても良いことが分かりました。
また、ほうれん草は野菜であることから、一旦口にすると、消化までに約1〜2時間必要となります。
これは一般的な時間であり、赤ちゃんとなれば、まだ大人とは違って胃腸器官が未発達であることから、もう少し消化に時間を要することになります。
それでも、栄養価が高い為、ぜひ、赤ちゃんの離乳食にはすすんで利用したい野菜になりますね。
しかし、どんな食べ物でも、食べすぎ、食べさせ過ぎは、下痢などの原因につながります。
その為、適度な量を赤ちゃんにたべさせてあげてくださいね。
消化についての記事