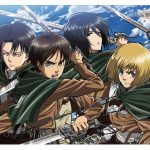- きのこが胞子を飛ばすその仕組みって?
- きのこの胞子を飛ばす仕組が活用されている
- きのこの胞子の体への影響は?
私たちはさまざまな「きのこ」と呼ばれるものを日々食していますが,よくよく考えるときのこって不思議な生き物ではないでしょうか。
今回はきのこが胞子を飛ばす仕組みとそれにまつわるエトセトラをご紹介します。
きのこが胞子を飛ばす仕組み
https://youtu.be/VGpof-F1YQs

風に乗って飛んでいくの?
昔、きのこは可能な限りの多くの胞子を作り出すだけの単純な生き物と思われていました。
きのこの胞子がどこまでと多く広がるかは、気まぐれな風次第だと思われていたのです。
しかし研究が進むにつれて、非常に複雑な仕組みが見えてきました。
ヒダのあるきのこ・胞子の飛ばし方
しいたけ、ぶなしめじ、えのき、マッシュルームなど、軸がありカサがあり、カサの裏側がヒダになっているきのこは「蒸発冷却」を利用して胞子を飛ばします。
ヒダに形成される胞子表面に付着する水滴を利用して、胞子をできるだけ遠くまで飛散させることができます。
胞子は風にも乗りやすい構造をしていて、風も利用してより遠くまで胞子をとばしていると考えられます。
ヒダをもたないきのこ・胞子の飛ばし方
https://youtu.be/Fs0cI1eVUAE
ヒダをもたないきのこにホコリタケがあります。
カサを持たない形状の「腹菌類」は、人や動物の力を借りて胞子を飛ばします。
動物に踏まれたり、雨などの物理的刺激で胞子を飛ばします。
他の力を借りて胞子を飛ばす
スッポンタケというきのこは独特の臭いを発して「ハエ」を呼び寄せ、ハエの力を借りて胞子を飛ばします(ハエに運んでもらいます)。
スッポンタケはスッポンの頭の形に似ているからその名前になりました。
スッポンタケの先端についている黒い部分はカサでなく「クレバ」という胞子を形成する器官です。
このクレバには胞子を含んだ液体がついていて悪臭を放ちます。
この悪臭はハエが好む臭いで、ハエを呼び寄せてハエに付着させ胞子を運ばせます。
動物に食べられて胞子を飛ばす
シバフタケやハラタケというきのこがあります。
これらのきのこは牛などの動物に食べられることで胞子の発芽率が高くなります。
動物に食べられることで胞子を拡散(移動)させ、しかも動物の胃袋を通過させることで生存のための胞子の発芽率が高くなるようになっています。
きのこの胞子が飛ぶ仕組みの応用

布団乾燥機はきのこがヒント!?
シャープはきのこが胞子を飛ばす仕組みを利用して布団乾燥機を開発したそうです。
「胞子を飛ばすためにできた形状のきのこのカサは、優れた流体制御装置としての役割もしていて、揚力を発生させて胞子を風にのせて遠くまで飛ばす」。
このような仕組みを利用して、「プラズマクラスターと温風・冷風を遠くまで飛ばす仕組み」を考えたそうです。
布団の中に効率的に温風を広げる仕組みとして、「きのこ」の形状をしたアタッチメント作成。
このきのこ状のアタッチメントが布団の中の温風を通る隙間を作り、さらにそのカサカーブ形状で風の流れを整え遠くまで強い風を届けることでしっかり「乾燥」「あたため」ができるそうです。
きのこの胞子の体への影響

アレルギーとかの原因なの?
きのこの胞子を吸い込むことにより、慢性の咳、発熱、息切れ、喘息、過敏性肺炎を起こす場合があるといわれています。
特に職業として室内できのこ栽培を行っていて、継続的にきのこの胞子に長期的に暴露する人に見られます。
また、カナダなどの森林の多い地域ではきのこの多くが該当する担子菌類の胞子が空中真菌フローラに30%以上含まれているという報告もあります。
そしてきのこ栽培者でない方にも発症が見られるようです。
きのこに対する反応例
きのこによる発症例としていくつかの報告があります。
マツタケ
8歳女児
気管支喘息とアトピー性皮膚炎
マツタケづくし料理を食べて1時間後に呼吸困難、嘔吐、顔面と四肢の浮腫
18歳女性
毎年春に鼻炎症状の自覚あり
職場の宴会でマツタケご飯を食べた翌朝、残ったマツタケご飯をおにぎりにして食べた20分後から咳、顔面浮腫が出現。1時間後に全身の蕁麻疹、意識低下を伴ふアナフィラキシーに進展。
しいたけ
しいたけの胞子を長期吸引することでの慢性の咳、喘息症状誘発、肺炎になるなどの例があります。
他の真菌やエンドトキシンによる影響の可能性もあるようです。
しいたけのほかに、ぶなしめじ、なめこ、エリンギにも同様の報告が見られます。
ヒラタケ
喘息の既往がある17歳女性
ヒラタケを摂取後10分以内にのどのかゆみ、呼吸困難、蕁麻疹が出現。
エノキタケ
17歳女性
エノキタケによる既往なく普通に摂取
摂取して1時間後に目、耳のかゆみ、全身蕁麻疹、呼吸苦。
このようにきのこに対して突然アレルギーのような反応を起こすことがあるようです。
しかしきのこへのアレルギーにおいては、アレルゲンが明らかになっていない面が多く、原因が判明していない症例も多いようです。
きのこの生態

きのこって植物?
動物でも植物でもない「第三の生物」とまで言われる「きのこ」には驚きの秘密がいっぱいあるそうです。
昔きのこは葉緑素を持たない下等な植物とされていましたが、今はきのこは菌類に分類されます。
きのこはカビや納豆菌と同じで菌類なんです。
菌類は地球上のあらゆる場所で活動しすごい働きをしています。
きのこは自然界では森の中でひっそりと暮らす小さな生き物ですが、地下の世界ではネットワークを張り巡らせ、地球上の植物の生育に大きく貢献しています。
加えて、地球上の物質環境において「分解者」となって極めて重要な役割を担っているのです。
そして人間の健康維持にとっても医食同源の食材としてなくてはならに存在となっています。
いろんな菌類がある中で、胞子を撒くために子実体を作るものを特に「きのこ」と呼びます。
私たちが食べている部分が子実体です。
きのこの子実体は多種多様で、その形状に合わせて胞子の撒き方も多種多様になっています。
まとめ
きのこの胞子の飛び方にはいろいろな飛び方があります。
風にのせて飛ばすのも運任せというわけではなく、ちゃんとカサとヒダで胞子を飛ばす仕組みができていたり、虫や動物の力を借りたりと、科学的でもあり神秘的でもあります。
そんな仕組みが電化製品に応用されているのも興味深いですね。
アレルギーに関してはよくわからない点も多く心配ですが、でも美味しいきのこですからいろいろ食べたいものです。
きのこに関する記事