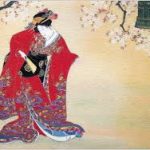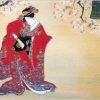- 上杉謙信の家紋にはどんな意味や由来があるの?
- 毘沙門天とはどんな関係だった?
上杉謙信と言えば、日本の歴史的人物の一人です。
しかも、上杉謙信は「長尾家」の出身であるにも関わらず、名前を上杉と名乗っています。
どうして一般人のような上杉謙信が、天皇家の家紋を使用できるのか疑問です。
ここでは、上杉謙信の家紋の由来と意味、そして、毘沙門天との関係についてご紹介したいと思います。
上杉謙信の家紋にはどんな意味や由来があるの?
上杉謙信の家紋について知る前に、上杉謙信についておさらいしておきましょう。
上杉謙信とはどんな人?
上杉謙信は、上杉家の家臣である「長尾為景」の子供として誕生しました。
実際のところ、名字が異なることから想像できるよう、上杉謙信は上杉家の子供として生まれた訳ではく、長尾家の四男として生まれたのです。
上杉謙信はお寺で奉公していた
上杉謙信は、生まれた時に「長尾虎千代」と名付けられました。
しかし、四男であることから、長尾家を継ぐ必要がなく、小さい頃お寺で奉公していたのです。
その後、謙信は何事もなければこのままお坊さんになっていたと思います。
その後、謙信の運命が変わりました。
謙信が15歳になったころ、長尾家は3つに分家しました。
そして、15歳で初陣を踏み、見事勝利したのです。
長尾家を継いだ謙信の兄である晴景は、身体が弱く、鎮圧させることができず、その時に引き出されたのが謙信です。
謙信は敵を攻め、初陣を勝利し、この快挙が広く知れ渡るようになったのです。
そして、家臣である黒田秀忠の謀反により、兄が殺害され、そのりごの国を鎮めるため、謙信は兵を挙げたのです。
長尾家の家臣、黒田秀忠が謀反を起こし、謙信の兄を殺害します。
この事態を受け、謙信は晴景のところへ戻り、黒田家を攻めました。
二度も裏切られた上杉謙信は、裏切りを図った黒田家のこが許せずに、兄と共謀し、黒田家を滅ぼしたのです。
その後、謙信は子供のいない晴景の養子となることになりました。
謙信が19歳の時、長尾家の当主として、越後の将より歓迎され、5年後に領主として地位を確固たるものとしたのです。
謙信は山内上杉家の家督を継ぎ、「上杉政虎」と名乗り始めるのです。
これが1561年の頃で、この時から「上杉」の名字を名乗るようになり、足利義輝より「輝」の一字を授かり、「上杉輝虎」と言う名を名乗るようになりました。
このようなことから「上杉謙信」は本名ではなく、法名として名付けられたことが分かります。
法名は、仏門に入った際にもらえる名前のことです。
謙信は、1560年に入道し、その際、「謙信」という法名が付けられているのです。
実名としては「上杉輝虎」になりますが、やはり歴史上の有名な人物であることから、「上杉謙信」に馴染みがあると言えます。
武田信玄との戦い
https://www.youtube.com/watch?v=PKw31ZEY-2M
上杉謙信の最大のライバルは武田信玄です。
実に5回に渡る「川中島の戦い」を行っているのです。
「布施の戦い」
布施の戦いは、武田信玄が信濃に攻めに入ったことから始まりました。
信濃の武将は、武田信玄に領地を取られたことに対し、領地の返還を求めました。
しかし、上杉謙信は、領地をとる理由がない為返還を承諾しました。
それでも、武田信玄は領地の返還を行おうとしなかった為に、1回目の川中島の戦いが始まりました。
この戦いでは、上杉謙信が、武田信玄らを攻撃し、その後、反撃にあいます。
その後、武田信玄らも上杉謙信らも帰国したというのです。
「犀川の戦い」
布施の戦いから2年後、再度両者の戦いが始まりました。
この時、今川義元の仲介で両軍が共に撤退しています。
「川中島の戦い」
3回目、1557年に川中島の戦いが始まります。
この戦いでも、今川義元の仲介で両軍が共に撤退しています。
「激化する川中島の戦い」
そして、4回目、川中島の戦いが起こり、この戦いがとても激しく、両軍とも多くの損害を出し、家臣が亡くなっています。
それでも両者の決着はついておらず、前半は上杉謙信側が勝利を得ています。
そして後半は武田信玄側が勝利を得たと言われているのです。
しかし、この川中島の戦いにより、武田信玄の弟の武田信繋が命を落としました。
歴史上に残る甲陽軍艦によると、上杉謙信と武田信玄の一騎打ちを行ったという事実が残っているそうです。
「決着がつかない川中島の戦い」
5回目に行われた川中島の戦いでは、両者の決着がつかずに武田信玄が亡くなり、戦いは引き分けのまま終わってしまいました。
上杉謙信の家紋の由来と意味について
上杉謙信は「竹に二羽飛び雀」が有名です。
謙信の家紋は「上杉笹」と呼ばれています。
謙信は上杉家の家紋を受取っている人物です。
天皇家から受けた「五七桐」の家紋
上杉謙信は「五七桐」の家紋を持っています。
この家紋は歴史上とても有名で、天皇家の象徴でもあります。

上杉謙信が五七の桐を使用できるのはなぜでしょう?
これは、謙信が19歳で家督を継ぎました。そして、このことを朝廷に報告したのです。
謙信は報告を行うとともに、直接お礼を言うことを望んでいたと言います。
しかし、この時代は、直接天皇に会えるようなことは容易ではありませんでした。
戦国時代であったこともあり、道中に敵陣に遭遇する確率も高いながらも、きちんと朝廷に報告すべく、上洛を決意したと言います。
上杉謙信と毘沙門天との関係について
上杉謙信は、自分自身は毘沙門天の生まれ変わりであると信じており、戦の神と言われる毘沙門天が自分の前世であると考えていました、
また、上杉謙信は、自分は戦国時代における最強の武将であると確信していた為、毘沙門天と自分が同じであると思っていたようです。
上杉謙信は合戦を得意としていた
上杉謙信は、幼少の頃から乱暴者であり、強かったと言われています。
14歳の時に武将して初陣を勝利し、それ以降、越後国内を駆け回った結果、負けを知らない戦いを続けてきたのです。
謙信の父である為景が死去した後は、越後の国民は、謙信の勇敢な生きざまを見て、謙信を高い地位に就かせる動きが出てきました。
そして、謙信は多くの国民からも認められ、家督を継ぐ立場となったのです。
戦いは勝利を飾り続けたものの、領土は広がることなく、戦いに勝利して領土を手に入れたとしても、すぐに取り返されるなどを繰り返し行っていたのです。
これは、越後にて兵農分離がなされていないことが原因であったと言われているのです。戦に勝利して領土を手にいれても、農繁期に国へ帰ることで領土を取り返されてしまいます。
自身を毘沙門天の生まれかわりであると信じ、戦いを続けていったのです。
上杉謙信の家紋について
@senpatirou ちなみに忠宗公期(慶安5年頃)に製作された瑞巌寺仏間の唐戸にも「横しない三引両紋」と「初期の竹に雀紋」がセットで使用されていますね。 #瑞巌寺 #伊達忠宗 #家紋 #三引両 #竹に雀 pic.twitter.com/LVdWU0k0gW
— 伊左大夫 (@0524Isataifu) May 18, 2013
上杉家の家紋は、「竹に飛び雀」であり、これは、後に文様化されています。
仙台の伊達氏が同じ「竹に飛び雀」の紋を使用し、これはそもそも上杉氏より譲り受けたものだと言われています。
しかし、伊達氏の家紋は文様化していないようです。
この紋は代表紋であり、勧修寺龍の家では、この「竹に飛び雀」の紋を使用しています。
この紋は、関東から各地へ広がり、どれも上杉氏から贈られたそうです。
まとめ
いかがでしたか?上杉謙信の家紋の由来と意味について、また、毘沙門天との関係について解説していきました。
上杉謙信が用いた家紋については、どれも謙信が戦い抜き、授かったものであることが分かりました。
謙信の家紋を見る限り、どれほど謙信が勇敢な武将であり、忠義を貫こうとする人間であったかを理解することができます。
戦国時代を生きた最もかっこ良い武将ではないでしょうか。
家紋や歴史についての記事