- もし、夫が癌になったら?癌の治療は高額なの?
- 生活保護どうやったら受けられる?条件や金額は?
夫がもし癌になったら。。。ショックも当然あるでしょうが、治療費や生活費など、現実的な悩みが確実に増えますよね。
また、治療を続けていくうえでさまざまな問題が起きて、離婚を考える方もいるでしょう。
離婚してからの生活に悩み、生活保護を考える方もいるかもしれません。
夫が癌になったら?癌の治療は高額?
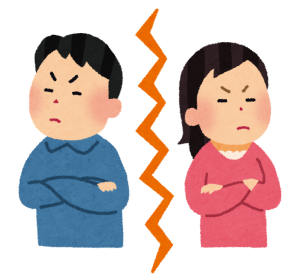
長年連れ添っている夫婦でも、まだそれほど長くない夫婦でも、もし、夫が癌になったら、まずはじめになにを思うでしょうか?
愛する夫のため、家族が一丸となって支えていこうと思う方が多いのではないかと思う反面、中には『離婚』を考えてしまう方もいるかもしれません。
癌の治療費はどのくらいかかる?

癌の治療は、どんな治療を受けるかによって、費用は大きく変わってきます。
- 手術
- 化学療法
- 放射線治療
癌の治療法はこの3つだけではありませんが、この三大治療は健康保険が適用される癌の治療法となっています。
これらのほかにも、自由診療となる治療法はとてもたくさんの種類があり、癌の種類へのアプローチもさまざまなので、費用も当然違ってきます。
また、医療保険のCMなどでも耳にすることの多い、先進医療という高度の医療技術を用いた治療もあります。
- 手術:約30~130万円
- 化学療法:約100万円
- 放射線治療:約60万円
【保険適用】健康保険+高額療養費制度
- 先進医療:約数百万円~1,000万円以上
【保険適用】健康保険適用外
これらは、標準的な治療法のおおよその費用になりますが、それでもかなりの費用がかかることになります。
癌の治療は時間がかかる!収入面でも問題が
手術を受ける場合には、体への負担が少ない内視鏡手術が増えてきているとはいえ、一般的な手術であっても、2~3週間くらいの入院は必要になります。
化学療法や放射線治療は、通院でも受けることはできますが、治療そのものに時間もかかる、そして、継続的に治療する必要があります。
治療費以外にかかるお金も、入院時に必要な身の回りのものの購入や通院の際の交通費など、多くの費用がかかってしまうということになります。
そして、出ていく費用が多いのもそうですが、入院中や治療を受けるときには仕事ができなくなってしまうため、その分収入が減ってしまうことも頭に入れておくとよいでしょう。
病気になったことや治療を続けていかなければいけませんし、精神的なショックも大きいと思います。
それに加えて、収入源が夫の稼ぎのみとなる場合、癌の治療に関わる費用だけでなく、生活費も考えなければいけなくなるので、お金への不安も大きくなってしまうことも考えられますね。
癌で離婚は特別なことではない
夫や妻が癌になって、より一層絆が深まったという夫婦もいるでしょう。ですが、癌が原因で離婚したという夫婦は、特別なことではありません。
どんなに思いが強い夫婦だとしても、経済面への心配やストレスによって、結果離婚を選択したという夫婦も。
中には、夫や妻に負担をかけたくないといった理由から離婚を選んだという夫婦もいました。
生活保護どうやったら受けられる?条件や金額は?

離婚する理由も生活保護を受ける理由も、人それぞれ理由がありますね。
さまざまな理由はさておき、つぎは生活保護のお話をしていこうと思います。
国や自治体が、経済的に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うこと。
最低限の生活を保障して、自立を助長する制度のこと。
収入などが足りない場合、条件が満たされれば、その足りない分を補って支給してくれる制度のことです。
生活保護を受けられる条件とは?

生活保護の条件は基本的に3つあります。
これは、世帯単位の扱いになるので、一人暮らしの場合はその一人が条件を満たしていればOK。
ですが、家族と同居している場合となると、その家族全員が条件を満たしていないと生活保護を受けることはできません。
- 預貯金、土地や家屋、車などの財産がないこと
- 生活を維持していける収入(最低生活費)がないこと
- 親族などからの援助がいないこと
では、一つずつ詳しくお話していきましょう。
預貯金、土地や家屋、車などの財産がないこと
お金になるような資産や財産があるのなら、それを処分して生活費にあてることができますよね。
あとになって資産があることがわかった場合も、申請を受け付けてもらえません。
ですが、車を持てる条件を満たしていれば、車を持っていても生活保護を受けられる場合もあります。
また、生命保険がある場合はダメといわれているのですが、次のような生命保険の場合、生活保護を受けられる場合もあります。
- 死亡や障害のための対策を目的とする保険
- 掛け捨て型の保険
- 貯蓄的な意味合いの薄い保険
- 解約返戻金があっても、30万円未満の場合(保有が認められることがある)
生活保護を受ける際、生命保険に関しては細かい取り決めがあります。
生活を維持しいていける収入(最低生活費)がないこと
収入があったとしても、最低生活費に足りていない場合、その分が保護費として受け取ることができます。
親族などからの援助がないこと
身内や縁者などに援助をお願いしてもそれができない場合。
申請があると、福祉事務所は、申請者の身内や縁者に対して、援助をするように依頼をしたり調査をすることになります。
借金があったら生活保護は受けられないの?
生活保護の申請時に借金がある場合でも、生活保護を受けることはできます。
ですが、借金の額が多い場合は、生活保護の受給後に自己破産を指導されることもあります。
生活保護の種類

生活保護には、8つの扶助があり、そのほかに必要に応じて支給される一部扶助があります。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 正業扶助
- 葬祭扶助
これらは、国で定められた基準によって、世帯の生活に応じて補助が支給されることになります。
医療扶助と介護扶助に関しては、医療機関や介護事業者などに委託して行う現物給付のため直接給付はありませんが、そのほかの扶助は原則として金銭給付となっています。
生活扶助
日常生活に必要となる費用のこと。
- 食費
- 被服費
- 光熱水費 など
住宅扶助
共益費を除く、住宅の家賃や地代として支払う費用のこと。
教育扶助
学校教材や学用品など、教育に必要な費用のこと。
医療扶助
診療や治療費、薬代など、医療サービスを受ける際の費用のこと。
介助扶助
要介護もしくは要支援と認定された人が対象となる、介護サービスに伴う費用。
出産扶助
出産に伴う費用。
生業扶助
生業費用や技能修得費用のこと。
生業に必要な資金や、器具や資材などを購入する費用、または、就労に必要な技能を修得するための費用。
生活保護の支給額はどのくらい?
ひとくちに生活保護といっても、実は住んでいる地域や世帯数によっても異なります。
世帯に障害者がいる家庭や母子家庭などは、障害加算や母子加算といって、最低生活費以外に加算されて支給されます。
生活保護の支給額の平均は?
先ほどお話したように、地域や世帯数によっても支給額は異なります。
だいたいの目安としてお話しますが、大人2人子供1人の3人世帯で約160,000円、子供2人いる母子家庭では約150,000円となっています。















