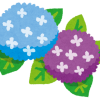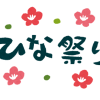- 端午の節句はいつから始まった?今でもやるもの?
- 端午の節句!兜は誰が買うべき?準備するものとは?
- 両親へのお礼はどうする?内祝いは必要?
- 端午の節句をお祝いしよう!お祝いのながれ
- 端午の節句における疑問を解決!
5月5日は、男の子の誕生を家族でお祝いする『端午の節句』です。
この日は、庭先に大きな鯉のぼりを飾り、家には兜を飾り家族や親戚が集まる華やかな一日となりますよね。
しかし、この兜は誰が用意するものなのでしょうか。
今回は、そんな素朴な疑問から端午の節句のお祝い方法までご紹介したいと思います。
端午の節句はいつから始まった?今でもやるもの?
今の時代、5月5日は『こどもの日』と呼ばれています。
ゴールデンウィークに重なるこの日は、子供達が主役のお休みで特に男の子がいる家庭にとっては、鯉のぼりや兜を揃え大きなイベントの日とするところも多いですよね。
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する

上記の意味がこめられています。
また、こどもの日は1948年に制定されたもので、それまでは『端午の節句』という呼ばれ方が一般的でした。
端午の節句の由来
端午の節句は奈良時代から始まり、平安時代には病気や災厄から身を守る大切な貴族の行事として執り行われていたと言われています。
平安時代の貴族の間では、こうしたしきたりがいくつかありました。
- 人日(1月7日)
- 上巳(3月3日)
- 端午(5月5日)
- 七夕(7月7日)
- 重陽(9月9日)
このような季節の節目に、体調や災厄から身を守る為の行事が決まっていて、それが貴族だけでなく民間にも広がっていた一つが端午の節句なのです。
端午の節句はなぜ5月5日?
端午(たんご)とは、「月の端(はじめ)の午(うま)の日」という意味です。
午の月(5月)の最初の午の日は5月5日とは限りませんでしたが、奇数月で同じ数字の重なる日を吉日と考えていた事から、5月5日が端午の節句をお祝いする日になったと言われています。
また、端午の節句を一般家庭でも祝うようになったのは鎌倉時代と言われています。
さらに、兜などの五月人形が一般家庭に普及するのは明治時代以後のことです。
端午の節句!兜は誰が買うべき?準備するものとは?
では、そんな端午の節句はどんな準備が必要で誰が用意をするのでしょうか。
端午の節句のアイテム
そんな、端午の節句に欠かせないものは以下のものです。
- 鯉のぼり
- 兜(かぶと)
- 鎧(よろい)
- 吊るし飾り
- 人形
このように、男の子が強く逞しく成長することを願う日であるので、武士をイメージさせるアイテムが多いですね。
また、菖蒲(しょうぶ)を浮かべて入る『菖蒲湯』の風習があるとことも多いです。
池、川などに生える多年生の草本で単子葉植物の一種
中国では古来より、ショウブの形が刀に似ていることと、邪気を祓うような爽やかな香りを持つことから、男子にとって縁起の良い植物とされていた
菖蒲は、端午の節句の季節になるとスーパーやお花屋さん、ネットなどで購入できます。
- 菖蒲を10本ほど用意する
- 浴槽に水を張るまえに菖蒲を入れて42~43度の熱めのお湯をはり香りを出す。
- 少し冷ましてから湯に浸かる
子供が入った後は、家族で楽しんでも血行促進や保湿効果があるのでおすすめです。
いつまでに用意する?
兜や鎧などの五月人形は、“4月後半から用意すれば良い”と考えている人も多いですよね。
しかし、兜や鎧などは大量生産ができない、いわゆる手作りです。
だからこそ、人気のものはすでに完売になっている事も多いのです。

3月中には用意をしておきましょう
特に3月3日の雛祭りが終わった後は、端午の節句に向けて店頭もネットなどでも忙しくなります。
そのタイミングに、端午の節句に必要なものを早めに準備し始めておくと良いですね。
いつから飾る?
端午の節句の飾り付けは、『内飾り』と『外飾り』に分けられます。
初節句では3月20日の春分の日を過ぎた辺りから、五月人形のような内飾りはを飾り始めます。
鯉のぼりなど、家の外に飾るものは4月上旬あたりから飾ります。
また、直前や当日に五月人形を飾るのは『一夜飾り』と呼ばれ、あまり縁起が良くありませんので、3月くらいから準備を始める事がおすすめです。
いくらくらいする?
端午の節句をどのようにするかは、家庭によって違います。

どのくらいが平均的でしょうか。
- 鎧飾り: 15万~30万円
- 兜飾り: 10万~20万円
- 武者飾り: 10万~15万円
このような価格帯が、だいたいの目安となります。

意外と高価です。
また、ネットなどではもう少しリーズナブルな価格もあります。
誰が買うもの?
では、そんな兜は誰が用意する事が多いのでしょうか。
パターンとしては以下の4つに別れる事が多いようです。
- 母方の実家(父母)が購入する
- 父方の実家(義理の両親)
- 互いの両親が折半
- 自分たちで購入
また、地域によって様々ですが、正式には母親の実家から五月人形・こいのぼりなど贈るのが正式なかたちとされています。
しかし、そういうかたちは正直どちらかに負担が掛かってしまい、関係が悪化してしまう事も多いです。
何より、父方の両親もお祝いに参加したいと思う事が多く、ほとんどが話し合いではありますが、両家でバランスよく行うのがベストです。
一方で、両家で行うと意見を合わせていくのも一つのポイントです。
- 価格
- お祝いの規模
このようなポイントが合えば良いですが、意外と合わないのも現実です。
しかし、せっかくのお祝いの日の事で険悪な雰囲気にはしたくないものですね。

だからこそ、担当を分けてみるのもおすすめです。
雛祭りと端午の節句で分ける
3月3日は女の子の日で雛人形を、5月5日は男の子の日で五月人形や鎧や兜を贈るのが一般的です。
だからこそ、男女どちらの子供もいる家庭では3月3日の女の子の日を母方の両親が購入し、5月5日の男の子の日を父方の両親が購入するというスタイルが多いとも言われていますね。
また、五月人形などの飾り物は1人に一体を贈るのが良しとされています。
だからこそ、長男次男で両家の担当を分けたりする家庭もありますね。
贈り物と会を設ける側で分ける
また、基本的にお祝いを頂いた側が、お祝いを送った方を節句祝いの会食に招きおもてなしをするというのが一般的です。
だからこそ、兜などの飾りを買うのが母方の両親であれば、お祝いの席は父方の両親が持つなどバランスをとってみるのも一つです。
端午の節句でなくともお祝いはできる
また、端午の節句だけでなくこれから小学校などに入学し、ランドセルなども必要になってきます。
だからこそ、端午の節句をどちらかがやる事に拘るのではなく、それであれば次のランドセルの時にお願いするなど、こちらも話し合いがベストです。
両親へのお礼はどうする?内祝いは必要?


また、お祝いを頂いた人への内祝いはどうするのでしょうか。
両親へのお礼は?
基本的には、家や外食先などおもてなしをするのが一般的な両親に対するお祝いのお返しとなります。
だからこそ、改まって内祝いの品物など用意していなくても良いです。
一方、それでも義理の両親の場合、高額な兜や5月人形などの飾りや鯉のぼりなどのプレゼントが多いで、お礼を改めてしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
だからこそ、お土産に何か記念になる品物を構えていても良いですね。
金額
その際のお礼ですが、金額は頂いた品物の半額〜3分の一が良いとされています。
つまり、兜などが5万円相当のものであれば、2万円〜2.5万くらいでお返しという事になります。
ただ、両親としては孫を思う気持ちからお祝いをしているので、そこまで高価なものでなく5千円前後でも気持ちが伝われば金額は関係ないと言えますね。
お返しの時期
お祝いの品が、五月人形や兜などの飾りの場合、5月5日の約1ヶ月前には贈られている場合が多いですよね。
届いたら、すぐにお礼状だけは送っておきましょう。
電話でも良いのですが、きちんと自筆で書かれた手紙の方が好印象です。
最近は、連絡をLINEなどを使い行う人も多いですが、LINEやメールの場合はその後に手紙でお礼状を出す事が望ましいでしょう。
お返しの品
では、お返しの品はどんなものが良いでしょうか。
- 子供の名前入り日本茶セット
- 写真入り お米
- カタログギフト
- ホテルスープセット
- 甘酒セット
お返しを選ぶポイントは、相手が“こんな高価なものを貰っては”と負担にならないものがおすすめです。
また、子供の名前や写真を入れることのできるギフトは、離れている両親などにも喜ばれます。
さらに、スープや健康飲料でも推奨されている甘酒など、両親の身体に優しく日持ちのするギフトも良いですね。
特に、カタログギフトなどは金額を設定でき、好きなアイテムを選んでもらえることからスマートで人気を集めています。
頂いたものと子供の写真を添えること
また、お返しの品と共に忘れてはいけないのは、頂いた物と子供が一緒に写ったし写真ですね。
例えば、兜の横に映る孫の写真を綺麗なフォトフレームと一緒に贈ってもらえれば、それ以上に嬉しいお返しはないといえます。
端午の節句には誰を呼ぶ?
また端午の節句ですが、家族だけでシンプルに行う家庭も増えていますね。
しかし、せっかくなのでたくさんの人に、子供の成長をお披露目する絶好のチャンスでもあるのです。
だからこそ、以下の範囲で節句祝いの会に招くのも良いでしょう。
- 両家の祖父母
- 親戚
- 名付け親や仲人
- 初節句祝い・出産祝いを送ってくれた人
このように、基本的には親族をメインに呼びお祝いを行います。
端午の節句のお祝い返し
また、お祝いの会に出席してくれた人々に、お祝い返しか必要かも悩むところです。
基本的に、おもてなしがお祝い返しとなるので別途、お返しの品物を用意する必要はありません。
一方、やむおえない理由で出席できなかった人へは、節句から1週間以内にお返しをする事がマナーです。

どんなに遅くてもその月中にはお返ししてください。
お返しの金額
お返しは基本的に頂いた物の、半額以下の金額で相手との関係によって選ぶと良いでしょう。
熨斗
その際の熨斗は、表書きで『内祝』または『初節句内祝い』とし子供の名前でお返しをします。

名前のみで苗字はいりません。
また、熨斗は水引で紅白の蝶結びです。
お返しの品
また、お返しの品は基本的に紅白の砂糖菓子やその他お菓子が一般的です。
名前入りのカステラも人気です。

鰹節やタオルなどもおすすめです。
端午の節句をお祝いしよう!お祝いのながれ

では、具体的に端午の節句のながれをまとめてみましょう。
端午の節句ながれ1:内飾り&外飾りを飾る
まずは、3月中旬あたりから兜や鎧などの内飾りを出し準備をします。4月に入ったら、鯉のぼりなどを出しましょう。
しかし、最近の住宅事情から外ではなく鯉のぼりの飾りなどを家の中で用意する場合は、内飾りと一緒のタイミングで飾っても良いでしょう。
端午の節句ながれ2:お礼と招待状を済ませる
まずは、兜などの飾りを用意してくれた両親や義理の両親に、きちんとお礼の手紙を送っておきましょう。
また、お祝いの席をこの時にはどうするか決めておき、一緒に招待状を兼ねて送っておくのも良いですね。
端午の節句ながれ3:お祝いの会を開く
お祝いの会は、家でも外でもどちらでも良いです。
しかし、せっかくであれば贈ってもらった兜や鎧などの五月人形の元で、お祝いをしたいものですね。
- ちまき(柏餅でもOK)
- 赤飯・ちらし寿司
- たけのこ
- 鯛
- 蓮
- 豆
上記をテーブルに並べます。

どれも、縁起の良いものとされているものですね。
この他にも、出世魚とされるブリ・スズキなどを用意しても良いでしょう。
また、初節句の子供や他子様用にケーキやゼリーなども用意しておきましょう。
端午の節句ながれ4:菖蒲湯に入る
菖蒲湯に入るタイミングは、5月5日の夜が良いでしょう。5月4日に菖蒲を枕にして寝ます。
そして、5月5日にはその枕を解き、それを湯に浮かべた菖蒲湯するのが一般的です。
お祝いの席が終わった夜に、菖蒲湯に入りましょう。
端午の節句ながれ5:お返しを贈る
5月5日が過ぎたら、1週間以内にお返しを贈りましょう。
ここまでが、端午の節句における一連のながれといえます。
端午の節句における疑問を解決!
そんな端午の節句には、まだまだ分からない事も多いので端午の節句におけるよくある質問をまとめてみました。
- 兜はどうやって飾るの?
- 兜はいつしまうもの?
- なぜちまきと笹餅なの?
端午の節句における疑問1.兜はどうやって飾るの?
では、兜の正しい飾り方をご紹介します。
まず、兜には刀と弓があるのでその置き方に迷いますよね。
基本のかたちは、向かって左側に弓、右側に太刀を飾ります。
また、その刀と弓にはそれぞれ意味があります。
刀の意味
刀は三種の神器の一つでもあります。
- 鏡
- 玉
- 剣(刀)
特に、刀には古くから『魂が宿る』とされています。
そのため、昔から神事には必ずと言っていいほど使用されていたと言われています。
つまり、『刀に宿っている魂が子を守り繁栄をもたらす』という意味から、兜と共に飾られるのがただしい理由です。
また、飾る時は鞘(さや)を上にして、手で握る方を下にして飾ります。
このように、”魔物は光り物を嫌う“というされている事から、災いから守ってくれる物として用意されているわけで、決して戦う為のものではないのです。
弓の意味
長い弓には『神様が降りてきて宿る』と言われています。

初詣でも、破魔矢を買いますよね。
その他、邪気を祓う為矢を射る流鏑馬(やぶさめ)のような儀式もあります。
また、魔物や鬼などは弓を引いた際の弦の音を嫌うとされていていますので、こちらも刀と同じく攻撃をするものとしてではなく、魔除けの意味が込められているのです。
このような意味を知り、正しく飾りましょう。
端午の節句における疑問2:兜はいつしまうもの?
兜を出す時期は大体わかりましたが、しまうタイミングがわからないという人も多いです。
基本的に兜や鯉のぼりは、端午の節句を過ぎるとあまり意味が無いものとされているので、お祝いの席が終わった翌週末にしまう家庭が多いです。

遅くとも梅雨前にはしまいましょう。
しかし、ひな人形の様に『婚期が遅れる』などという言い伝えも無いので、せっかくの立派な兜や鎧をケースに入れそのまま飾る家庭もあるようです。
大安か友引の日に
また、しまうのであれば縁起を担ぐ意味としても、大安か友引の日にしまうのが一般的です。
さらに、空気が乾いた天気のいい日に片付ければホコリや湿気を取り除き易く、カビも防げるのでいつまでも状態良く保つ事ができおすすめです。
端午の節句における疑問3:なぜちまきと笹餅なの?
男の子が生まれて初めての節句となる『初節句』には“ちまき”を、2年目からは“柏餅”を食べるのが望ましいと言われています。
ちまきの由来
元々、ちまきは中国の食べ物です。
昔、中国国王の側近として働いていた“屈原(くつげん)”という詩人は、陰謀が理由で国を追われ、5月5日に川に身を投げ自らの命を経ちました。
国民に愛されていた屈原(くつげん)に対し、民衆は供養の意味を込めてその川に食べ物など投げ込もうとしましたが、『龍がいる』とされていた中国では食べ物が屈原(くつげん)に届く前に竜に食べられてしまうと思います。
そこで民衆は、龍が苦手とする楝樹(れんじゅ)という葉でもち米を包み、邪気を払う為に5色(赤・青・黄・白・黒)の糸で縛って川に流す事で、屈原(くつげん)に無事届いたとされているのです。
このように、龍をも退ける効果があるちまきを食べることによって、無事に子供の成長を願うことと重ねたのではないかと言われています。
このことから、5月5日にはちまきを供えるようになったのです。
日本のちまきは、もち米を笹の葉で巻いて釜でゆでて作りましたが、今はもち米か、うるちの粉を練って、それを茅(かや)や笹、葦に包んで蒸してつくるのが一般的とされています。
笹餅の由来
柏餅に使われる柏の葉や柏の木は、厳しい冬を乗り越えて次の新芽が出るまで葉が落ちないという特性を持っています。
ここから、『子供が生まれるまで親は死なない=跡継ぎが途絶えない』と考えられるようになり、子孫繁栄の意味を込め食べられるようになったと言われています。
このように、今でこそ少子化ですが家系存続が大切な時代の武家にとって、 柏は大変縁起のいいものだったのです。
こういったながれから江戸を中心に、関東では柏餅を食べるようになったと言われているのです。
さいごに
いかがでしたか。今回は、端午の節句の兜を誰が買うのが良いかなど、端午の節句についての素朴な疑問をご紹介しました。
兜などは、誰が買うかも大事ですが、子供の成長をお祝いする大事な日を気持ちよく迎える事ができる事が何よりです。
だからこそ、準備を早めにしどちらの家が何を用意し、どんな形にしていくか早めに相談しておくのがベストですね。
また、準備にはさまざまなアイテムを用意する必要がありますが、ネットなどでも簡単に用意できたりします。
特に、端午の節句用にまとめてセットになっていたりもするので、そういったものも活用しお祝いするのも良いでしょう。
端午の節句に関する記事