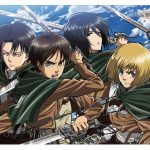- 花魁言葉への変換が人気な言葉10選!
- ありがとう等の挨拶も花魁言葉に変換!
日本の時代劇の中でよく耳にする遊女のセリフに聞き覚えはありませんか?
何だか言葉の語尾にいつも常に特徴があることに気付きませんか?

例えば、「~でありんす」「おいでなんし」など言っていますよね。
これを「ありんす言葉」などと呼んでおり、実際には江戸時代の吉原遊郭の高級遊女が男を接客する際に使用していたというのです。
ここでは、花魁言葉として人気な言葉についていくつかご紹介していきたいと思います。
花魁言葉とは?

花魁言葉とは、別名「廓言葉」と言い、かつて吉原遊郭で遊女が使用していた言葉の全てを指します。
他にも「ありんすことば」「おいらんことば」「さとことば」などと言われることもあります。
もともとは京都の島原だけで使用されていたそうですが、その後、吉原遊郭でも使用されるようになりました。
廓言葉が使用される理由は?

吉原には当時、あらゆる地方から遊女見習いとして女性が多数やってきました。
その女性たちは皆、それぞれの地方訛りな話し方をする為、同じ日本人としても言葉が通ずることがなく、「何を話ししているのかが分からない」「お客が疲れてしまう」といった理由が生じてきたのです。
その為、優艶な廓言葉を使用するようになったと言われています。遊郭は男性客に夢を与えるような場所でした。
その為、男性客は遊女に対して常に、「身分の高い女性であってもらいたい」という思いから、廓言葉は男性客にとって心地よい響きであったのかもしれません。
廓言葉はそのような男性の思いをくむような言葉だったのでしょう。
廓言葉が現代用語として使われてる

遊郭で使用されていた廓言葉の現代用語をいくつかご紹介します。
サル→エテ
客が「去る」ことは、遊郭にとってマイナスでしかありません。その為、良いこととしては捉えられていませんでした。
このようなことから、「去る(さる)」ではなく「エテ(得て)」と表現していました。
スルメ→アタリメ
盗みをすることを「掏る」と表現し、縁起が悪いことから、「スルメ」を「アタリメ」と呼ばれるようになりました。
馴染み
馴染みは現代では「お馴染みのものは~」「お馴染みの種類の~」などといった一般的に使用されることばです。
しかし、遊女の間では、何度も通う男性と親密な関係となる意味を「馴染み」になると表現していました。
お茶を挽く
遊女はお客にお茶葉を挽かされていた為、現在の水商売でも、暇な状態を「お茶を挽く」と表現します。
あがり
これは寿司屋などでもよく耳にするお茶のことを「あがり」と言います。遊郭は、お茶と言う言葉を縁起の悪いものとして捉えていました。
客が来店し、お茶を出す際に「上がり花」と表現しており、縁起の悪いお茶を「あがり」と良い表現をしていたことから、現在も使用される言葉として残っています。
花魁言葉で人気の言葉は?
- ~してくれますか?
→~しておくんなんし - ~ごめんなさい
→ごめんなんし - ~ありがとう
→ありがとうござりんした - ~ではありません
→~ではないでありんす・~ござりんせん・~ありんせん - そうですか
→そうでありんしたか - ~ですか?
→~ありんすか?
その他にも遊女の言葉にはどんなものがある?
よく、昭和のお金持ちの奥様が口にしていたイメージの「~ざます」も元は遊女が使用していた言葉だそうです。
今ではドラえもんのスネオのママがこんな言葉使いになっていますよね(笑)
- ~ではおっせん
→~ではありません - ~なんざんす?
→~なんでございますの? - そうざいます
→そうでございます
自分のことを言う
「です」→「ざんす」の使い方も非常に使いやすくなっています。
- お楽しみざんす(お楽しみです)
- どこざんすえ(どこにいますか)
- ほんざんす(本当です)
- うれしうざんす(うれしいです)
- ようざんす(結構です)
- 気がつまりんす(気がつまります)
- 気にかかりんす(気にかかります)
- この夏からでんして(この夏からでまして)
- ほんでござんす(本当でございます)
- そんな事ござんすか(そんな事あるものか)
- お入りなんし(お入りください)
- きなんすよう(来ますよう)
- 見なんし(見てください)
- いいなんすな(言わないでください)
- おくんなんし(ください)
- しなんす(します)
- あらっしゃる(ある)
- おっせえす(おっしゃいます)
- おあんあんせんかえ(おがなりなさいませんか)
などといったような法則で、江戸の口語として自由に使用することができます。
吉原の中で特別に使用される言葉
- 主(ぬし)
客や、尊敬する人物のことを言うときに使う。 - 塩次郎
うぬぼれが強い人に対して言う言葉のこと。 - 武左
「むさ」と発音し、武者=武士の客に限らず、常にいばっている客のこと。 - 七夕
「たなばた」と読むが、バタバタ足音がうるさく歩く客のこと。 - おゆかり様
お馴染みの客のこと。 - さし
花魁に事情があって会いたくない客のこと。 - もてる
吉原では「遊女に丁寧にもてなされる」ことで、これが転じ、「モテる」というの意味の言葉が生まれたそうです。
共通語にはどんなものが?
共通語は、遊女が属しているお店ごとに言葉が違うということも多く、遊女たちの言葉を解説するような書物までもがこの時代に刊行されていたというのです。
その中でも作家 山東京伝による傾城訛りについて、江戸時代当時の吉原遊郭を代表する遊女屋であった「松葉屋」「丁子屋」「角玉屋」「扇屋」の遊女だけが使用する方言が解説されているといいます。
その中でも「松葉屋」の遊女については、「~でございます」を、「~おす」と表現していました。また、「来ぃした(来ました)」「しのびをこめる(密かにする)」など、京都弁に近い響きの言葉が多いと言われています。
「丁字屋」の遊女については、「~でございます」ではなく「~ざんす」といった表現に、また、「どうともしなんし(あなたの好きなように)」という意味で使用されていました。全体的に艶っぽい表現の多い言葉です。
「角玉屋」の遊女は、個性的な言葉が多く、よく多用されていた言葉が「あきれけぇる」といったその通りの意味で、「あきれる」という表現です。
他にもモテることを「ぼちぼちね」と、そしてフラれることを「ちゃきちゃき」と表現していたようです。まさに江戸時代の下町的な響きに聞こえます。
「扇屋」の遊女については、「ほんだんすかえ」という言葉を相づちとしてよく使用していました。
そして、現代の日本の若者は、口癖のように「やばい!」という言葉使いがなされています。これは、「きさんじなもんだね」という表現で、「ダメだね」といった意味でもあります。
まとめ
いかがでしたか?花魁言葉で人気な言葉や定番の言葉についてご紹介しました。
まさか、今の時代にそこまでの花魁言葉を使用する場面があるか!?となると実際には必要性がないと感じる方の方が多いかもしれません。
しかし、古き良き言葉で、末尾の響きが女性らしく感じたり、その地ならでは当時の様子がうかがえるかのような雰囲気のある言葉は、受け継ぎたい気もしますね。
実際に京都では、花魁言葉に近い言葉が今もなお使用されているようです。これらの言葉使いは日本独特のものであり、実用性は薄いものの、時代を経て知っておくのも良いかもしれませんね。
また、関西の高級遊女は、実は関西弁で接客していたのだとか!?だからこそ、江戸時代の吉原遊郭の独特な文化が「ありんす言葉」だったようですよ。
花魁の服装に関する記事
花魁になりきりたいなら?
花魁風のセクシーな着物はレンタルして気軽に試すことができます。
生地や作り込みの品質もピンキリですから、興味があれば ぜひチェックしてみてください!