- 神道で葬儀をする場合、どのくらい費用がかかるの?
- 神道の葬儀はどんな流れで行う?
- 葬儀の服装や挨拶のマナーは?
日本には、神社とお寺が存在します。
日本で行われる葬儀の大半は仏式であることが多く、それが一般的であるとされていることから、神道での葬儀についての常識についてはあまり知られていないようです。
そこで、ここでは全国各地にある神社において、神道の宗教に基づいた、神式でのお葬式を行う際の一般常識についてご紹介したいと思います。
神道の葬儀の費用と流れは?特別なマナーはある?
神道とは?仏教との違いはある?
神道は、日本における宗教です。
古来、日本人が生活を送る中で根付きました。
神道と仏教にはどのような違いがあるか

仏教との違いについてチェックしてみましょう。
仏教は、インドの釈迦が開祖し、実際に日本に伝わったのは飛鳥時代であると記されています。
仏教は、釈迦が説いた教えとなる「経典」をもととしています。
それにより、教義や戒律が定められており、神道には特にこだわった決まりなどは存在しません。
神道は、いつか御霊を神に返すものという考えを持っています。
そして、神道のお葬式を行う際は、故人を守護神とする為、儀式を行います。
それが「遷霊祭」というものであり、故人の霊魂を霊璽に移し、葬場祭で故人を家の中の守護神として祀るのです。
神道の葬儀は「御霊移し」と呼ぶ

これは「御霊移し」とも呼ばれています。
神式の葬儀については、自宅または斎場を借りて行うことが多いです。
神道の葬儀はこのように行われる
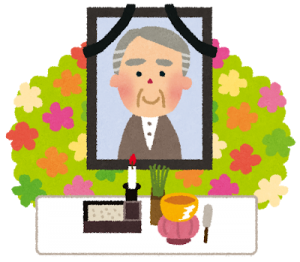
神道の葬儀の際、故人との最期の別れを行うのが「葬場祭」と言い、通夜祭は前日に自宅でとり行われています。
神葬祭とは
神道によって行われる葬儀を「神葬祭」と呼びます。
神葬祭において、人が亡くなると、神社の神職が執り行うことになります。

ここで、神道と仏式による葬儀は異なる点が多いです。
仏式においては、亡くなられた故人は極楽浄土へ見送るという考えのもと行われる葬儀です。
一方で、神葬祭は、亡くなられた故人の御霊を、各家に留め、今後は家の守護神として家族を守る立場となってもらうための儀式となるのです。
神葬祭においては、仏式のようなお焼香を行うといったことがなく、これと同等のものが玉串奉奠と呼ばれる儀式を行います。
- 玉串とは、榊の枝に紙垂が付いたものを指します。
- 玉串を捧げたら、二拝二拍手一拝でお参りをします。
- 五十日祭までの拍手についてはそっと手を合わせるのみとなります。
神道においては、人が亡くなることは穢れであると考えられていることから、神の鎮まる聖域となる神社で葬儀が行われることはごく稀です。
葬儀自体は、故人宅または斎場を借りて行うことがほとんどです。
神道でいう「穢れ」は、「不潔」「不浄」という意味だけではありません。
「気枯れ」を「けがれ」と認識されているのです。
神葬祭全体の流れ
①帰幽奉告
そして、神棚の前に白紙を下げることになります。
②枕直しの儀
故人が好んでいた食べ物など、お供えものをしてください。
③納棺の儀
棺に蓋をし、白い布(薄いピンクの布)で覆い、参列者全員で拝礼してください。
④通夜祭
神道による通夜祭は、仏式の通夜と同等のものとなります。
遷霊祭は、故人の御霊を霊璽に留める儀式となります。
⑤葬場祭
故人との最期の別れを告げる神葬祭の重儀とされています。
⑥火葬祭
火葬祭は、故人の遺体を火葬する前に、火葬場において行う儀式となります。
神職が祭詞を奏上し、遺族は玉串を奉って拝礼を行います。
⑦埋葬祭
昔は火葬場から遺骨を墓地へ移し、即日に埋葬を行っていました。
しかし、近年においては、仏式と同様、いったん故人の遺骨は自宅へ帰り、忌明けとなる五十日祭で埋葬される傾向になっています。
⑧帰家祭
直会は、葬儀でお世話になった神職の方や、お世話をして下さった方に対し、お礼の意味を込めて宴を開催し、おもてなしをすることです。
ここまでが神葬祭の全体の流れとなります。
神道での埋葬の法要について

神道において出棺する際は「出棺祭」を行います。
出棺祭は、かつては自宅から斎場へ向かう際に行われていました。
現在は、斎場祭と一緒に行われます。
仏教で言う、初七日の法要を葬儀の際に一緒に行うことと同様です。
故人の名前を記す旗である銘旗、遺影、花、玉串、神饌を棺とともに霊柩車にて火葬場まで運びます。そして、火葬祭を行います。
棺を炉の前にご安置し、お供え物を備えます。斎主が祭詞奏上を行い、その後、参列者一同が拝礼し、玉串奉奠を行います。
火葬を終えた後は、仏式と同様に骨上げを行います。
神式において、昔は火葬後の遺骨はすぐに埋葬されることとなっていました。
近年においては、仏式と同様、一旦遺骨は自宅へ持ち帰り、五十日祭までは祭壇にご安置されることとなっています。
骨上げを終えた後、すぐに埋葬する場合でも、遺骨をいったん自宅へ持ち帰るにしても、帰宅後には「帰家祭」を行います。
葬儀に参列した方々は、玄関で手水により身を清め、塩をかけ、神官のお祓いを受けた後、自宅に入ってください。
帰家祭を行った後、仮の御霊舎に霊璽、遺骨、遺影を飾ってください。

お祓いや神前にお供えものをします。
帰家祭を終えた後は、斎場祭を手伝って下さった方々へ向けて直会を行います。
お葬式での作法やマナーは?

神式は、仏式において行う通夜にあたる通夜祭、お葬式にあたる斎場祭といったような、それぞれの儀式をとり行う前には、必ず「手水の儀」を行うことが一般的です。
これによりまずは身を清めてから儀式が始まるものと思っておいてください。
この儀式の中において、仏式で行うお焼香が、神式においては、「玉串奉奠」です。
ここでそれぞれの作法について簡単に手順をご説明します。
- 水を汲んだ柄杓を右手に持ち、左手に3回水をかけてください。
- その柄杓を今度は左手に持ち替え、右手にも3回水をかけ、両手を清めてください。
- 左手の手の平に水を受け、その水を口に含んでお口の中を軽くすすいでください。
- そして、最後は左手に再度水をかけて懐紙で口と手を拭いてください。
- 玉串を両手で受け取ったら、まず遺族の方へ向き、一礼してください。
- 玉串を正面に立てて持ち、それを時計回りに回転させます。
- その後、根元が祭壇側になるように置きます。
- 玉串を捧げた後は二礼、手を二拍打ち、一礼します。 「二礼二泊一礼」
- 数歩下がり、遺族に対して一礼して元の位置に戻ります。
神式の香典返しはどのようにすれば良い?

神道においても、香典のやり取りがあります。
神式は、次の供養が五十日祭であることから、香典返しを行う場合はこの日を境に送ると良いでしょう。
神式における香典返しを行う際も、仏式と同様に、必ず丁寧な対応を行うよう、挨拶状を添えておくと良いです。
また、挨拶文の文面に、「成仏」「冥福」「供養」といった仏語の使用は避けてください。
あくまで神式であることを念頭においた挨拶状として仕上げるようにしてください。
神道における葬式費用について
神道のお葬式を行う際に必要となる費用については、家族葬と一般葬で費用は異なります。
神道のお葬式を一般葬にて行った場合の平均相場は30~50万円となっています。
相場に開きがあるのは、葬儀内容や参列者の人数によってもその費用は異なります。
神道の葬儀は斎場でとり行われることがほとんどであり、葬儀会場によって費用も異なることから、できるだけ葬儀費用を安く抑えたいと言う場合は、公営の式場を検討されると良いでしょう。
神式のお葬式のマナーとは
日本における神道の宗教で行うお葬式の流れと、仏教で行うお葬式流れについては、様式や手順が全く異なります。

もちろん、その意味も異なります。
神道の葬式にはどんな意味がある?
仏教は葬式を行う意味としては、故人が極楽浄土で過ごせるよう、また、故人が仏のそばで暮らすことができるよう行われています。
一方で、神式における葬式の神葬祭は、故人は家の中の守護神となる為の儀式であるという、異なる意味で行われています。
また、本来は、仏式で行うお葬式はお寺で行われます。
神葬祭は、神社では行われません。

斎場または自宅にて行われます。
神葬祭でのマナー

葬儀の形式は宗教によって様々なことが異なります。
その形式が異なることによって、葬儀のマナーも注意点もそれぞれ違いがあります。
ここでは、神葬祭においてのマナーをご紹介します。
数珠は使用しないこと
数珠の使用は仏式の葬儀の際、僧侶が読むお経の数を数えることに使用されている為、神道における葬儀の際は数珠は使用しません。
服装は喪服で参列すること
葬儀に参列する際の服装については、特にこの服装でなければならないといったような決まりはなく、仏式で行う葬儀の際に着る喪服を着用しましょう。
男性も女性も、喪服の色は黒に統一してください。
靴下やストッキングも黒です。
バッグや小物類(ハンカチや髪留めなど)も黒で合わせるようにしてください。
特に、女性の場合は小物やバッグ、アクセサリー類については、キラキラとしたような派手なデザインのものやそのような雰囲気のものは身に付けてはいけません。
アクセサリーについては、結婚指輪以外は身につけないようにしてください。
不祝儀袋はどう選ぶ?書き方は?
- 神道の葬儀の際に準備しておく不祝儀袋には、蓮の花が入っていないものを使用。
- 水引は黒白、又は双銀を選らびます。
- 表書きには「御霊前」「御霊串料」となっているものを選びます。
挨拶の際に「冥福」「成仏」「供養」という仏式の言葉の使用は避けてください。
仏教と神道では、「死」の考え方が異なることから、仏教用語となるような言葉の使用はしません。
神道においては、「御霊のご平安をお祈り申し上げます」といったように言葉をかけてください。
神道における葬儀での服装とマナーについて
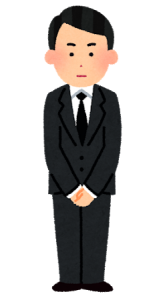
ここで改めて神道における葬儀に参列する際にふさわしい服装を、男性、女性、子供ともに全てご紹介します。
通夜は、略礼服で参列することが常識でもあります。
しかし、大抵の場合は黒を選択する方が大半です。
とは言え、通夜については、急な訃報の知らせであることから、急いでその場へ駆けつける事態でもあることから、すぐに喪服の着用が難しいことも多いかと思います。
その場合でも、光沢感のあるようなスーツは避け、トーンが落ち着いたものを着用するのが常識です。
男性の喪服は

男性が着用する喪服は、礼服用のブラックスーツが一般的です。
この時、ネクタイや靴下の他、靴も全て黒に統一させるようにしてください。
細かい点を指摘すると、ベルトについては革製品は避けてください。
男性には少ないですが、アクセサリー類も結婚指輪以外は身に付けることは避けましょう。
また、男性は通常バックを持たない方の方が多く、それが最もフォーマール的なスタイルとなります。
香典はスーツの内ポケットに入れて準備してください。
財布については普段が長財布など大きめのものを持たれている場合は、葬儀の日だけでは小さめでコンパクトな財布に、必要最低限のものだけを持参するようにしましょう。
もしもバッグを持つ場合は、色は黒でシンプルなデザインのものを持つようにしてください。
女性の喪服

女性の喪服について説明します。
- 黒のフォーマルスーツ又は黒のワンピースを着用
- スカート丈については膝丈か膝下くらいの長めのものを着用する方が良い
- ブラウスの下に着用するインナーは黒
- バッグは光沢感のない合成の革製バッグや黒無地のハンドバッグが最適
- 靴は、ヒールの高さが7cm以下で太めのヒールで安定感のあるものを選ぶ
間違ってもピンヒールなどは派手なイメージを与えてしまうことから、常識的な範囲のものを着用するようにしてください。
髪の毛については、肩より長い場合はゴムでまとめて束ね、ひとつにまとめるなど、シンプルな髪型にしておきましょう。
ヘアアクセサリーなどを付ける場合も色は黒で大人しいデザインのものにしてください。
また、貴金属については、一連の小さなチャームのネックレスのみは着用可能としています。
結婚指輪以外の指輪などは外して葬儀に参列してください。
子供の喪服

葬儀に参列する際に一番悩むのが子供の服装ではないでしょうか。
子供にブラックフォーマルなスーツをお持ちの方は少ないと思います。
その為、学校や幼稚園などで指定された制服がある場合はその制服を着用するようにしてください。
制服は通常、子供の礼服という考え方をしていることから、通夜や葬儀で着用することができます。
もしも制服のない学校や幼稚園である場合は、男の子は黒や紺、グレーなどの色のブレザー、ズボンを着用、女の子は黒や紺、グレーなどのブレザーとスカート、ワンピースなどを着用するようにしてください。
靴はフォーマルな靴があればそれを履くようにしましょう。
もしも手持にない場合は、できるだけ黒系の靴を選んで履くようにしてください。
- ネクタイはきちんと締め、葬儀の間は上着やブレザーは着用したままにすること
- 透け感のあるような素材の服や肌が露出するようなデザインの服は着用しないこと
- 光沢感のある服装とならないよう、素材に気を付けること
- メイクはナチュラルかつ控えめに仕上げること
- ネイルやフレグランスなどを付けることは避けること
- 皮製品の衣類は殺生のイメージとなる為、着用しないこと
- 色が黒であってもカジュアルな服装は避けること
- ベルトや靴にゴールド系の光るような金具がついていないこと
- タイピンやカフスなどは避けること
- 時計は身につけないこと
葬儀という儀式である為、自身の服装に乱れのないよう、終始気を付けなければなりません。
普段の生活の場とは異なる状況であることを考慮し、きちんと常識ある服装を心掛けることが大切です。
喪服を新調する場合は
フォーマルスーツなどをお持ちではない場合は、今後のことも考慮し、必ず1着は持っておくべきものであることから、店舗やネットショッピング等を利用し、購入検討するようにしてください。
最近では、価格帯も随分と低価格化しており、5000円~といった価格で購入することができます。
大きな体型変化がなければ、長く利用することができます。
また、フォーマルスーツじたいに流行りすたりといったことはなく、特に大きな変化は見受けられません。
最近では、ブランド服からフォーマルスーツが登場している為、良いものを長く利用するという考えもあるようです。
急に喪服が必要となった場合

いつ、どこで人が亡くなられるかなど誰にも分かりません。
その為、急な訃報を受けた場合でも、すぐさま駆けつけることができるよう、最近では手軽にフォーマールスーツを購入することができる店舗も増えています。
実際に着用し、その場でサイズ確認をし、その場で丈を直すこともできる為、あなたにぴったりのスーツを選択することができます。
大抵のものを1つの店舗内で揃えることができる為、急な場合は店舗利用で購入するようにしましょう。
今後の準備の為に事前購入ならネット利用も便利
これから喪服も必要となって来るだろうと考えている方は、事前準備可能な時間がある場合は、店舗購入とネット購入を比較することもできます。
ネット購入は実際に着用することができないうえ、写真とイメージが違っていたなどといったことも多々あります。
しかし、手軽なネット購入の方が楽な場合も多いです。
近年においては、喪服を購入するというスタイルから、喪服をレンタルするといったサービスも展開されるようになりました。
もしも未だ購入を検討されている場合は、必用な時にこのような喪服レンタルサービスを利用されてみても良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?神道での葬儀の費用や流れについて、また服装や挨拶など、マナーについてご紹介しました。
神道での葬儀は仏式とはまた様々な点が異なることが分かりました。
共通して注意すべき服装やマナーもありますが、それぞれの宗教に応じた適切な葬儀への対応を行うことが大切です。
ですから、ぜひこの記事を参考にして、一通り 葬儀の流れを把握しておかれると良いと思います。
神道や宗教について















