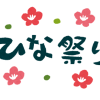- 端午の節句に鯉のぼりは何故あげるの?
- 鯉のぼりの吹流しには意味がある?
- 鯉のぼりの意味や順番は決まっている?
男の子のお子様がいる家庭では、5月5日に鯉のぼりを飾る男の子らしいイベントの日がありますよね。
この鯉のぼり、なぜ飾られるようになったのでしょうか。

鯉のぼりの吹流しは色が全て違いますが、順番や色は関係しているのでしょうか。
今回は、「鯉のぼりって何で色が違うの?」と子どもに聞かれたときに胸を張って教えてあげられるように鯉のぼりについて勉強しておきましょう。
鯉のぼりが飾られる『端午の節句』
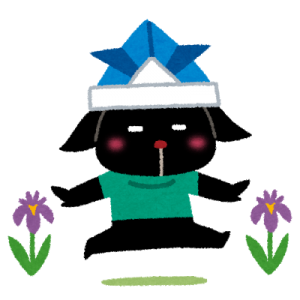

5月5日というと柏餅などを食べる「端午の節句」でもありますね。
端午の節句
- 男の子の成長を祝い、立身出世を祈願してきた伝統的な風習
- 五月人形、鎧兜、鯉のぼりなどを飾り、菖蒲湯に浸かったり、柏餅などを食べる
ゴールデンウィーク中の端午の節句ですが、男の子がいる家庭は鯉のぼりの準備がありますよね。
お家の環境によってはベランダに小さめの鯉のぼりを飾ったり、空を泳ぐような大きな鯉のぼりを上げる家庭もあります。
大きいものになると大人には少々気が重い作業になる場合もありますが、忘れずに用意してあげたいものです。しかし、なぜ鯉のぼりを飾るのでしょうか。
鯉のぼりの由来

鯉のぼりはなぜ飾られるようになったのでしょうか。
もともと端午の節句は古来中国の行事が日本に伝わり、日本独自の風習として根付いたものなのです。
日本で一般的にも定着したのが江戸時代のこと。
当時は庭に立てられていたのが、「武者のぼり」というもので、現在のような鯉のぼりではありませんでした。
「武者のぼり」とは?

武者のぼりの起源は戦国武将の「旗指者」とされています。
時代劇などの戦いのシーンで、家紋のついた旗を掲げていたり、馬に乗った武将が旗を挿して走っているところを見たことがあるのではないでしょうか。
その旗が「旗指者」です。
室町時代末期の武家社会の風習で、端午の節句に家紋が描かれた「旗指物」を虫干しをかねて飾る
↓
鐘馗(しょうき)や金太郎、武者絵が描かれた「武者のぼり」に形が変わった。(鐘馗=中国に伝わる道教系の神。)
「旗指者」がこのようにして「武者のぼり」に変わっていきました。
武者のぼりに描かれている絵にはもちろん意味があり、子どもに幸せな人生を送ってほしいという願いが込められていたそうです。
正確な呼び名は「絵のぼり」・「節句幟(せっくのぼり)」絵柄に武者絵が多かったことから通称で武者のぼりと呼ばれたということ。
庶民がその風習を真似るようになったことがきっかけで、日本全国各地に広まったとされています。
「鯉のぼり」は江戸時代に誕生

鯉のぼりの原型は江戸時代中期に誕生しました。
起源となっている武者のぼりには「鯉の滝登り」の図柄が描かれていました。鯉の滝登りは立身出世のシンボル。
この図柄から作られたのが鯉の小旗で、鯉のぼりの原型になります。小旗が時代とともに変化して現在の鯉のぼりになったのです。
現在の立体型の鯉のぼりが主流になったのは、明治時代以降のこと。
大きな真鯉はお父さん~小さい緋鯉は子どもたち~♪

鯉のぼりの歌はみなさん歌えますよね。
大きな真鯉はお父さんで、小さい緋鯉は子ども。
あれっ、お母さんが登場しないではないですか!
鯉のぼりに女性が登場しないのは、端午の節句のときには女性には大事な役割があったからなのです。
5月5日を旧暦で考えると6月の梅雨。
この梅雨の時期は実りに影響が出る大切な時期に五穀豊穣を願う神事を行い、女性たちは身を清めて水の神様に祈りを捧げていたのです。
このような役割があった時期なために女性がいないのです。
鯉のぼりの”吹流し”に意味はある?

鯉のぼりのセットになっている吹流しには意味があるのでしょうか。
吹流しには意味がちゃんとあります。
- 魔除けを意味する
- 日本古来の民間信仰の五行説に基づいたもの
五行説とは、世界の全てが「木・火・土・金・水」の5つの要素で構成されているという考え。
それぞれに色があり、
水引のこの5色が五行を司る色。
- 木:青
- 火:赤
- 土:黄
- 金:白
- 水:黒
互いが作用することでバランスを保ち、悪いことを寄せ付けないという意味があります。
鯉のぼりが現在のような順番になったのは?

どの鯉のぼりも色や順番は同じですよね。
現在の鯉のぼりは、お父さん、お母さん、子どもを表しますよね。
- 真鯉=父親
- 緋鯉=母親
- 青い鯉=子ども
江戸時代は真鯉だけでした。
緋鯉は錦鯉をモデルにしたものと言われ、緋鯉が出回ったのは明治時代で、当時は子どもを表していました。
現在の表し方になったのは、昭和に入ってからのことです。鯉のぼりの色って、真鯉が黒で緋鯉が赤、そして青い鯉が並んでいるのがお馴染みのスタイル。
しかし、色が決まっているのは「真鯉の黒」だけなのです。それぞれの色には吹き出しのように五行説が関係しています。
鯉のぼりの色と意味の由来

それぞれの色にはどのような意味があるのでしょうか。
父親を表し、色は黒
黒は、冬で水を表すのです。五行説での冬は堅く閉ざされた季節で、生き物のほとんどが活動を停止する時期。
水は全ての生物の命の源であり、必要不可欠なものですね。
いるだけで存在感があり、少しのことでは動じずに構える一家の大黒柱である古き時代の父親を表している。
母親を表し、色は赤
赤は「夏の火」を表します。夏はたくさんの生命を育む季節。太陽の陽射しを存分に浴びて、植物も成長しますよね。
また、人間が「火」を手に入れたことで知恵を持ち、文明を築きだしたと言われ、そこから「火」は万物を生み出す源、そして知恵を象徴するものとなったのです。
そんな「火」と「母親」。子どもを産み、生活の知恵をたくさん持ち、子を育てながら家庭を守る。温かいおかあさんという存在ですね。
子どもを表し、色は青
子どもの鯉の青は、「春」「木」を表します。
春は全ての生命がのびのびと活動を始める季節で、草木もどんどん成長します。
春のいきいきとした季節に、草木がすくすくと真っ直ぐに成長する姿は、子どもの成長を表しています。
鯉のぼりの色と表す意味の由来を知ると、平和な家庭を表していることが分かりますね。
それと同時にそれぞれあるべき姿として願っているのでしょう。
ちなみに、下のお子様が増えたときには、緑か紫の鯉を足してあげると良いそうです♪
子どもに「鯉のぼりって何であるの?」と聞かれたら

こいのぼりを題材にした絵本はありますが、子どもに鯉のぼりの歴史について説明するには難しいものです。
歴史の話をしていたら長いし、飽きてしまいます。説明したところで、小さい子なら余計に理解できませんからね。
子どもに説明する場合は、江戸時代とかの話はカット!ざっくり説明してあげましょう。
こんな感じ。
鯉のぼりは、鯉っていくお魚でとても強くて元気なお魚なんだ。
1番大きいのがお父さんで、次がお母さん。青い鯉が子どもなの。
川でも池でも元気に泳いでいるし、山にあるなかなか登れない急な川を登って龍になったというお話だってあるんだよ!
すごく強いお魚だから、大変なこととか苦しいことがあっても、鯉みたいに負けずにがんばろうね!○○くんが、強くてかっこいい男の子になれますようにってお願いして飾ってるんだよ。
こんな感じで説明してあげると分かりやすいですね。参考までに。
まとめ
鯉のぼりの由来は古来中国にありました。端午の節句が、日本で独自の形となり鯉のぼりが飾られるようになり広まったのは江戸時代。現在の真鯉、緋鯉、子どもの鯉という形になったのは、昭和になってから。
それぞれ色には意味があり、平和な家庭を表しています。

5月5日の端午の節句は、男の子の成長を祝い、立身出世を祈願するという日です。
突然、子どもに鯉のぼりが何故飾られるのか、どんな意味があるのか聞かれても、堂々と教えてあげることができますね!
鯉のぼりに関する記事