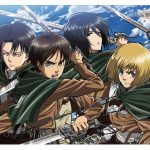- ひらがな以外のしめじの表記ってみたことない
- しめじって漢字あるの?
- しめじってもともとどんな意味?
しめじはスーパーに行けばいつでも置いてありますが、その表示は「しめじ」ですね。
「しめじ」という漢字はあるのでしょうか。
実は「しめじ」はいろんな漢字表記があります。今回は「しめじの漢字」についてご紹介です。

志・目・寺?
占地・湿地(しめじ)とは?

これはたまに見かける
しめじは、秋に各地の雑木林でできるキシメジ科のキノコです。
「香りマツタケ、味シメジ」といわれるほど、味わいが深くいろんな料理に登場する食材です。
そんなしめじですが、スーパーの袋にもパックにも「しめじ」あるいは「シメジ」とひらがなかカタカナで表記されることが多く、漢字で書かれているものを見ることは少ないですね。
それでも、しめじを占地や湿地と書かれているのはたまに見かけるのではないでしょうか。
占地や湿地の由来はどんなものでしょう。
- 占地と書かれる由来
:地面を占めるほどびっしり生えるから - 湿地と書かれる由来
:「湿った地面に生えるから
湿地茸(しめじだけ)と呼ばれていたものが「しめじ」と略されて呼ばれるようになったともいわれています。
そのため、漢字表記でなくひらがな表記が多くなったとも考えられます。
また、現在はしめじも人工栽培がほとんどで、雑木林に自然に生えるしめじが食卓に並ぶこともほとんどありません。
ですから漢字で占地や湿地と表記しても、それがいつも食べているしめじのことだと理解されづらく、ひらがなやカタカナで表記するようになったのかもしれませんね。
王茸(しめじ)とも書く?

きのこの王様?
しめじを漢字で書くときに「王茸」と書くことがあります。漢字の意味からすると、キノコの王様ととれますね。
なぜしめじがキノコの王様?キノコの王様ならマツタケでしょう?もちろんマツタケはお値段でいえばキノコの王様ですね。
しかし「香りマツタケ、味シメジ」とよく言われます。
キノコの中で香りが最も優れているのがマツタケで、味が最も優れているのがしめじということです。
味が一番おいしいからしめじがキノコの王様、「王茸」となり、「王茸」と書いてしめじを意味するようになったのかもしれません。
本しめじとぶなしめじ
ただし、しめじの中にもいろいろ種類があります。
味が一番といわれるしめじは「本しめじ」のことを指します。
普段スーパーで目にしているのは「ぶなしめじ」です。
ぶなしめじはお値段もかなり安いです。
それで「王茸」と呼ぶのはちょっと違いますよね。
本しめじはお値段もそこそこします。100g 1,000円ぐらいするものもあります。
ぶなしめじは100g 100円ぐらい。
本しめじはマツタケほど高価ではないももの、気軽に変える値段でもないですね。
ちょっとお高くてそれでいて味も良いとなれば「王茸」の称号を与えてもいいのではないでしょうか。
しめじの漢字あれこれ

まだまだしめじの漢字はあります
古来の書物にはしめじについての漢字表記は、占地・湿地・王茸以外にもあります。
それらが引用されているものをいくつかご紹介しましょう。
占地茸(しめじ)
笑話の翌朝は、引続き快晴であった。近山裏の谷間には初茸の残り、乾びた占地茸(しめじ)もまだあるだろう… 【泉鏡花著 怨霊借用】
占地茸(しめじ)を一籠、吸口柚まで調えて…この轆轤を窄めた状の市の中を出ると、たちまち仰向けに傘を投げたように四辻が拡がって、往来の人々は骨の数ほど八方へ雨とともに流れ出す。【泉鏡花著 卵塔場の天女】
占治茸(しめじ)
片手懐って、ぬうと立って、笠を被ってる姿というものは、堤防の上に一本占治茸(しめじ)が生えたのに違いません。【泉鏡花著 化鳥】
湿地茸(しめじ)
松茸だとか、湿地茸(しめじ)だとかおいいでなかったのもこの時ばかりで、そして顔の色をおかえなすったのもこの時ばかりで 【泉鏡花著 化鳥】
湿茸(しめじ)
この附近の石占山というところは、文化文政の頃から茸の名所となってはいるが、そこでとける茸は、松茸、湿茸(しめじ)、小萩茸、初茸、老茸、鼠茸というようなものに限ったものです。
そこから毒茸が出て、人を殺したという例はまだ無い。【中山介山著 大菩薩峠:30畜生谷の巻】
「占」か「湿」かの漢字の違いで、しめじが生えている場所やその形態が表されているようですね。
いろいろなしめじ

しめじにもいろいろあるのね
一口にしめじといってもいろんな種類があります。
その名の由来と一緒にいくつかご紹介しましょう。
橅占地(ぶなしめじ)
スーパーに並んでいる身近な、一般的に「しめじ」と認識されているものです。
「ぶな」はブナの倒木から生えるからこの名がつきました。
本占地(ほんしめじ)
「味しめじ」といわしめるしめじが本占地です。
本当のしめじはこれだ!という意味でつけられたともいわれます。
畑占地(はたけしめじ)
畑から生えているのを見つけたためつけられた名前。
最近は人工栽培も可能になりスーパーでも見かけるようになりました。
霜降占地(しもふりしめじ)
霜が降りる晩秋に生えるしめじなのでこの名前がつきました。
食感が良く非常においしく、別の意味で「霜降肉のようなキノコ」という意味もあるのかも。
春占地(はるしめじ)
多くのしめじは秋に生えますが、これは春に生えるためこの名前に。
梅の木の近くに生えるのはウメハルシメジ、桜の木の近くに生えるのは、ノイバラハルシメジと名前も違います。
桜占地(さくらしめじ)
桜色をしたしめじです。
桜の木の近くで生えるのはノイバラハルシメジで、桜色のしめじがサクラシメジとちょっとわかりづらいですね。
布袋占地(ほていしめじ)
七福神の布袋様が由来のしめじです。
軸の下の部分が膨らんでいる形状が布袋様のお腹のように見えるためこのような縁起の良い名前がつきました。
大黒本占地(だいこくほんしめじ)
こちらも布袋占地同様七福神の大黒様が由来です。
ぷっくりとなっている軸が大黒様のお腹を連想させます。
仁王占地(におうしめじ)

お寺の入り口に立っている仁王様を彷彿させる巨大なキノコのことです。
巨大キノコといえば、仁王占地のことです。
釈迦占地(しゃかしめじ)

お釈迦様の髪型である「螺髪」のような生え方をするのでこのような名前になりました。
岐阜県では「香りマツタケ、味シメジ、食って美味いはシャカシメジ」といわれるほど美味しいしめじのようです。
まとめ
「香りマツタケ、味シメジ」といわれるだけあり、種類も多く、その漢字表記もいくつかあるしめじです。
食べ方もバター炒めやアヒージョ、おつまみからメインまでといろんなバリエーションを楽しめる食材です。
スーパーで売られている姿は地味で目立ちませんが、実は栄養価も高くすぐれた食材なんですよ。
スーパーに行ったらいろいろと見比べてみるのも面白いでしょう。

今日のメインはしめじ料理で。
シメジに関する記事