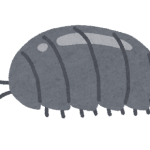- ザリガニを飼育する方法!
- ザリガニにはどんな種類がある?
- 水槽の環境や餌で臭いを抑えられる?
お子さまに「ザリガニを飼いたい!」とねだられたことはありませんか?
生き物を飼うことは責任もあり大変ですが、子どもにとってはとても良い経験になります。
おそらくこの機会にザリガニを飼育してみようかな?とお考えの方も多いですよね。

特にザリガニは初心者でも簡単に飼うことができるのでオススメですよ。
今回はザリガニを飼育する方法について、徹底的にご紹介させていただきたいと思います!
また、「ザリガニは飼ってみたいけど、臭くなるのは嫌だ…。」
と思っている方のために、ザリガニの臭いを抑えるための工夫もまとめましたので、最後までゆっくりご覧になってくださいね。
ザリガニを飼育する方法!

それでは早速ですが、ザリガニを飼育してみたいと思います!
昔よく学校の教室でもザリガニの飼育をやっていましたよね。
また小川や田んぼなんかで、ザリガニを捕まえて遊んだことのある方もいらっしゃるかと思います。
こんな風に我々が普段身近で目にする、あの全身真っ赤な風貌をしているザリガニは「アメリカザリガニ」といいます。
でも実は、ザリガニってアメリカザリガニだけじゃなくてもっと沢山の種類が存在するんです。
ザリガニの種類
ザリガニには野生の品種や、野生ではないけれども飼育専用に流通している品種など様々な種類があります。
ザリガニを飼ってみようとお考えの方は、まずどんな種類のザリガニを飼ってみたいかな?とザックリ考えてみるところから始めましょう。
アメリカザリガニ

現在私たちの周りでもっとも多く見られるザリガニは、このアメリカザリガニです。
見た目は赤色や褐色で、体長8〜12センチほどの大きさをしています。中には最大20センチほどにまで成長することもあるんだそうですよ。
雑食性でとにかく環境適応力が高いため、あっと言う間に繁殖します。
実はこのアメリカザリガニ、元はと言えばウシガエルの餌として、その名の通りアメリカから持ち込まれたものでした。
しかし爆発的に個体数を増やし、今や在来種を脅やかす存在として「日本の侵略的外来種100選」に指定されているほどなんです。
ニホンザリガニ
一方、こちらは野生の個体を見る機会が滅多にありませんが、日本に古来から存在している在来種のニホンザリガニです。
見た目は茶色の褐色で、何となくポッテリしているのが特徴です。
体長は5、6センチほどですから比較的小さめのザリガニで可愛いですよね。
基本的に水温の低い綺麗な水にしか生息できませんから、昔は北日本の川に沢山存在していましたが、今では環境の変化と共にだいぶ個体数も減ってしまいました。
秋田県にある生息地は「天然記念物」に指定されているほどです。
ウチダザリガニ
このウチダザリガニは何とアメリカザリガニよりひと回りも大きい個体で、体長は15センチほどあります。
元々ウチダザリガニは食用としてアメリカから持ち込まれたものでしたが、日本にいる在来種を脅かすなど生態系に影響を与えるとして「日本の侵略的外来種100選」に指定されています。
またあらゆる水温に耐えることができるのが特徴で、−33℃〜30℃でも生息できると言われています。
そのため、あっと言う間に生息地を広げて繁殖してしまうのです。
ドワーフザリガニ

続いては、体長4センチほどの可愛らしいザリガニのご紹介です。
ドワーフザリガニは、ペットショップなどで販売されていますが名前が色々あります。
- 「メキシカンドワーフクレイフィッシュ」
- 「テキサスドワーフザリガニ」
- 「メキシカンドワーフザリガニ」
- 「テキサスドワーフクレイフィッシュ」
- 「オレンジドワーフザリガニ」
- 「オレンジドワーフクレイフィッシュ」
これらは全てドワーフザリガニのことを意味していますので、混乱しないでくださいね。
ミステリークレイフィッシュ
見た目は大理石のようで、大きさはニホンザリガニと同じくらいのミステリークレイフィッシュは、なんとザリガニの中で唯一「単為生殖」が可能な個体なんです。
「単為生殖」とは、オスがいなくてもメスだけで繁殖が可能という不思議な生態のことをいいます。
発見された当時はそんな不思議な生態が話題になり、一部の愛好家のみが飼育できるような状況でしたが、今では誰でも手に入れることができるようになりました。
ちなみにミステリークレイフィッシュと呼んでいるのは日本だけで、世界では「マーブルクレイフィッシュ」という名前が一般的です。
フロリダハマー
美しい青色のザリガニ、フロリダハマーは元はと言えばハマー氏が品種改良して作り出したザリガニでした。
流行り始めた当初はまだまだ個体数が少なく、1匹あたり数万円もした高級ザリガニだったそうですよ。
今では誰でも1500円〜ほどで手に入れることができるようになりました。
まずはザリガニを用意する

当たり前ですがザリガニを飼育するには、まずザリガニを用意しなければ始まりません。
ということで、先ほどご紹介させていただいたザリガニの中から好きな種類を選んで用意しましょう。
売っているものを買ってきても良いですし、知り合いから譲り受けてもいいですね。
最近では縁日などでも金魚すくいならぬ、「ザリガニすくい」なんてものがあったりもします。
ちなみに基本的にはどの種類のザリガニもペットショップやアクアショップなどで手に入れることができます。
ただし、やっぱり自分で捕まえてきたザリガニを飼ってみたい!という方は、ザリガニを釣ってくるところから始めなくてはなりません。
ザリガニの捕まえ方について

ザリガニ釣りはとても簡単ですので、お子さまや初心者でも沢山釣れますよ!
昔はよく近所の川でザリガニ釣りをしたものですが、最近の子どもは経験したことがない子も多いですよね。
そもそもザリガニがいるような川や池、用水路なんかもあまり見かけなくなってしまいました。
しかし探してみれば意外と簡単に見つかったりもしますので、自然と触れ合う貴重な機会として、まずはザリガニ釣りを体験してみることをオススメします。
ザリガニ釣りに用意するもの
基本的にザリガニ釣りの道具はすべてその辺にあるものでOKです。
ある日いきなり思い立ってもすぐに釣りに行けるのが魅力です。
- 割り箸や園芸用の支柱
- タコ糸や釣り糸
- バケツ
- 網
- クリップ
- 餌
これらの道具が手元に無い場合、もしも代替できるようなものがあればそれでもOKです。
ザリガニは本当に簡単に釣れるので、あまり神経質に道具を揃えなくても大丈夫です。
ザリガニはどこにいるの?
ザリガニは水のあるところであれば結構どこにでもいます。
小川や池、用水路、田んぼの側溝、溜め池….などのザリガニスポットをまずは探してみてください。
ちなみにお子さまが釣りに出掛けるときはなるべく誰か大人の方が同伴するようにしてください。
くれぐれも雨が降ったあとの増水しているときなどは、足を滑らせたりしないように気をつけてくださいね。
ザリガニ釣りのベストシーズンは?
基本的には一年中捕まえることができますが、ザリガニは冬になると活動量が減って冬眠状態に入ってしまいます。
ですからベストシーズンは春から秋にかけて、だいたい5〜11月頃になります。
ザリガニの釣り方

では、道具を用意したら早速ザリガニを釣りに出掛けましょう。
- 割り箸や園芸用の支柱を釣り竿に見立て、タコ糸を結び付けます。
- さらに棒に結び付けた反対側のタコ糸の先には、クリップを結びます。
- そしてクリップに餌を挟んだら釣り竿の出来上がりです。
- 水の透明度が高くてザリガニの姿が見えている場合には、ザリガニの目の前に釣り竿の餌を垂らしてあげましょう。
- 水が濁って見えない場合には、石や水草の陰などに隠れている場合が多いので、そのポイント周辺に餌を垂らしましょう。
- ザリガニが餌に食いついたら慌てずにゆっくりと引き上げるのがコツです。
- ザリガニがしっかりハサミで餌を掴むまでは引き上げないようにしましょう。
- ある程度持ち上げたら、下から網ですくってあげると確実にゲットできますよ。
餌のオススメは?

ザリガニは雑食ですので、基本はなんでも食べます。
基本的には家の冷蔵庫の中にある残り物で問題ありませんが、魚介系の匂いが強めな食材の方がよく釣れるみたいですよ。
例えば、
ちくわ、スルメ、魚のアラ、いりこ、むきエビ、かまぼこ、ソーセージ
中でも特にオススメは、スルメです。
スルメはクリップに留めやすく、尚且つ濡れてもちぎれにくいので何度も使えます。
またクリップがない場合には、ちくわを輪切りにしたものを使えばヒモに結びやすいのでこちらもオススメです。
ザリガニのオスとメスの見分け方は?
ザリガニを準備したら、早速飼育していきましょう…と言いたいところですが、まず手元にあるザリガニがオスかメスか見極めるところから始めたいと思います。
なぜか?というと、ザリガニはどちらか片方の性別だけを沢山水槽に入れておくと、共食いしてしまう可能性があるからです。
1匹だけを飼う場合はどちらでも問題ありませんが、何匹か一緒に入れて飼う場合はバランス良くオスとメスを入れてあげましょう。
最初に準備するもの

続いてはザリガニの飼育に必要な道具をご紹介したいと思います。
水槽や飼育ケース
まずなんといってもザリガニを入れておくお家が必要ですよね。
水槽や飼育ケースを用意しましょう。
プラスチック製は扱いやすいですが、使っていくうちにだんだん表面が白っぽくなって外から見えづらくなってきますから、オススメはガラス製です。
なるべく大きな水槽で広々と育ててあげるのが望ましいとされています。
30センチ程度の小さな水槽の場合は多くても2匹までにしておきましょう。
ちなみに水槽で飼う場合には、ザリガニが脱走してしまう可能性があるのでなるべく蓋つきのものを選ぶと良いでしょう。
濾過フィルター
飼育ケースで水を少しだけ入れて飼育することも可能ですが、できれば水槽にたっぷりと水を入れて育ててあげた方が良いです。
その場合、濾過フィルターは欠かせません。濾過フィルターを使わないとすぐに水が濁って汚くなってしまうからです。
きちんと濾過フィルターを入れておけば、掃除する頻度も減ってラクですよ。
エアポンプ
また、水槽に水をたっぷりと入れて飼育する場合にはエアポンプも必要です。
いくら水中の生物といえども、酸素が足りないと酸欠になってしまいますからね…。
よく水槽にブクブクと泡を出しているあの装置です。
比較的安いものもありますから、きちんと設置してあげましょう。
砂
ザリガニ飼育の場合、水槽の底に敷く砂がけっこう重要な役割を果たしています。
なぜならザリガニは脱皮をした後、触覚の根元にある「平衡胞」という穴に自ら砂を入れて平衡感覚を調整しているからです。
そのため、金魚鉢用のもので構いませんからなるべく細かい砂を用意して入れるようにしましょう。
隠れ家
ザリガニがストレスなく長生きするためには隠れ家も必要です。
ザリガニは基本的に夜行性のため、日中は隠れ家の中でヒッソリと身を潜めていることが多いのです。
ザリガニが隠れるものであればなんでもいいのですが、使いやすいのは塩化ビニール製のパイプや植木鉢製のものです。
水槽に水をたっぷりと入れる場合はあまり軽いと浮いてきてしまうため、ある程度重量のあるものを選びましょう。
石や水草
石や水草もザリガニの隠れ家としての役割を果たします。
特に水草については小さな子ザリガニが掴まる場所として利用したり、お腹が空いたときの非常食にもなりますので入れておくと良いでしょう。
水の作り方は?

ザリガニの水槽に入れる水については、何か気をつける点はあるのでしょうか?
よく「水道水をそのまま入れるのは良くない」とか、「きちんとカルキ抜きする必要がある」なんて言われていますよね。
しかしザリガニって意外と生命力が強いので、そこまで神経質にカルキ抜きしなくても大丈夫だったりします。
ただザリガニを少しでも長生きさせたいのであれば、カルキ抜きをした水の中で飼育した方がいいのはもちろんです。
ホームセンターやアクアショップ、インターネットの通販などでカルキ抜きの薬剤が売られていますから、それを利用するのが簡単です。
もしくは晴れた日に、バケツいっぱいに水を入れて1日太陽に当てておくとカルキ抜きの効果がありますから試してみてくださいね。
餌のやり方は?
続いては餌についてですが、ザリガニは雑食ですから基本的には何でも食べます。
スルメ、サキイカ、煮干し、ちくわ、ソーセージ、米、パン、麺、ほうれん草、レタス…などなど、とにかく何でも食べられます。
ただし、ザリガニも栄養バランスを考えてきちんと動物性食品と植物性食品の両方を与えてあげなくてはなりません。
つまり、スルメや煮干し、ちくわなんかを与えたら、ほうれん草やレタスなども一緒に与えると良いという訳です。
餌は多すぎると水槽を汚しますし、少なすぎると共食いの原因となってしまいます。
1日1〜2回、様子をみながら少しづつ与えてみてください。

調整が難しいようであれば、ザリガニ用の餌を与えるのもオススメです。
ザリガニ用の餌であれば栄養バランスも良く、水槽も汚しにくくなっています。
初心者はザリガニ用の餌から与えてみた方がいいかもしれませんね。
水槽の掃除について
ザリガニは雑食で様々な動物性の餌を食べますので、比較的水槽の中が濁りやすいのです。
ですから、小まめに水槽の中の水を換えてあげる必要があります。
水槽の水の換え方は一気に全部換えるのではなく、3分の1だけ抜いて換えるのがポイントです。
頻度としては、1週間に1回は水の入れ換えを行なってあげるのが望ましいでしょう。
ザリガニの飼育で注意すべきポイント
ザリガニの飼育については、基本的に以上の飼育方法を守っていれば比較的誰でも簡単にできます。
以下は、さらにザリガニ飼育で注意すべき点についてご紹介していきます。
冬は冬眠をさせましょう
ザリガニは冬は冬眠する生き物ですから、冬になったらきちんと冬眠できる環境を整えてあげましょう。
秋には冬眠に向けてたっぷりと栄養をつけさせます。
冬になったら水温を10℃以下に保てば自然と冬眠状態に入ります。
ただし暖かい室内で飼育する場合には無理に冬眠させる必要もありません。
もしも卵を産んだら?

もしもザリガニが卵を産んだらどうしたら良いのでしょうか?
ザリガニのメスは、産卵したらお腹に100個以上もの卵をくっ付けます。
ひっくり返したらビッチリ卵がくっ付いているのがすぐに分かるかと思います。
もしも卵を産んだら、必ず他のザリガニと離して別の水槽に入れてあげましょう。
だいたい2〜4週間で孵化しますので、赤ちゃんザリガニが産まれたら茹でたほうれん草や金魚の餌などを与えてみましょう。
共食いを避けるために

ザリガニは雑食がゆえに、お腹が空いたら仲間を食べてしまうことがあります。
ですから、ひとつの水槽に何匹も入れて飼育する場合には共食いを避けるために注意しなければなりません。
基本的には単独飼いが好ましいので、一個の水槽には1匹だけ入れるのが理想です。
しかし、何匹かいる場合にはそんなことも言っていられなかったりしますよね。
そんな時はなるべく大きな水槽(60センチ以上〜)で、飼ってあげるのが良いでしょう。
また何匹か入れる場合には、必ず「オスだけ」、「メスだけ」という組み合わせは避けて、オスメスバランス良く入れてあげます。
大きい水槽でも、なるべくオスメス二組くらいまでにしておきましょう。
そして複数のザリガニがいる水槽には、必ずザリガニの数だけ隠れ家を用意してください。

共食いを避けるには、基本的に空腹状態にしないことが重要です。
餌を小まめに与えることはもちろん、お腹が空いたときに食べられるように水草や流木を入れておくことも大切です。
ザリガニがお腹を空かせていないか?常にチェックしてあげましょう。
水槽の環境や餌で臭いを抑えられる?

ザリガニは可愛いけど、飼うのは臭いから嫌だな…。
こんな風にザリガニは臭いってイメージを持っている方も多いかと思います。
でもザリガニが臭いというのは誤解で、実は臭いのはザリガニ自体が原因ではありませんでした。
ザリガニを自宅で飼育する場合も、水槽の環境や餌を工夫することで臭いを抑えることだって可能なんです!
ということで、ザリガニが臭い本当の原因とザリガニの臭いを抑えるための方法についてご紹介していきたいと思います。
どうしてザリガニは臭いの?
ザリガニが臭い原因は、ザリガニそのものが発している臭い…というわけではありません。
実はザリガニを飼育している水槽の水が、汚れてしまっていることによる悪臭だったのです。
水が汚れる原因はいくつかありますが、もっとも大きな要因としては「ザリガニが食べ散らかした餌の食べカス」ではないかとされています。

ザリガニが餌を食べる様子を見たことはありますか?
けっこう豪快に撒き散らしながら食べているんですよね。しかも一度撒き散らしたエサには見向きもしません。
その姿が可愛かったりもするんですが、この撒き散らした食べカスが水槽の水を汚す主な原因となってしまうわけです。
食べカスをそのままにしておくと徐々に腐敗して、ザリガニの排泄物などと混ざり合い、悪臭を放つようになるのです。
ザリガニの水槽の臭いを抑える方法
ザリガニが臭い原因は水槽の水であることがよくわかりました。
では、水槽の水を汚さないためにはいったいどんなことを工夫すれば良いのでしょうか?
まず前提として、ザリガニを飼育する場合はたっぷりと水を入れた水槽で育てることをオススメします。
実はザリガニは、虫を入れる飼育ケースの中などで、背中が浸かるくらいの少量の水を入れただけで飼育できたりするんです。
少量の水で育てるメリットは、掃除がしやすいこと、水交換がやりやすいこと…くらいでしょうか。

しかし飼育ケースの水が少ないと、なにしろ臭いです。
なぜかというと、水が少ないってことは食べカスや排泄物を含む濃度がそれだけ高いってことになるからです。
これだと、頻繁に水を換えないとすぐに臭くなってしまいます。
ですから、最初からたっぷりと水を入れてあげた方が水が汚れにくく、水換えの頻度も少なく済むというわけです。
濾過フィルターやエアポンプの設置
また、たっぷりと水を入れた水槽で飼育するには、ザリガニの酸欠を防ぐためにエアポンプの設置が必要である…という話は先ほどもしましたよね。
このエアポンプ、実は水質を綺麗に保つためにも役立っているんです。
エアポンプが作動することで水がうまく循環しますが、このおかげで水質を綺麗にしてくれるバクテリアが沢山発生するんです。
また、濾過フィルターの設置も忘れないでください。
濾過フィルターがあるだけで掃除の頻度が減るくらい、かなり水質の状態が良くなります。
小まめに水の交換を

水槽の水質を綺麗に保つためには、もちろん水槽の掃除も欠かせません。
頻度としては1週間に1回程度で構いませんので、きちんと水の交換をしましょう。
このときのポイントは、全ての水を交換するのではなく、3分の1程度にとどめることです。
水交換用のホースなどを使うと簡単で便利ですよ。
バクテリアの力を借りる
水中のバクテリアは我々の目には見えないくらい小さな生き物ですが、実は大きな働きをしてくれています。

悪臭を引き起こす物質を自然に分解してくれるすごい存在なんです。
先ほど小まめに水の交換をして掃除する必要がある…という話をしましたが、一度に全ての水を交換しないのは、バクテリアを繁殖させて定着してもらうためなんです。
最初から定着させるのは難しいので、液状のバクテリアを水槽に入れる方法もあります。
初心者はバクテリアを買ってきて投入するのがオススメですよ。
ザリガニ専用の砂を使う
ザリガニの飼育には水槽の底に砂を敷く必要がある、という話をしましたよね。
この砂ですが、実はザリガニ専用の消臭効果のあるタイプのものが市販されているんです。
この砂には、水質を汚す原因となっている物質を除去する効果があります。
ザリガニの水槽の臭いが気になる場合には、この砂を利用してみるのも一つの手段です。
餌を工夫することも重要
ザリガニの餌の食べカスが水槽を汚す主な原因である…ということは、水槽を汚しにくい餌を与えることも効果的です。
やはりスルメやさきいか、魚、ちくわ…などの動物性の餌は水槽の水を汚しやすいので、あまりあげないようにしたいものです。

そもそも餌のあげすぎに注意しなければなりません。
餌を沢山与えすぎると、食べきれない餌はそのまま食べカスとなって水槽を汚す原因となってしまいます。
ちょっとづつ与えながら様子をみて、足りないようであればまた少し与える…という風に餌やりしましょう。
またもしもザリガニが餌を食べきれなかった場合には、すぐに残った餌を取り除くようにしましょう。
色々気にするのが面倒なときは、ザリガニ専用の餌で水槽の水を汚しにくいタイプのものも売られています。
ホームセンターやアクアショップ、インターネットの通販などで手に入れることができますので最初からこの餌を与えるのもオススメですよ。
まとめ
「ザリガニを飼ってみたい!」と考えていらっしゃる方のために、ザリガニの飼育方法について徹底的にご紹介させていただきましたが、如何でしたでしょうか。
ザリガニは比較的どんな状況でも飼育できて、雑食でなんでも食べてくれるので、なんだか今日からでも飼えそうな気がしませんでしたか?

初心者でも簡単に飼育できるのが、ザリガニの魅力ですよね。
また、ザリガニは飼ってみたいけど臭いが気になる…という方も、ザリガニ自体が臭いわけではありません。
飼育環境による水の汚れが臭いを引き起こす原因である、ということがわかっていただけたかと思います。
臭いを抑えるためには、食べカスを出さないように少しづつ餌を与えたり、餌の種類を工夫することが有効です。
また水質を綺麗に保つために、水量を増やしたり、小まめに水を換えたり、バクテリアの力を借りたりすることも重要とされています。
水槽が臭くなったらザリガニの飼育も楽しくなくなってしまいますし、何よりもザリガニが長生きするためには水質を綺麗にすることが大切です。
生き物を育てることはとても貴重な経験です。是非皆さんも楽しいザリガニの飼育を始めてみましょう!
ザリガニについての記事